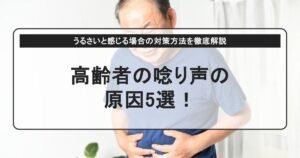「最近、親が何にも興味を示さなくなった…」
「テレビを見ていても反応が薄く、無表情でいることが増えた…」
このように高齢者が無気力な状態に陥り、心配や不安を感じていませんか?
これはただ「やる気がない」という状態ではなく、「アパシー(無気力症候群)」という症状かもしれません。
本記事では、高齢者に見られる無気力症候群「アパシー」の特徴や原因、家族ができる改善策について解説します。
アパシーの知識を身につけることで、高齢者への適切な対応が可能になります。
アパシーと似た状態にうつ病がありますが、違いについては以下の記事を参考にしてください。
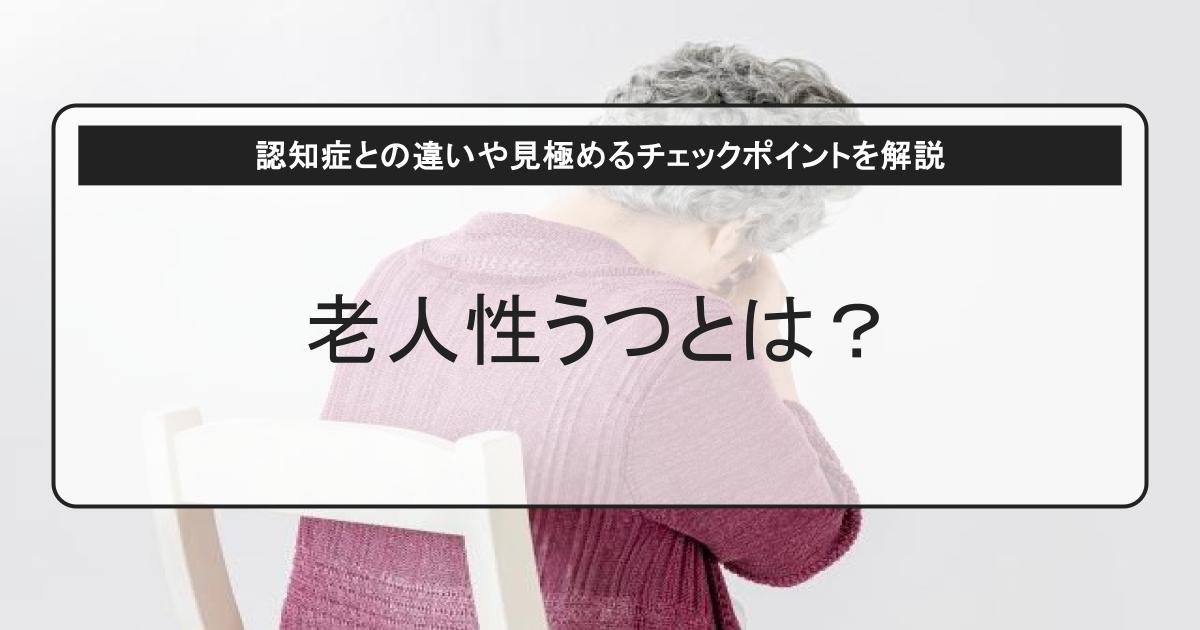
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の無気力(アパシー)に関する基礎知識
アパシーは「意欲の低下」が見られる症候群で、高齢者によく見られる症状と言えます。
一時的な「やる気のなさ」とは異なり、持続的に意欲や関心が失われる状態が特徴です。
ここでは、無気力症候群「アパシー」について詳しく解説します。
アパシーと加齢の関係
アパシーは、加齢との関係性が高い症状です。
加齢に伴い、脳の「前頭前野」という部位の機能が低下しやすくなります。
前頭前野は、意欲・感情・行動の調整に重要な役割を担っています。
神経伝達物質の減少や脳血流の低下により、加齢とともにアパシーのリスクが高まるのです。
高齢者のアパシーの問題点
高齢者がアパシーになると、身体機能の低下を招くケースが多いです。
無気力によって活動意欲が減少すると、筋力低下や身体機能の衰えが加速します。
また、脳への刺激が減ることで、認知機能の低下も進行しやすくなるでしょう。
さらに、高齢者の孤立も問題となっており、他者との交流を避け、孤独感が強まるケースも珍しくありません。
介護負担の増加やQOL(生活の質)の低下などの問題点を放置すると、健康寿命の短縮につながる可能性があります。
無気力症候群「アパシー」の状態
アパシーの状態では、以前は楽しんでいた活動や周囲のことに興味を示さなくなります。
自発的な行動が減り、促されないと動かない傾向があります。
また、喜怒哀楽の感情表現が乏しくなることも特徴的です。
例えば、かつては園芸が趣味だった方が植物の世話をしなくなったり、好きな番組を見ても表情が変わらなくなったりするケースがあります。
65歳以上の高齢者の約3割がアパシー
ある研究によると、65歳以上の高齢者の約3割がアパシーという結果があります。
アパシーの高齢者は、慢性疾患や認知症患者についての報告も多いです。
参考:浜松医科大学 髙部 さやか,渡井 いずみ「地域在住高齢者におけるアパシーとソーシャル・キャピタル、閉じこもり、外出頻度との関連検討」
アパシーのセルフチェックと重症度
アパシーのセルフチェックとして、活動量の低下や新しいことへの意欲減退があります。
友人や家族に会うことに関心がなく、将来の計画や目標が浮かばないケースも多いです。
アパシーの重症度は、以下の3段階に分けられます。
- 軽度:趣味や社会活動への関心が低下
- 中等度:自発性が明らかに低下
- 重度:基本的な日常生活動作の減少
高齢者が無気力症候群「アパシー」になる原因
高齢者のアパシーには、以下のような要因が関わっています。
- 刺激の少ない環境
- 慢性疾患や認知症初期の症状
- 脳機能の低下
- 薬の副作用
アパシーの原因を理解することで、高齢者への適切な対応が可能になるでしょう。
それぞれについて、解説します。
刺激の少ない環境
高齢者は、退職による社会的役割の喪失や環境の変化によって、アパシーを引き起こす場合があります。
外出機会や交流の減少も、無気力につながるでしょう。
新しい環境への適応が困難となりやすく、無気力状態が生じる原因となります。
慢性疾患や認知症初期の症状
アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症、パーキンソン病などの疾患はアパシーと関連性が高いとされています。
特に前頭葉の機能障害を伴う疾患では、アパシーが高頻度で見られるでしょう。
脳機能の低下
加齢や疾患により脳機能が低下すると、アパシーが生じやすくなります。
意欲や動機づけに重要な役割を果たしているのです。
高齢者の意欲を引き出し、脳の機能変化を理解することが、対応への第一歩となるでしょう。
薬の副作用
薬の副作用で、アパシーが生じることがあります。
高齢者は複数の薬を服用していることが多く、薬の相互作用も影響するでしょう。
薬剤の調整によって症状が改善することもあるため、医師への相談が重要です。
家族や介護者ができる高齢者への3つのサポート
アパシーの高齢者をサポートする家族や介護者の役割は重要です。
以下のようなサポートが、進行の予防効果に期待できます。
- 高齢者の状態変化を早期発見
- 高齢者とのコミュニケーションの工夫
- 高齢者の生活環境の調整
高齢者の状態変化を早期発見
高齢者の状態変化を早期発見することで、進行予防に期待できます。
高齢者の興味の減退や表情の乏しさ・会話の減少・自発性の低下などの変化に気づくことが大切です。
上記のような状態が2週間以上続く場合は、アパシーの可能性を考慮すべきでしょう。
早期発見が症状改善の鍵となるので、高齢者の状態の変化に気づいたら早めに専門家へ相談してください。
高齢者とのコミュニケーションの工夫
高齢者には、簡潔ではっきりと話しかけるコミュニケーションを取るようにしましょう。
非言語コミュニケーションも活用し、感情を込めて話しかけることも大切です。
例えば「何をしたいですか?」ではなく「散歩と読書、どちらがいいですか?」のように具体的な選択肢を提案すると効果的です。
高齢者とのコミュニケーションに不安がある方は、以下の記事を参考にしてください。
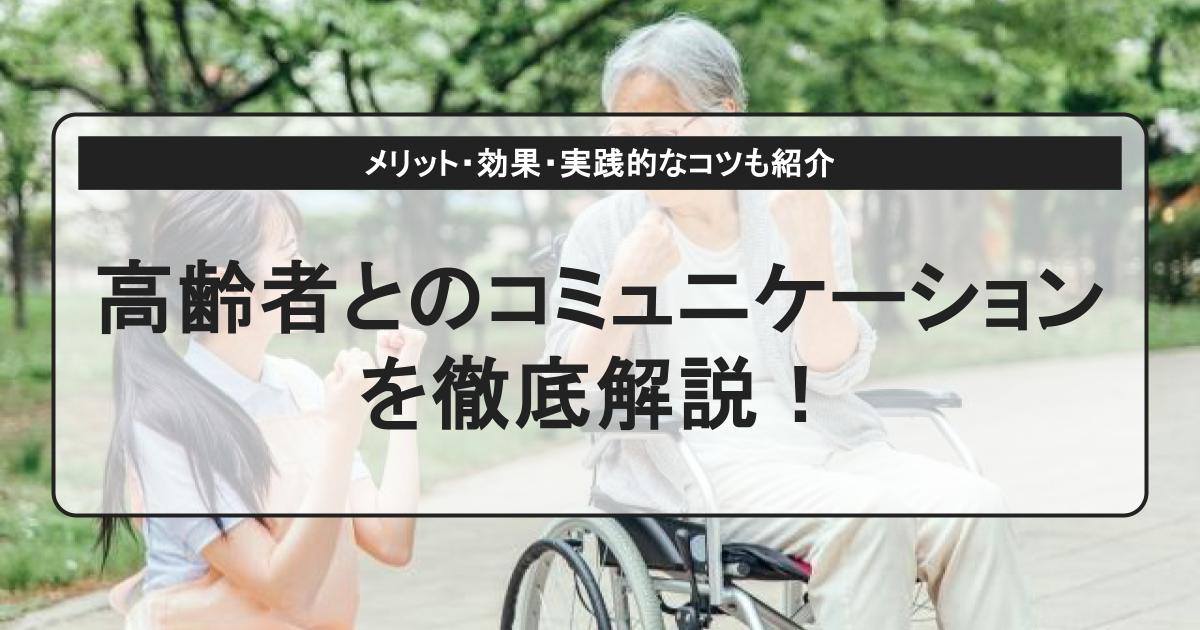
高齢者の生活環境の調整
高齢者の暮らす環境にも、適度な刺激のある空間づくりが重要です。
五感を刺激する工夫や思い出の品を置くことも効果的でしょう。
安全に活動できるスペースの確保も忘れてはなりません。
スケジュールを作成して視覚的に予定を示すことで、「何をすればよいか分からない」状態を減らすこともおすすめです。
高齢者を無気力症候群「アパシー」から意欲を引き出す6つの方法
高齢者のアパシーから意欲を引き出すには、以下の6つの方法が有効的です。
- 生活習慣の見直し
- 人との交流の機会を増やす
- 趣味や楽しみを再発見
- 高齢者の可能な範囲で自立を促す
- 一人時間も満喫できるようにする
- 医療機関を受診する
それぞれの方法について見ていきましょう。
生活習慣の見直し
高齢者の生活リズムを規則正しく整えることが、アパシー改善の基本となります。
バランスの良い食事や適度な運動も大切です。
また、日光を浴びる機会を増やすことも効果的でしょう。
特に朝の日光浴は体内時計を整え、セロトニンの分泌を促進するため、気分の改善に効果が期待できます。
人との交流の機会を増やす
家族や友人との定期的な交流や地域活動への参加は、脳への刺激となります。
デイサービスの利用やボランティア活動も社会とのつながりを維持するのに役立つでしょう。
人との交流は感情や意欲を引き出す効果に期待でき、積極的なコミュニケーションが心の活性化につながります。
趣味や楽しみを再発見
高齢者が以前楽しんでいた趣味を再開することで、意欲が湧きやすくなります。
音楽を聴いたり、創作活動を行ったりする時間も効果的です。
特に音楽療法は感情を刺激し意欲を引き出すと言われ、懐かしい曲は記憶を呼び覚まし、感情表現を豊かにします。
高齢者の可能な範囲で自立を促す
高齢者が日常生活での役割を持ってもらうことで、自己肯定感が高まります。
選択肢を提示して、自己決定の機会を作り、成功体験を積み重ねることで自信回復につなげましょう。
「やってあげる」介護ではなく、「見守る」介護を心がけることが意欲を出すために効果的です。
一人時間も満喫できるようにする
高齢者にとって質の高い一人時間も、意欲改善に役立ちます。
一人でも楽しめる活動を用意することで、家族や介護者がいない時間にも意欲を引き出すことに期待できます。
医療機関を受診する
高齢者の症状が続いたり悪化したりする場合は、専門医への相談が必要です。
専門医により、薬物療法が検討されることもあります。
医学的なアプローチも意欲改善の選択肢の一つとして捉えましょう。
高齢者を無気力症候群「アパシー」からの改善を目指しましょう
高齢者のアパシーは、適切なアプローチが必要な症状です。
特に早期発見・原因の特定・環境調整が重要となります。
アパシーの高齢者には、焦らず・否定せず・共感を示す態度で接することが何より大切です。
高齢者への適切な理解と対応で、QOL(生活の質)の向上を目指していきましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら