「なんとなく物忘れが増えてボケ始めてる気がする…」
「最近、親の言動が認知症ではないかと心配…」
上記のように、認知症に対して不安を抱える人も多いでしょう。
平均寿命が男女ともに80歳を超える日本人にとって、認知症の発症は他人事ではありません。
ただし早めに認知症予防に取り組めば、発症のリスクを下げ、進行を遅らせる効果に期待できます。
本記事では、高齢者の「ボケ防止」に効果が期待される生活習慣や日常での工夫、年齢別の認知症予防策を解説します。
もし一人暮らしをしている高齢者が身内にいれば、以下の記事もあわせて読んでみてください。

- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者のボケ防止はなぜ必要?
認知症とは、脳の機能が低下し、記憶や判断力に障害が出る病気の総称です。
厚生労働省の調査では、2022年の認知症の高齢者は約443万人、軽度認知障害の方は約559万人と推計されているのです。
高齢者の約 3.6 人に1人が、認知症またはその予備群ということになります。
認知症が進行すると日常生活に支障が現れはじめ、一人での生活が困難になってきます。
高齢者が少しでも長くボケないように過ごすことが、介護者の負担軽減につながるのです。
認知症は何歳から始まるのか?
認知症の中でもアルツハイマー型認知症は、65歳以上の高齢者に多く見られますが、発症のタイミングには個人差があります。
認知症の原因は、脳細胞の変性・生活習慣病・遺伝などと言われていますが、未だ解明されていない部分も多いです。
また若年性認知症であれば、40代〜50代で発症するため、年齢だけで判断するのは難しいケースもあります。
高齢者における認知症の影響とボケ防止の重要性
高齢者が認知症を発症すると、日常生活に支障をきたし、普段の買い物・金銭管理・服薬管理など、生活の中で当たり前にできていたことが難しくなります。
本人だけでなく、家族や周囲への負担も大きくなるため、早いうちから予防に取り組むことが重要です。
生活の中で意識的に脳への刺激や、運動習慣などの行動を継続することが、認知症予防につながります。
高齢者の心身の健康を守ることが、将来の自立した生活を支えるのです。
今日から始める!高齢者の認知機能維持に役立つ4つの生活習慣
高齢者が今日から始められる認知機能維持に役立つ生活習慣は、以下の4つです。
- 健康的な食事で脳に栄養を送る
- 毎日の運動習慣で体を元気にする
- ストレスを減らして心の健康を保つ
- 社会参加で脳を活性化させる
一つずつ解説するので、生活に取り入れていきましょう。
1.健康的な食事で脳に栄養を送る
高齢者は、健康的な食事で脳に栄養を送ることが重要です。
高齢者の脳の健康を保つには、バランスの良い食生活が欠かせません。
塩分や脂肪分の摂りすぎは、生活習慣病を引き起こす原因となり、認知症のリスクを高めるため注意しましょう。
特に青魚に含まれるDHA・EPA、野菜や果物に豊富な抗酸化物質は、脳機能の維持に効果が期待できます。
また、高齢者の健康維持に欠かせない栄養素の一つであるたんぱく質については、以下の記事で詳しく解説しています。

2.毎日の運動習慣で体を元気にする
高齢者にとって毎日の運動習慣はとても大切です。
運動を習慣化することで脳への血流を促進し、認知機能の低下を防ぐ効果があります。
ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で毎日続けることがポイントです。
運動を習慣化することで、心身ともに健康な状態を保てるでしょう。
高齢者が運動する際の目安や注意点については、以下の記事で解説しているのであわせて読んでみてください。
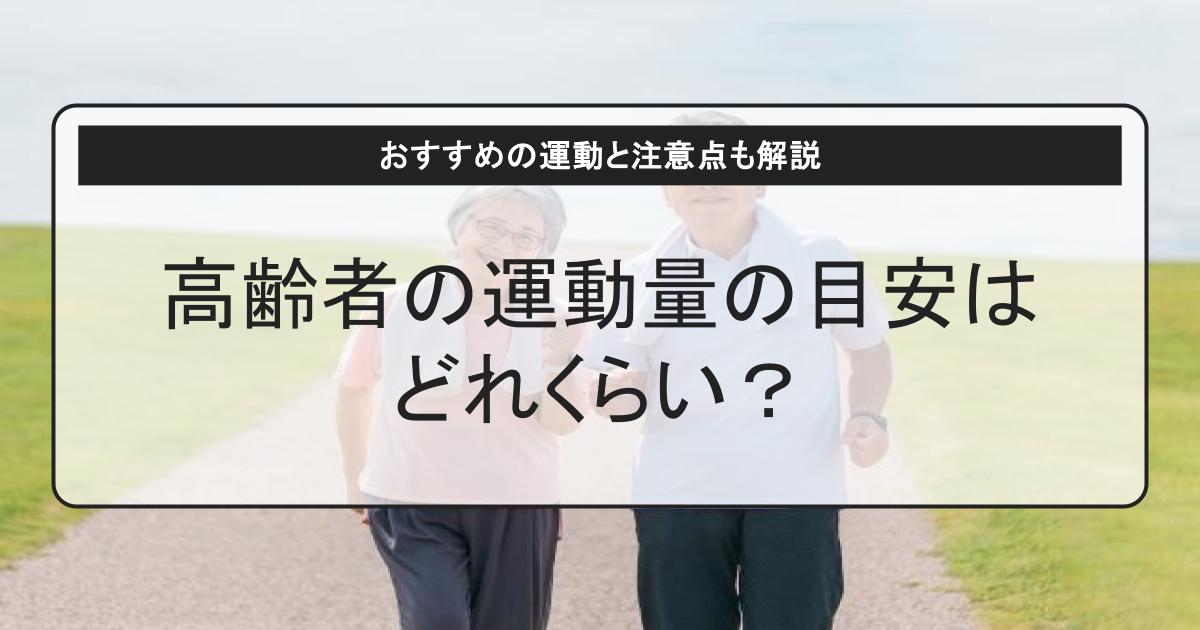
3.ストレスを減らして心の健康を保つ
ストレスを減らして心の健康を保つことも、認知機能を維持させる習慣としてとても大切なことです。
高齢者にとって慢性的なストレスは、心身ともに悪影響を及ぼすことが知られています。
ストレスが溜まると脳の記憶を司る「海馬」の働きが低下し、ボケの進行を早める一因となる可能性も指摘されているのです。
趣味に没頭する・自然に触れる・家族や友人と交流するなど、リラックスできる時間を大切にしましょう。
自分に合ったリラックス方法で、無理なく継続することが心身の安定につながります。
4.社会参加で脳を活性化させる
地域のボランティア活動やサークルへの参加は、高齢者の脳へ刺激となってボケ防止に役立ちます。
社会とのつながりや人間関係を築けば、孤独感を防いで心の健康にも良い影響を与えるでしょう。
また地域のコミュニティ活動や趣味のサークルへの参加は、記憶力・判断力のトレーニングにもつながります。
まずは小さな交流からでも、積極的に機会を作ることが大切です。
以下の記事では、高齢者でも参加しやすい社会活動について紹介しています。
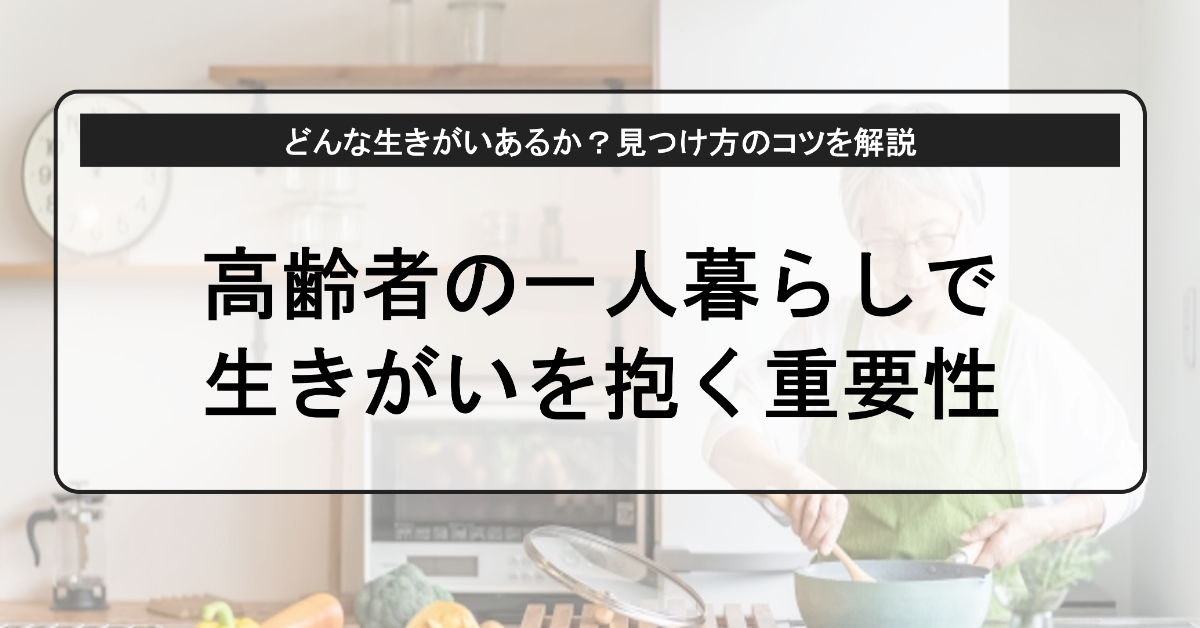
日常生活でできる高齢者のボケ防止の工夫
高齢者が日常生活で簡単にできる、ボケ防止策について解説します。
何気ない日常の中で、脳を活性化させたり、刺激を与えたりするように心がけてみましょう。
デュアルタスクで脳を活性化させる
デュアルタスクとは、2つ以上の作業を同時に行うことで脳を活性化させる方法です。
高齢者におすすめの日常生活で簡単にできるデュアルタスクには、以下があります。
- 散歩しながらしりとりをする
- 買い物しながら献立を考える
- 料理をしながら歌を歌う
同じタイミングの作業で脳が複数の機能を使い、認知機能のトレーニングになるのです。
新しい趣味を始めて脳を刺激する
新しい趣味を始めることは、高齢者のボケ防止に効果的です。
例えば、以下の手の指先を活用する趣味は、特に脳への刺激になります。
- 手芸
- 塗り絵
- 楽器演奏
- 囲碁、将棋
何歳からでも始めることが、脳の若々しさを保つポイントです。
一つに限らず自分に合った趣味を見つけて、生活に生きがいを見つけましょう。
高齢者におすすめの趣味は、以下の記事で詳しく紹介しているのであわせて読んでみてください。
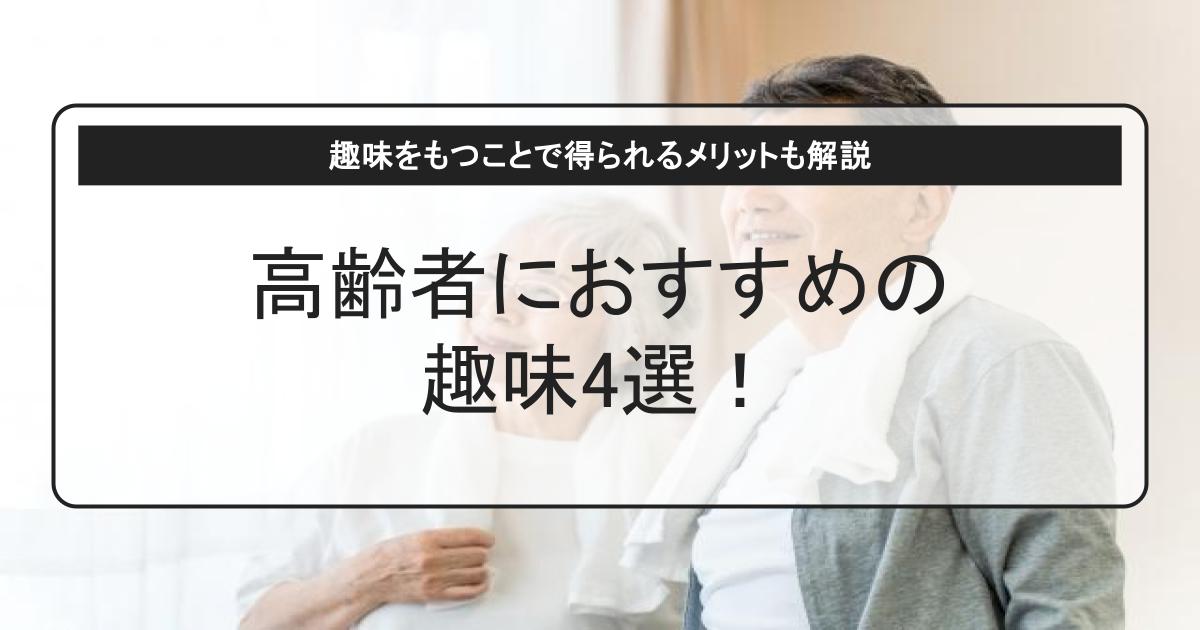
【年代別】認知症予防策
ここでは認知症を予防する方法について、年代別で解説します。
認知症の心配がまだない方も、あらかじめ理解し少し、意識するだけで向き合い方が変わるでしょう。
20代〜30代の心がけ
20代〜30代は、若いうちから生活習慣を整えることが、将来のボケ防止に大きく関わります。
生活の中で特に以下の3つを意識して、脳に良い生活を習慣化しておくことが重要です。
- 適度な運動
- バランスの取れた食事
- ストレス管理
早くから認知症の知識を身につけ行動しておくと、将来の発症リスク低下につながります。
40代〜50代の対策
40代〜50代は、生活習慣病のリスクも高まるため、より認知症に対して具体的な対策が必要になります。
定期的に健康診断や歯科検診を受け、血圧・血糖値をはじめとする体内のコントロールを行いましょう。
なぜ口腔ケアが認知症予防に関連するかは、以下の記事を参考にしてください。
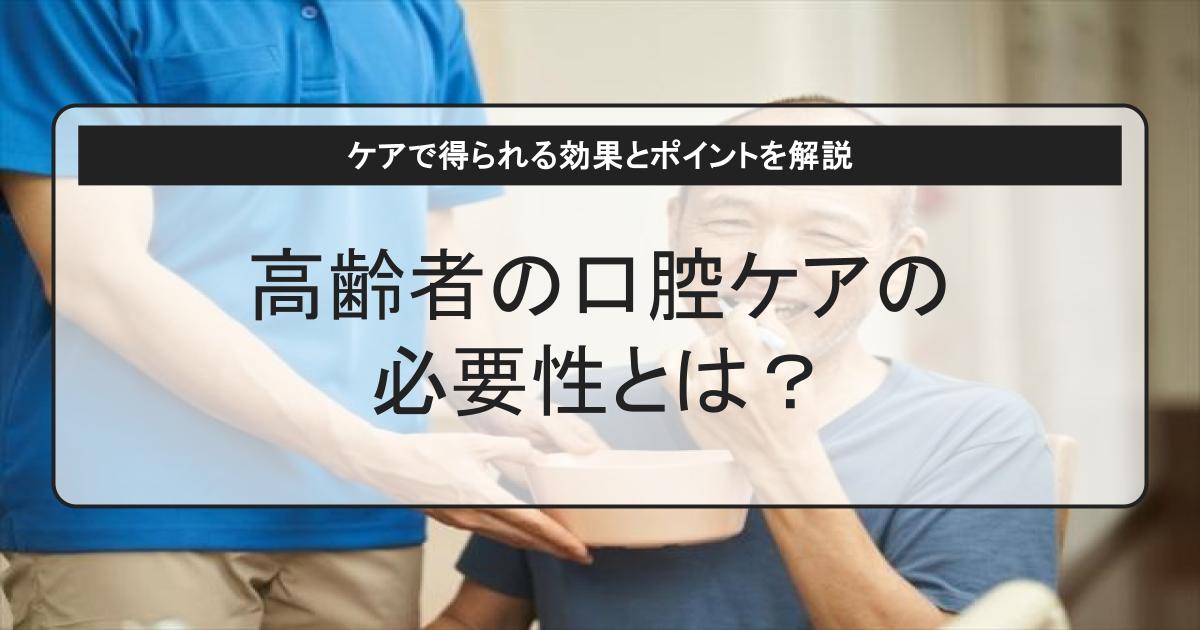
60代以降の具体的行動
60代以降は、より実践的な認知症予防が求められます。
認知機能のセルフチェックも取り入れ、異変を早期発見することがポイントです。
また、脳トレーニングやゲーム、新しい知識の吸収にも積極的に取り組み、脳に刺激を与え続け認知症を予防しましょう。
高齢者におすすめの脳トレは、以下で詳しく解説しているので、ぜひ取り組んでみてください。
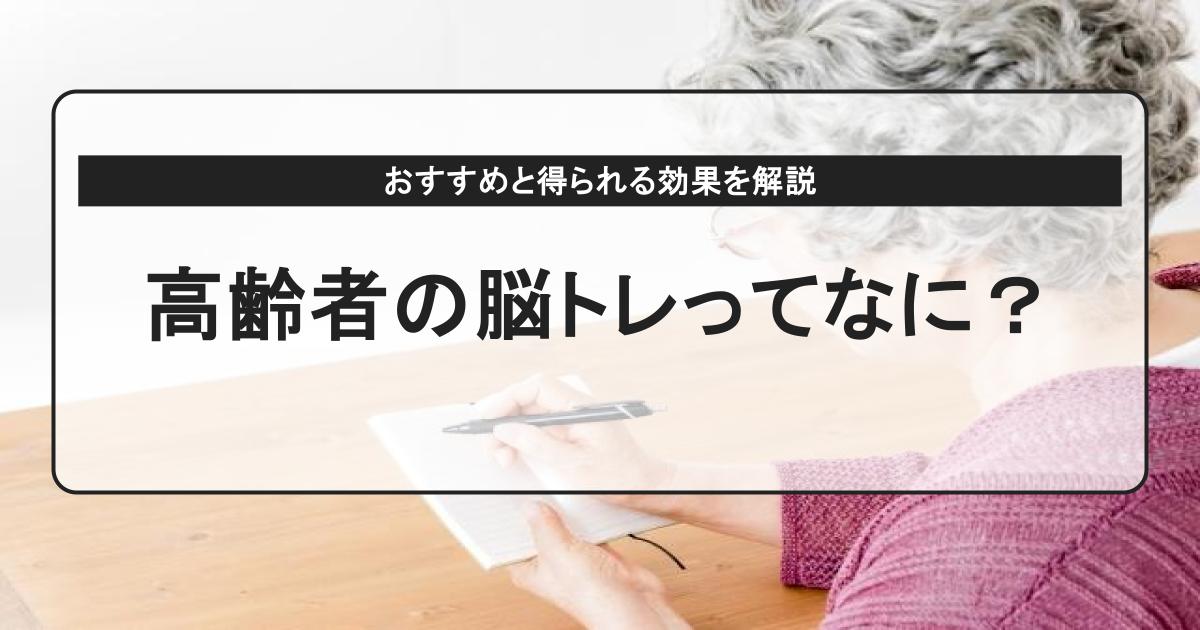
一生元気に過ごすために!自分に合ったボケ防止法を続けよう
高齢者のボケ防止には、特別な治療法があるわけではなく、日々の生活の積み重ねが大切です。
無理なく楽しく続けられる方法を見つけ、自身に合った習慣を選んでください。
特に以下を意識することで、高齢になっても元気に笑顔で毎日を過ごせる可能性が高まります。
- バランスの良い食事
- 適度な運動
- ストレスの少ない生活
- 社会参加
今すぐできることから生活に取り入れ、少しずつ習慣化させましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









