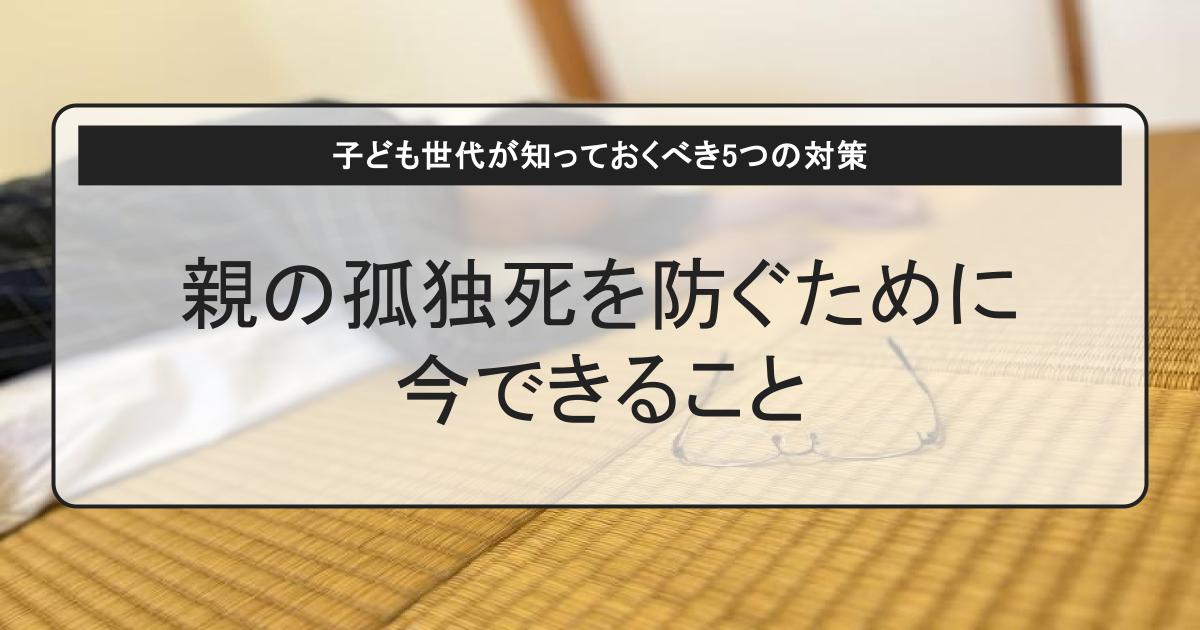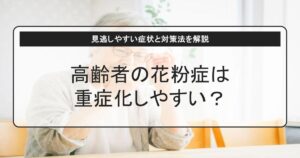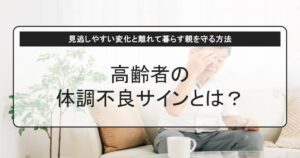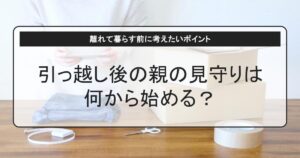「親が一人暮らしだから孤独死のことを考えると心配…」
上記のようにお悩みではありませんか?
孤独死=高齢者の問題と思われがちですが、実は同居世帯でも起こりうる可能性があり、誰にとっても無関係ではない現実です。
この記事では、孤独死の定義やデータから、家族ができる5つの対策、そして「見守る関わり方」のヒントまでを詳しく解説します。
大切な人の安心を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら孤独死とは
「孤独死」とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなり、一定期間発見されない死を指します。
明確な医学的定義はありませんが、行政や福祉現場では、社会的孤立や家族とのつながりの希薄さが背景にあるケースを含めて使われることが多くなっているのです。
東京都監察医務院の調査によると、都内23区内で一人暮らしの人が自宅で亡くなったケースは年間5,000件を超えており、その多くが「孤独死」に該当します。
特に注目すべきは、70代から急激に件数が増え始めるという点です。
仕事をリタイアした後の年代は、社会との接点が減る一方で家族とも距離ができやすく、孤独を感じやすい時期と重なります。
また、厚生労働省の資料などでも「高齢者の孤独死は今後さらに増加が見込まれる」と警鐘が鳴らされており、これは都市部に限らず、地方でも同様の傾向があります。
孤独死は高齢者特有の問題だけでなく、人生の後半に入った誰もが向き合い得るリスクであり、子ども世代が他人事とせず向き合うべきテーマといえるでしょう。
孤独死の「誰にも看取られない」という現実
孤独死が深刻なのは、その死に際して誰にも気づかれず、長い時間放置されてしまうという現実です。
亡くなったのが数日から数週間、あるいはそれ以上にわたって発見されないケースも少なくありません。
きっかけは、以下の状況などで発見されることが多いです。
- 連絡が取れない
- 郵便物がたまっている
- 異臭がする
つまり、本人の死を日常的に気にかける人がいなければ、発見すらされない可能性があります。
さらに、誰にも看取られないまま亡くなることは、本人にとっても、残された家族にとっても非常につらく、精神的な負担や後悔を生む原因となります。
「最期は家族に看取られたい」と願っていても、日常のつながりが薄れていれば、その願いは叶わないのです。
孤独死は一人暮らしに限らず同居でも起こりうる
「孤独死は一人暮らしの高齢者に限った話」と思われがちですが、実は同居していても孤独死のような状況が起こることがあります。
たとえば、家族と同じ家に住んでいても、日常的に顔を合わせる機会が少なく、会話がほとんどない家庭も珍しくありません。
「高齢の親が2階の一室にこもりきりで、体調の変化や異変に家族が気づかず、数日後に発見される」ようなケースも現実に起きています。
また夫婦だけの世帯や、高齢のきょうだいで暮らしている場合、一方が突然倒れたあと、もう一方も助けを呼べずに亡くなる「ダブル孤独死」のような事例もあります。
形式的には同居していても、実質的には孤立状態にあることが背景にあると言えるでしょう。
つまり、誰かと一緒に住んでいるからといって安心とは限らず、「日々の関わりの密度」が孤独死のリスクを左右すると言っても過言ではありません。
家族ができる5つの孤独死対策
孤独死を防ぐうえで最も重要なのは、本人が「誰かに見守られている」「気にかけられている」と感じられる環境をつくることです。
高齢の親が一人でも安心して暮らせるようにするためには、日常的なつながりやちょっとした気づかいの積み重ねが、何よりの予防策になります。
ここからは、家族として無理なく取り入れられる5つの孤独死対策をご紹介します。
1.定期的なコミュニケーション
孤独死を防ぐには、日々のコミュニケーションが何よりの予防策です。
短い電話やLINEでも、高齢者は「気にかけてもらっている」と感じることで、安心感や心の安定につながります。
特別な話題がなくても、「元気?」「今日はどうだった?」といった一言のやり取りを続けることが大切です。
日常的な連絡があれば、体調や気分の変化にも早く気づけます。
「用事があるときだけ連絡する」から、「何もなくても声をかける」関係を心がけましょう。
小さなつながりが、大きな安心を生み出します。
以下の記事では、孤独感を感じる高齢者とのコミュニケーションについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
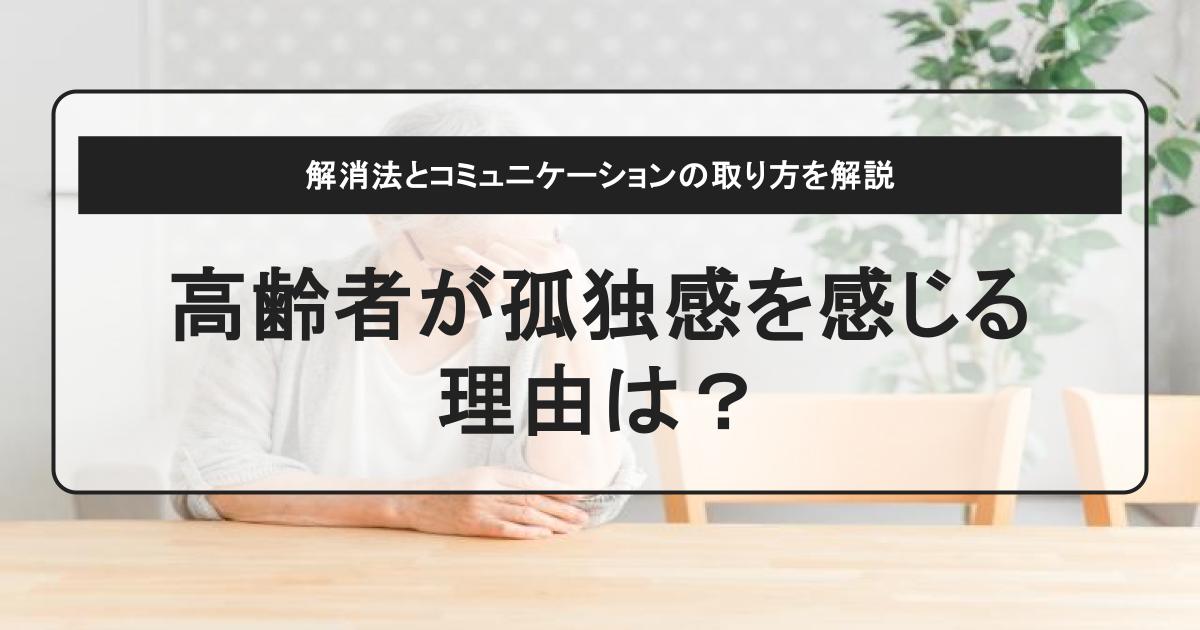
2.見守りサービスの導入
離れて暮らす親の様子が気になるとき、見守りサービスは有効な手段です。
センサー型(人感・ドア開閉)、カメラ型、家電と連動するタイプなど、ニーズに応じた選択が可能です。
例えば、冷蔵庫の開閉やテレビの使用状況から生活の動きを把握できるサービスもあり、異変があればすぐ通知される仕組みも整っています。
直接の連絡が難しいときも、「見えない安心」を支えるツールとして活用できます。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら以下の記事では、見守りサービスの選び方を詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
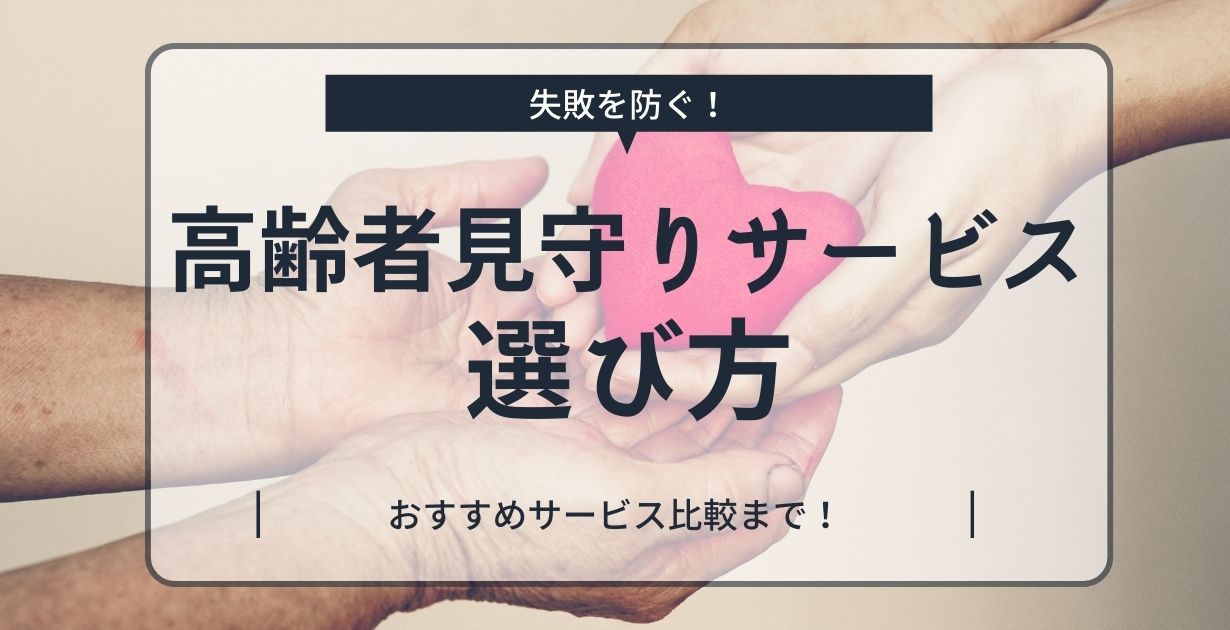
3.地域活動やデイサービスへの参加の後押し
地域活動やデイサービスへの参加の後押しも、高齢者の孤独死を防ぐ対策法の一つです。
人とのつながりを持ち続けることは、孤独死を防ぐ大きな力になります。
地域のサロンや体操教室、デイサービスなどに参加することで、外出の機会や会話が増え、心の刺激にもつながります。
最初の一歩を踏み出すのが不安な人も多いため、家族の「一緒に行ってみようか」「こんな場所があるよ」という声かけが大切です。
顔なじみがいる環境をつくることが、孤立を遠ざける第一歩になるでしょう。
4.話し相手の確保
話し相手を確保しておくことも、高齢者の孤独死を防ぐ効果が期待できます。
誰かとちょっと話すだけでも、心はずいぶん軽くなります。
定期的に訪れる介護スタッフ・近所の人・親戚など、気軽に会話できる相手がいると、孤立を防げるかもしれません。
一人の時間が長いほど不安や塞ぎこみは強くなりやすいため、「ちょっと話せる誰か」が身近にいるだけでも安心感が生まれます。
家族がつなぎ役となって、話し相手の輪を広げておくことが、見えない支えになります。
5.「何でも話せる関係」を構築
高齢者の孤独死を防ぐうえで、「何でも話せる関係」を構築しておくことも大切です。
表面的な会話だけでなく、「ちょっとした不安や本音も話せる関係」があると、孤独感はぐっと減ります。
「こんなこと言ったら迷惑かな」とため込まずに済む関係性が、心の安心につながるでしょう。
そのためには、日頃から相手の気持ちに耳を傾け、否定せず受け止めることが大切です。
「話しても大丈夫」と思える空気をつくることが、見えない孤立を防ぐカギになります。
孤独死を防ぐうえで親の「ひとり時間」をゼロにする必要はない
「孤独=ひとりの時間」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
一人で過ごす時間そのものが悪いのではなく、「誰ともつながっていない」と感じる状態が、孤立や不安を深めてしまうのです。
ここからは一人時間を大切にしつつも、安心感を持ってもらうための関わり方について見ていきましょう。
過干渉ではなく「見守る」スタンスが大切
孤独死を防ぐうえで、過干渉ではなく「親を見守る」スタンスを意識しましょう。
「親のことが心配で、つい口出しや介入が増えてしまう」といった関わり方は、かえって本人の自尊心を傷つけてしまうこともあります。
大切なのは、何かあったときにすぐ気づける距離感を保ちながらも、普段はそっと見守る姿勢です。
「困ったときは頼っていい」と伝えつつ、自主性を尊重することで、親も安心して自分らしく過ごせます。
プライドや自立心を尊重しながら支える方法
高齢の親にとって、「誰かに頼る」ことは、思っている以上に勇気がいるものです。
だからこそ、手を差し伸べるときは、「助ける」ではなく「一緒にやろうという姿勢」が大切です。
家事や手続きなども「手伝おうか?」ではなく「一緒にやってみようか?」と声をかけることで、相手の自立心を尊重できます。
さりげない気づかいと対等な関わりが、信頼と安心感につながっていきます。
「支援されている」のではなく「つながっている」と感じてもらう工夫
「支えてあげている」という姿勢は、知らず知らずのうちに上下の関係を生んでしまうことがあります。
大切なのは、親に対して一方的な支援ではなく、自然なつながりとして関わることです。
たとえば、こちらから近況を話したり、ちょっとした相談をしてみたりすると良いでしょう。
「お互いさま」のやり取りがあることで、親も「まだ自分は役に立てている」と感じられ、前向きな気持ちにつながります。
孤独死を防ぐのには日々の気づかいが大切
孤独死は高齢者だけの問題だけでなく、誰にでも起こりうる現実です。
一人暮らしに限らず、同居でも「実質的な孤立」があればそのリスクは存在します。
大切なのは、日常的なコミュニケーションや見守り体制の整備、地域とのつながりを通じて「ひとりではない」と感じられる環境をつくることです。
親の自立やプライドを尊重しつつ、支援ではなくつながりとして関わることで、孤独死を防ぐ家族の役割が見えてきます。
大切な人の「もしも」を防ぐために、今できることから始めてみましょう。
完璧なケアや特別なことではなく、日々のちょっとした声かけや気づかいが、大きな安心へとつながります。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら