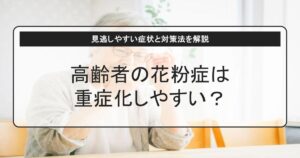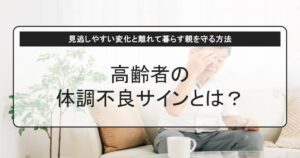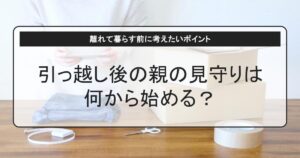「高齢者の歩きすぎは身体に良くない?」
「歩きすぎって何歩から?」
上記のように、高齢者の歩きすぎについて気になっている方も多いでしょう。
歩きすぎの基準は明確に定まっていませんが、歩きすぎると関節に負担がかかったり、免疫力が低下したりする恐れがあります。
本記事では、高齢者の歩きすぎについて詳しく解説していきます。
高齢者が安全で効果的なウォーキングを行うためのポイントも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の歩きすぎは何歩から?
「高齢者の歩きすぎは何歩から?」という疑問を持っている方も多いでしょう。
歩きすぎの基準についてはエビデンスがなく、「高齢者の歩きすぎは10,000歩から」のように明確に決まっているわけではありません。
高齢者の身体機能や患っている病気などによって、適切な運動強度が異なるからです。
しかし、「1日に何歩以上歩くのが健康に良いか」は分かっています。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド」によると、1日に40分以上かつ6,000歩以上歩くことが推奨されています。
また、推奨される運動量をこなせない高齢者の方でも、日常生活に少しずつ運動を取り入れるのがおすすめです。
少しでも運動をした方が健康に良いと証明されているため、ひきこもりがちな高齢者も積極的に運動をしていきましょう。
毎日のちょっとした積み重ねが重要です。
高齢者のひきこもりや外出しないことによる問題点について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
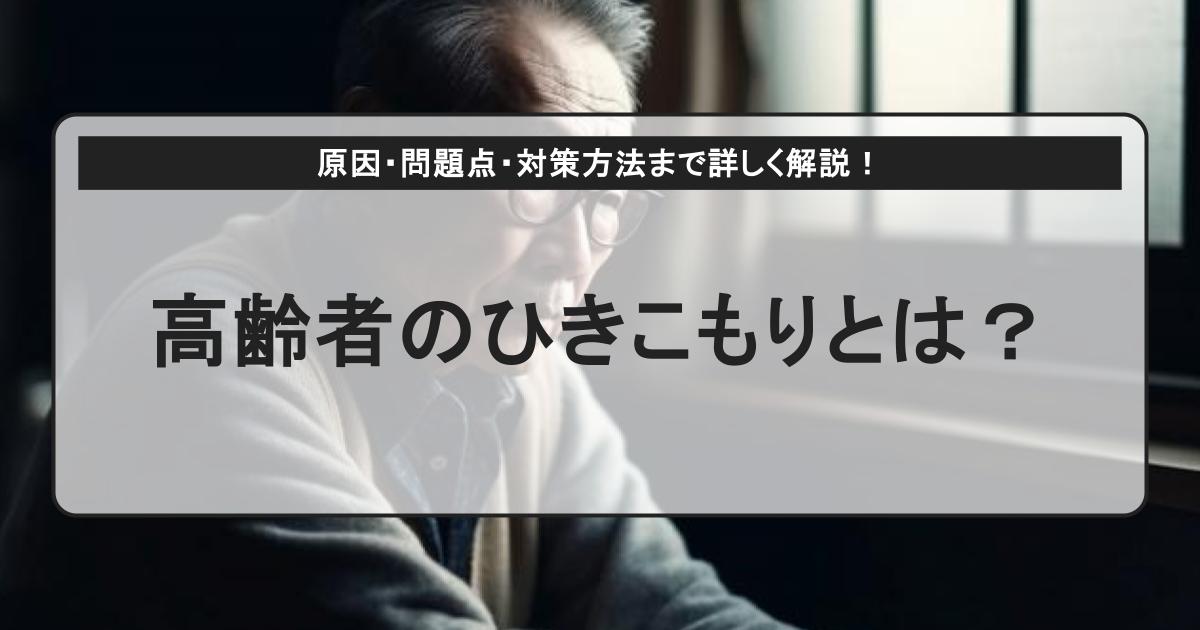
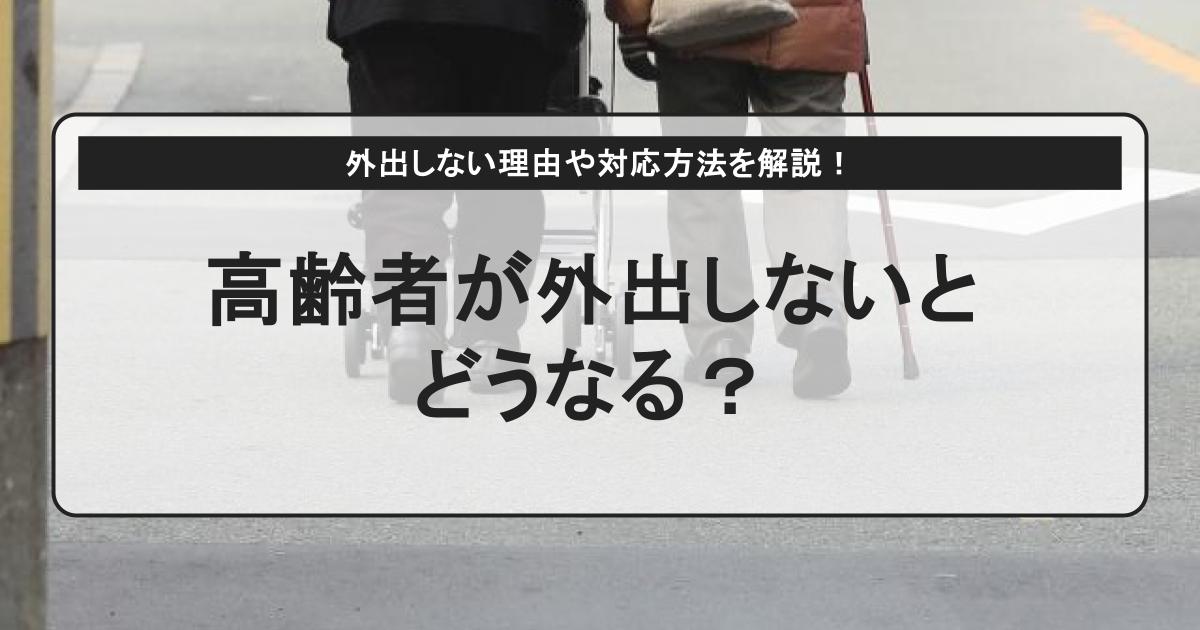
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスク5選
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクとして、以下の5つが挙げられます。
- 膝や腰などの関節の負担
- 筋肉や腱の炎症
- 脱水症状や熱中症
- 疲労による免疫力低下
- 転倒や骨折リスク
それぞれの健康リスクについて詳しく解説していくので、高齢者の歩きすぎに不安を感じている方は参考にしてください。
①膝や腰などの関節の負担
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクの1つ目は、膝や腰などの関節の負担です。
加齢に伴って、軟骨がすり減ったり筋力が低下したりするため、関節のクッションが正常に機能しません。
その中でも特に膝の関節は、体重の3~5倍の負荷がかかると言われています。
そのため、長距離のウォーキングや坂道・硬い地面での歩行が続くと、関節の負担がかなり大きくなってしまいます。
歩きすぎることで関節に大きな負担がかかると、痛みや炎症を引き起こすだけではなく、変形性関節症などにつながるリスクも否定できません。
また、炎症や痛みなどで関節が動きづらくなったまま歩き続けていると、他の部位に影響が出る場合もあります。
例えば、炎症や痛みで膝の関節が動かしづらいからといって、膝をかばった状態で歩き続けていると、腰などに負担が増えるケースもあります。
②筋肉や腱の炎症
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクの2つ目は、筋肉や腱の炎症です。
高齢者は、筋肉の量が減少するだけではなく、柔軟性も低下しているケースが多いです。
そのため、若い方よりも筋肉や腱にストレスがかかりやすい状態になっています。
特に、以下のような部位は、歩きすぎによって負担が大きく増加します。
- 太もも
- ふくらはぎ
- アキレス腱
何度も負荷がかかると、炎症や痛みが増加して歩行障害につながる恐れもあります。
炎症が慢性化すると、腱鞘炎(けんしょうえん)・筋膜炎・肉離れなどに発展する可能性も否定できません。
適度なウォーキングは健康に良いですが、炎症や痛みを感じた場合は休むことも検討してみましょう。
③脱水症状や熱中症
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクの3つ目は、脱水症状や熱中症が挙げられます。
加齢によって体内にある水分量が減るだけではなく、喉の乾きを感じづらくなります。
そのため、高齢者は、歩きすぎによって汗をかくと脱水症状や熱中症になりやすいです。
また、高齢者は体温の調整をうまくできないため、暑さを感じづらくなり、気付かないうちに熱中症になる可能性もあります。
ふらつき・頭痛・吐き気などの症状から始まり、重症化すると意識障害や熱射病になって命に関わる事態に発展するケースも否定できません。
帽子や日傘を使用したり、通気性の良い服を着たりするなど、脱水症状や熱中症に注意する必要があります。
暑い日はウォーキングの量を減らすなどして、歩きすぎに気を付けましょう。
高齢者が水分を取らない理由について解説した以下の記事も参考にしてください。
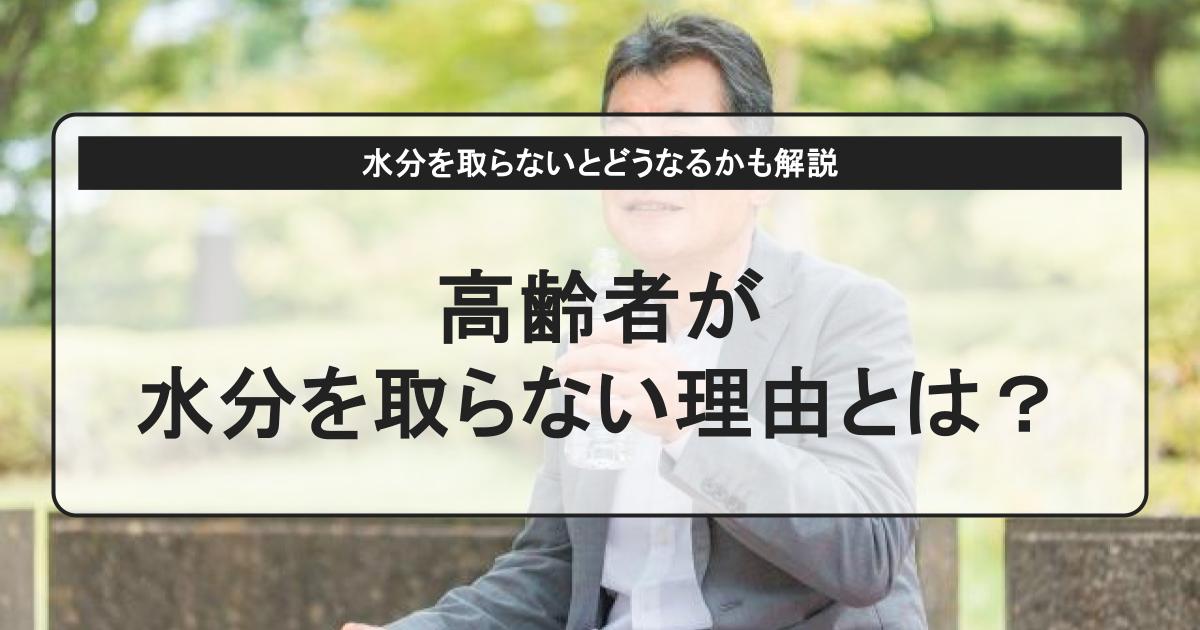
④疲労による免疫力低下
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクの4つ目は、疲労による免疫低下です。
適度なウォーキングであれば免疫力を高める効果が期待できますが、疲労が蓄積したまま歩き続けると免疫力が低下します。
疲労が溜まったままの場合、体内で炎症物質やストレスホルモンが増加して、免疫細胞の働きが低下すると言われています。
免疫力の低下は、風邪や感染症リスクが増えるだけではなく、傷の治りが遅くなったり疲労感が続いたりするなどの不調につながりやすいです。
特に高齢者の場合は回復力が低いため、免疫力を維持するのは重要です。
⑤転倒や骨折リスク
高齢者の歩きすぎで起こる健康リスクの5つ目は、転倒や骨折リスクが増えることです。
歩きすぎで疲労が蓄積すると、足を高く上げられなくなったり、バランスを崩しやすくなったりします。
特に高齢者の場合は、筋力や反射能力が低下しているため、若い方よりも転倒や骨折のリスクが高まります。
小さな段差・ぬれた路面・暗い場所などでは転倒しやすく、大きなけがにつながるケースも少なくありません。
また、骨粗しょう症の高齢者の場合は、軽い転倒でも大腿骨・背骨・手首などを骨折するリスクが高いです。
寝たきりの状態になる恐れもあるため、転倒や骨折の可能性が高まる歩きすぎには注意が必要です。
高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法
高齢者の歩きすぎによるリスクを抑えるためにも、安全で効果的なウォーキング方法を知っておくのが重要です。
ここからは、高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法として、以下の4つを紹介していきます。
- 中強度を目安にする
- 準備運動を行う
- 正しいフォームを意識する
- 水分・栄養・休養の3要素を重視する
厚生労働省の「身体活動・運動を安全に行うためのポイント」も参考にしながら、分かりやすく解説していきます。
歩きすぎを抑えて、安全で効果的なウォーキングをしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
①中強度を目安にする
高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法の1つ目は、中強度を目安にすることです。
ただ毎日たくさん歩けば良いというわけではなく、歩く際の運動強度も意識しておくのが大切です。
実際に、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド」でも、中強度の運動が推奨されています。
具体的なウォーキングの強度として、「会話はできるが歌うのは難しい程度」「息が少し上がるくらいの歩行速度」と表現されています。
また、心拍数は最大心拍数の50~60%程度がおすすめです。
歩数ばかりを気にしていると、歩きすぎる可能性が高いため、ウォーキングのスピードや強度などを意識してみましょう。
②準備運動を行う
高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法の2つ目は、準備運動を行うことです。
加齢によって筋肉・腱・関節などの柔軟性が低下しているため、急に動くことで痛みや炎症につながる恐れがあります。
高齢者が歩きすぎで身体を壊さないためにも、下半身を中心に軽いストレッチや体操を行いましょう。
関節の可動域が広がれば、歩きすぎによる怪我も防げます。
特に冬の寒い時期や朝の運動では、筋肉が凝り固まっている場合も多いため、最低でも5分程度のウォームアップを取り入れるのがおすすめです。
また、準備運動をせずにいきなり早歩きをすると、関節だけではなく心臓にも負担がかかります。
高齢者が早歩きをする場合は、少しずつ歩くスピードを上げていくように心がけましょう。
③正しいフォームを意識する
高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法の3つ目は、正しいフォームを意識することです。
正しいフォームで歩けば、膝や腰への負担が軽減できるだけではなく、転倒リスクも軽減できます。
具体的には、以下のようなポイントを意識するのがおすすめです。
- 背筋を伸ばす
- 目線はやや遠くを見る
- 腕を自然に前後に振る
- かかとから着地する
- 足裏全体を使って蹴り出すように歩く
また、歩幅を広げ過ぎないのも重要です。無理に歩幅を広げようとすると、関節を痛める原因になります。
疲労で「フォームが崩れてきたな」と感じた場合は、歩きすぎのサインにもなるため、日ごろからフォームを意識して歩くのがおすすめです。
④水分・栄養・休養の3要素を重視する
高齢者のための安全で効果的なウォーキング方法の4つ目は、水分・栄養・休養の3要素を重視することです。
高齢者は喉の乾きを感じづらくなっているため、喉の乾きを感じていない場合でも、意識して早めに水分を摂取するのがおすすめです。
冬や夏などの季節に関わらず、運動前・運動中・運動後に積極的な水分補給を心がけましょう。
また、栄養面では、筋肉の修復に重要なタンパク質や、エネルギー源となる炭水化物の摂取も大切です。
さらに、筋肉・関節・免疫力などを回復させるために、適度に休養日を設けることも意識してください。
「3日に1回はウォーキングを休む」「雨の日は歩かない」など、明確なルールを設けておけば、歩きすぎを抑えられるだけではなく、適度な運動習慣を構築できます。
高齢者の歩きすぎに関するよくある質問
高齢者が歩きすぎることに不安を抱いている方の中には、以下のような疑問を持っている方も多いでしょう。
- 高齢者の歩きすぎで筋肉は落ちる?
- 高齢者の歩きすぎで病気になる?
- 高齢者の歩きすぎで太る?
ここからは、それぞれの質問に回答していきます。
高齢者の歩きすぎで筋肉は落ちる?
高齢者の歩きすぎで筋肉が落ちるという意見がありますが、明確な根拠はありません。
しかし、高齢者の筋肉は運動後の回復が遅いため、運動をしてから回復するまでの時間が少ないと、筋肉が十分に合成されない可能性があります。
筋肉の合成が間に合わない場合は、歩きすぎで筋肉が落ちる可能性があるでしょう。
タンパク質を摂取したり、休養をしっかり取ったりすれば、歩きすぎで筋肉が落ちることを防げます。
高齢者の歩きすぎで病気になる?
歩くのは健康に良いとされていますが、高齢者が歩きすぎると病気になるリスクは高まります。
例えば、歩きすぎで関節に大きな負担がかかると、変形性膝関節症になる可能性があるのです。
また、高齢者の歩きすぎで免疫力が低下すると、細菌やウイルスなどに感染しやすくなるため、病気になるリスクが上昇します。
歩きすぎは健康に良くないため、適度な運動量を意識するのが大切です。
高齢者の歩きすぎで太る?
高齢者の歩きすぎで太るという意見がありますが、「運動したら痩せるはずでは?」と疑問を抱いている方も多いでしょう。
高齢者が歩きすぎることで太る可能性は十分にあります。
歩きすぎで太る理由は、以下の通りです。
- 歩きすぎで食欲が増えて過食になる
- 歩きすぎによる疲労で活動量が減る
- 歩きすぎで筋肉が落ちて基礎代謝が下がる
歩いて消費するカロリーよりも、摂取するカロリーの方が多くなれば、体重が増えていきます。
また、歩きすぎることで、ウォーキングをしている時間以外の活動量が減る場合も考えられます。
ウォーキングのような有酸素運動では、脂肪燃焼効果が期待できますが、筋肉を維持する効果はあまり大きくありません。
そのため、基礎代謝量が減少して、太りやすい体質になる可能性もあります。
高齢者の歩きすぎに注意して健康に過ごそう! まとめ
本記事では、高齢者の歩きすぎについて詳しく解説しました。
高齢者の歩きすぎの基準は明確に決まっていませんが、歩きすぎると免疫力の低下や関節痛など、さまざまな問題に発展する恐れがあります。
高齢者の健康にとって適度に歩くことは良い効果を期待できますが、歩きすぎにはさまざまなリスクが伴うため、気を付けておく必要があります。
また、高齢者のウォーキングを安全で効果的なものにするためにも、記事内で紹介した方法を参考にしてください。
歩きすぎないように注意したうえで、適切な方法でウォーキングを続けることで健康的な生活を手に入れましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら