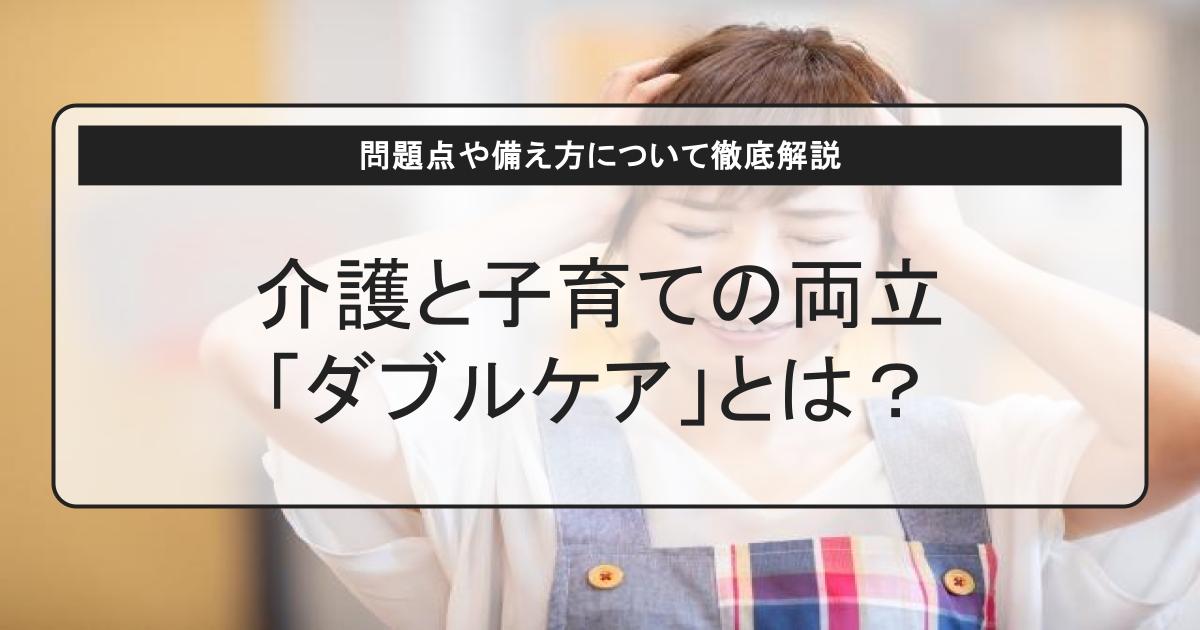育児と介護が同時期に重なる「ダブルケア」。
いまや全国で25万人以上が直面しており、特に女性に負担が偏りがちです。
身体的・精神的な疲労、孤立、子どもへの影響、経済的な不安など、さまざまな問題が潜んでいます。
この記事では、ダブルケアの現状や課題に加え、少しでも負担を減らすための備えや支援の活用法についてわかりやすく紹介します。
両立に悩む方や、将来に備えたい方はぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら介護と子育ての両立「ダブルケア」とは
介護と子育てが重なる「ダブルケア」は、近年注目されるようになった社会課題の1つです。
少子高齢化が進む中、同時に親の介護と子どもの養育を担う人が増えており、その負担は想像以上に大きなものとなっています。
まずは、ダブルケアの現状と背景について見ていきましょう。
ダブルケアに陥っている人は25万人以上
総務省の就業構造基本調査によると、育児と介護を同時に担っている人は、およそ25万人と推定されています。
育児だけをしている人が約1,000万人、介護のみを行っている人が約557万人いることを考えると、ダブルケアをしている人の割合は少なく見えるかもしれません。
しかし、「ダブルケア」という言葉がまだ十分に社会に浸透していないことから、実際には統計に表れていないケースも多い可能性があります。
女性に負担がかかりやすい傾向にある
ダブルケアは、女性に負担がかかりやすい傾向にあります。
ダブルケアを担う約25万人のうち、女性はおよそ17万人、男性は約8万人とされており、女性の人数は男性の約2倍に上ります。
さらに、育児と介護の両方を主に担当している割合を見ても、女性は約50%に対し、男性はおよそ30%にとどまっており、女性への負担の偏りがうかがえます。
加えて、介護の頻度に関しても、週4回以上対応している人の割合は女性が37.4%、男性が29.4%と、女性の方がより多くの介護を日常的に担っているのです。
近年は育児に積極的な男性も増えてきましたが、依然として子育ては女性が中心となる傾向が強く、結果としてダブルケアにおける負担も女性に偏りがちであるといえるでしょう。
ダブルケアの問題点
ダブルケアは一見すると限られた人だけの問題に思えるかもしれませんが、実際には多くの負担や悩みを抱える深刻な状況です。
日々の生活の中で育児と介護の両立に追われることによって、心身ともに大きな影響が及ぶケースも少なくありません。
ここからは、ダブルケアによって生じやすい主な問題点について、詳しく見ていきましょう。
肉体的・精神的な負担
ダブルケアの問題点の1つ目が、肉体的・精神的な負担です。
ダブルケアに取り組む中で睡眠が十分に取れず、慢性的な疲れに悩まされることも少なくありません。
育児と介護の両方を担う立場になると、不安や気がかりも増え、精神的なストレスも大きくなっていきます。
すべてを自分ひとりで抱え込んでしまうと、「育児うつ」や「介護うつ」などのリスクが高まり、心身ともに追い詰められてしまう可能性もあります。
体調を崩してしまえば、子育ても介護も思うように続けることができなくなってしまうでしょう。
孤立
孤立もダブルケアの問題点の1つです。
現状では、ダブルケアに関する社会的な認知はまだ十分とはいえず、行政による支援体制や制度面での整備も不十分なままです。そのため、必要なサポートを受けづらいというのが実情になっています。
育児と介護の両方を担う人たちは、明確な解決策を見出せないまま、日々休む間もなく対応し続けているのが現状です。
育児の悩みは身近な友人やママ友に話せても、介護に関する話題は共有しにくい傾向にあります。
さらに育児と介護では担当する行政機関が異なるため、相談や手続きに手間や時間がかかることも、負担を感じる一因となっています。
こうした状況のなかで悩みを打ち明けられる相手が少ない場合、孤独感が強まりやすくなるでしょう。
子どもへの心身のストレス
介護の期間が長くなると、子どもへの対応が後回しになってしまうこともあり、日常的な関わりや愛情表現が不足しがちになります。
介護に多くのエネルギーを費やすことで、子どもに向けるべき気持ちや時間がどうしても限られてしまうのです。
ダブルケアに取り組む際には、当事者自身の負担だけでなく、家族の一員である子どもへの影響にも目を向ける必要があります。
子どもは親の変化や感情にとても敏感なため、愛情不足や親の疲れを感じ取り、心や体にストレスを抱えてしまう可能性があります。
行政からのサポートの受けにくさ
ダブルケアという言葉が広まったのは2012年と比較的新しく、社会全体での認知度はまだ十分とはいえません。
そのため行政の相談窓口が複数に分かれていることもあり、必要な支援を受けるまでに時間や手間がかかる場合があります。
介護と子育ての両立「ダブルケア」への備え
育児と介護を同時に担うダブルケアは、心身だけでなく経済面でも大きな負担となります。
負担を軽減し、無理なく両立していくためには、日頃からの準備や家族・周囲の協力が欠かせません。
ここでは、ダブルケアに備えるための具体的な対策や支援の活用法についてご紹介します。
介護で家計にかかる負担が大きくなる前に準備する
ダブルケアへの備えとして、介護で家計に負担が大きくなる前に準備しておくことは、とても大切です。
子育ては開始時期がある程度予測できるため、働き方を調整したり、費用面でも比較的計画を立てやすいと言えます。
例えば、預貯金を準備したり、学資保険を活用するケースも多いです。
一方で親の介護については、元気なうちは実感しづらく、準備が後回しになりがちです。
介護による経済的な負担が大きくなる前に備えるためには、早い段階から介護資金として貯蓄を始めましょう。
また、介護に関わる費用は当事者だけでなく、家族や親族間で分担することも現実的な方法のひとつです。
2000年に施行された介護保険法により、高齢者の介護を社会全体で支える公的な介護保険制度が整備されています。
身内同士で助け合いながら介護の責任を分け合う
身内同士で助け合いながら、介護の責任を分け合うことも、ダブルケアにおいて大切です。
協力してくれる家族や親族がいる場合は、すべてを自分一人で抱え込まず、経済的な余裕や状況に応じて負担を分け合うことが重要です。
一人ですべてを背負うと、どこかで無理が生じてしまうため、近くにいる家族や親族に可能な範囲でサポートをお願いしましょう。
また、遠方に住む家族や親族でも、費用の一部を負担してもらったり、帰省時に手伝ってもらうだけでも、ダブルケアに取り組む人の負担を軽減可能で、遠距離介護を行っているケースもあります。
家族や親族同士でしっかり話し合い、協力体制を築くことが大切です。
介護に役立つ制度や勤務先のサポート体制を確認しておく
ダブルケアを行う際に、介護に役立つ制度や勤務先のサポート体制を確認しておきましょう。
仕事を続けながら育児や介護をする人が、看護休暇や介護休暇を取りやすくするために、2021年に育児・介護休業法が改正されました。この法律により、すべての労働者が休暇を取得でき、1時間単位での利用も可能となっています。
育児・介護休業法の規定に該当すれば、子どもが1人の場合は年間5日まで、2人いる場合は年間10日までの看護休暇を取得できるようになりました。介護休暇についても同様の変更が行われています。
また、勤務先によっては独自の休暇制度を設けていることもあるため、育児や介護に関する休暇の有無を事前に確認しておくことが大切です。
訪問介護サービス・保育サービス・介護施設を利用する
訪問介護や保育サービス、介護施設の利用も、ダブルケアへの備えの1つです。
子育てと介護の両立を目指していても、体力的にも精神的にも限界を感じることがあります。そんなときは、介護施設や訪問介護、保育サービスをうまく活用することで、負担を和らげられるかもしれません。
特に介護サービスについては、利用できる条件が決まっている場合もあるため、事前に市区町村や地域包括支援センターなどで相談しておくと安心です。
以下の記事では、老人ホームの種類や費用も詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてください。
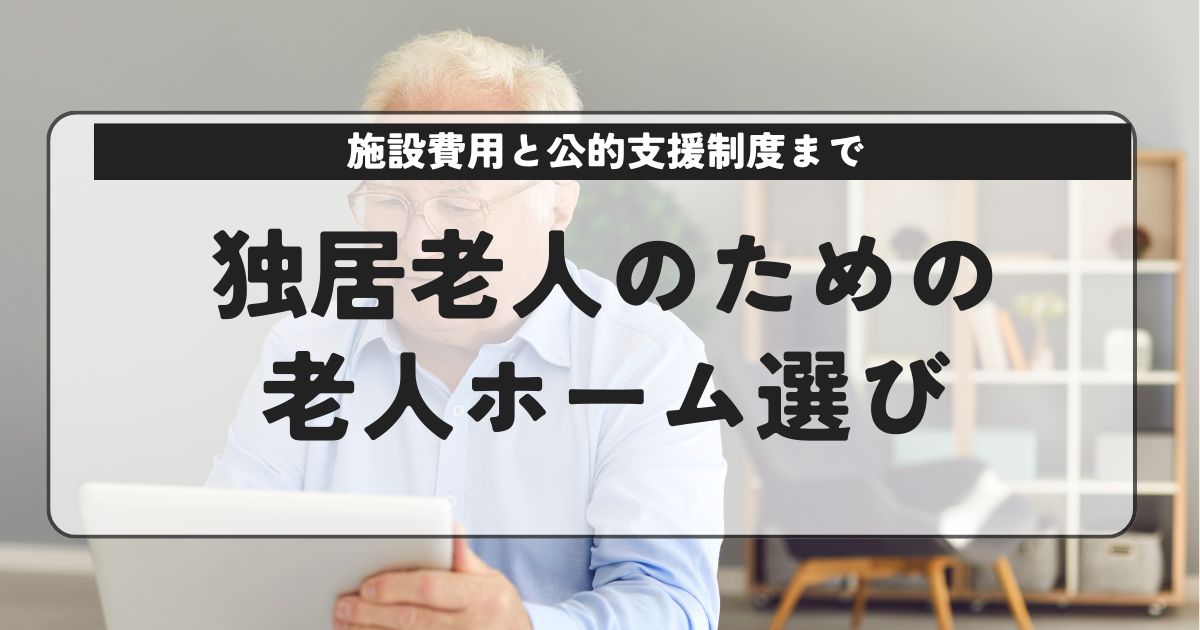
ダブルケアカフェに参加する
ダブルケアを担う方々が集まり悩みを共有できる場として、「ダブルケアカフェ」というコミュニティが各地で開催されています。ここでは、同じ立場の人同士が思いを語り合うことで、気持ちが軽くなったり、共感やつながりが生まれたりすることもあります。
身近に同じ境遇の人がいない場合でも、こうした場を利用することで孤独感が和らぐ可能性があります。
また、自治体によっては、ダブルケアへの支援としてサポーターの派遣や、専門のコーディネーターによる相談対応を行っているところもあります。
お住まいの市区町村でどのような支援があるのか、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
まとめ
ダブルケアは、子育てと介護を同時に担うことで心身に大きな負担がかかりやすく、孤立や経済的な悩みも抱えやすい深刻な社会課題です。
無理のない両立には、制度や支援サービスの活用、家族との連携が欠かせません。
早めの準備と情報収集で、日々の負担を少しでも軽くする工夫が求められます。
高齢の親の介護に不安を感じたら、見守りサービスの導入も選択肢の1つです。離れて暮らす家族の安心を、見守りという形で支えてみませんか?
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら