「高齢者の冷え性の原因を知りたい」
「冷え性を放置するとどうなる?」
高齢者の冷え性に関して、上記のようにお悩みではありませんか?
年齢を重ねるにつれ、「手足が冷たい」「布団に入っても温まらない」と感じる人が増えます。
実は、冷え性は単なる体質ではなく、加齢による体の変化も深く関係しているのです。
本記事では、高齢者が冷え性になりやすい理由と、今日から始められる改善のヒントを解説します。
冷え性を放置することによって起こりうるリスクも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の冷え性を引き起こす5つの主な原因
高齢者が冷え性になりやすい背景には、いくつかの具体的な原因があります。
ここでは代表的な5つを見ていきましょう。
1. 筋肉量の減少
高齢者が冷え性を引き起こす原因の一つ目は、筋肉量の減少です。
筋肉は、体の中で熱を生み出す「暖房器具」のような役割を果たしています。
特に下半身の筋肉は全体の7割を占めており、ここが衰えると体全体の代謝が落ちる傾向にあります。
そして高齢になると運動量が減り、筋肉量も自然に低下するため、体が冷えやすくなるのです。
さらに座って過ごす時間が長い人ほど、血流が滞りやすく冷え性を悪化させる傾向にあります。
以下の記事では、高齢者が筋肉をつける方法を解説しているので、合わせて参考にしてください。
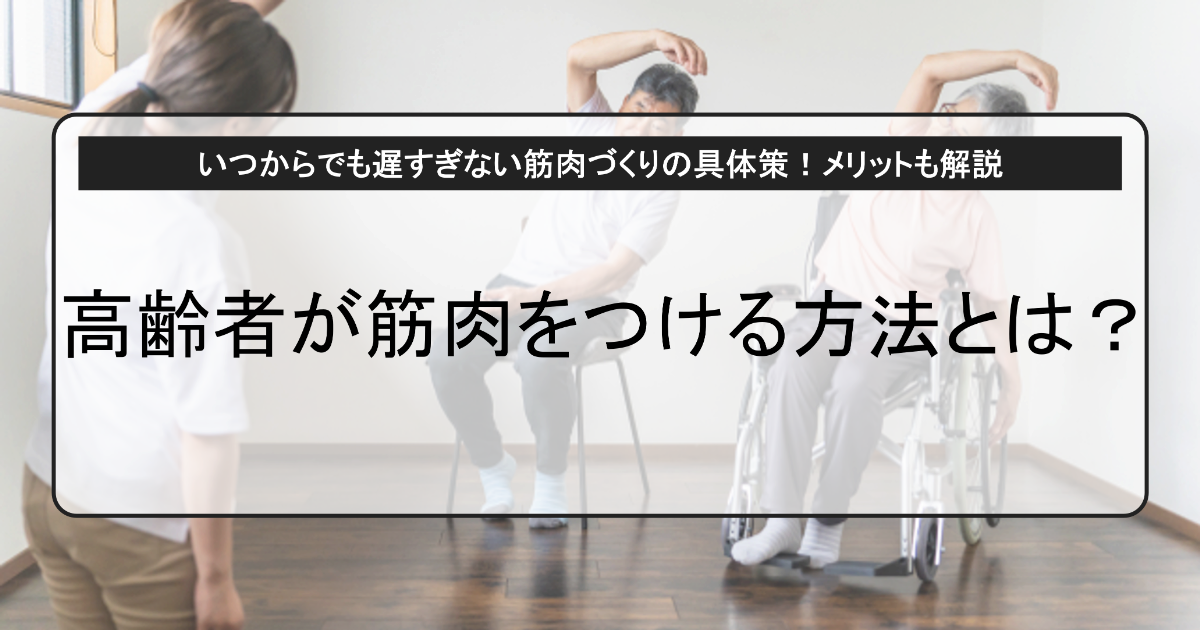
2. 血流の悪化
高齢者が冷え性になる原因の二つ目が、血流の悪化です。
血液は酸素と栄養を運ぶと同時に、体の熱を全身に届ける役割を持っています。
しかし高齢になると動脈硬化などで血管が硬くなり、血流がスムーズに流れなくなります。
その結果、末端の手足に十分な血液が行き渡らず、冷えを感じやすくなるのです。
また、高血圧や糖尿病といった生活習慣病がある人は、血流障害によって冷え性がさらに悪化しやすい傾向にあります。
以下の記事では高血圧の食事について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

3. 自律神経の乱れ
自律神経の乱れも、高齢者が冷え性になる原因の一つです。
自律神経は体温を一定に保つための「温度センサー」のような存在です。
寒いときに血管を収縮させて熱を逃がさないようにしたり、暑いときに汗を出して体温を下げたりしています。
しかし、高齢になると自律神経の働きが鈍くなり、気温の変化にうまく対応できません。
特にストレスや不眠、生活リズムの乱れは自律神経のバランスを崩し、冷えを感じやすくさせます。
4. 食生活の偏り
高齢者が冷え性になる原因の四つ目は、食生活の偏りです。
高齢者の中には、食欲の低下や調理の手間から、食事が偏りがちになる人も少なくありません。
炭水化物中心の食事や、たんぱく質・ビタミン・ミネラルが不足することで、代謝が低下し熱を作り出す力が弱まります。
また、冷たい飲み物や果物を多く摂ると体を内側から冷やす原因にもなるため、注意が必要です。
5. 服装や住環境の問題
服装や住環境の問題も、高齢者が冷え性になる原因の一つです。
冬場に厚着をしていても、体の首・手首・足首が冷えていると、体全体が冷たく感じます。
特に高齢者は衣服の調整がうまくできないことがあり、寒暖差による体温変化が起きやすい傾向があります。
また、室内が乾燥していると体感温度が下がるため、暖房だけでなく加湿も重要になるでしょう。
冷え性を放置するとどうなる?高齢者に起こりやすいリスク
冷え性を放置すると、高齢者の体にはさまざまな悪影響が生じます。
ここでは特に注意したいリスクを、体の免疫機能・筋肉や関節・睡眠・転倒の観点から詳しく見ていきましょう。
免疫力低下で風邪や感染症にかかりやすくなる
冷え性を放置することで、免疫力が下がり風邪や感染症にかかりやすくなる恐れがあります。
冷えによって血流が悪くなると、免疫細胞の働きが低下します。
体温が1℃下がると免疫力は約30%低下すると言われ、風邪や感染症にかかりやすくなるため、注意が必要です。
冷えは単なる不快感だけでなく、病気のリスクを高めるサインでもあります。
筋肉や関節の不調を悪化させる
冷え性を放置することで起こりうるリスクの二つ目は、筋肉や関節の不調を悪化させることです。
血流が滞ると筋肉や関節に十分な酸素や栄養が届かず、こわばりやしびれ、関節痛を引き起こしやすくなります。
体が冷えた状態が続くと、運動や日常動作にも支障をきたし、さらに筋肉が衰える悪循環に陥ります。
睡眠の質が低下する
睡眠の質の低下も、高齢者の冷え性を放置することで起こりうるリスクの一つです。
体が冷えるとリラックスしにくく、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。
熟睡できないことで疲労が蓄積し、日中の活動量が減るため、筋力低下や血流悪化を助長します。
冷えは眠りの質にも直接影響するのです。
転倒や骨折のリスクが高まる
冷え性を放置すると、転倒や骨折のリスクが高まる可能性もあります。
体は冷えによって筋肉がこわばると、バランスを崩しやすくなるのです。
特に高齢者は転倒による骨折や寝たきりのリスクが高く、生活の自立にも影響します。
高齢者の転倒予防について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
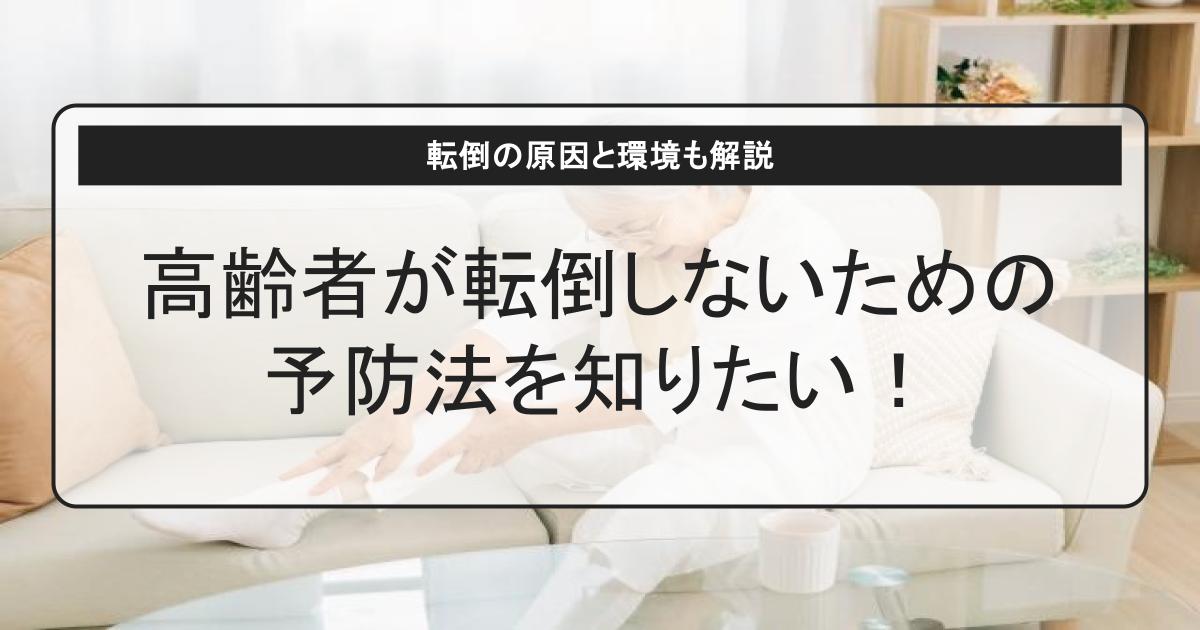
高齢者の冷え性を改善するための生活習慣
冷え性は、日常生活を少し見直すだけでも改善が期待できます。
特別なことをしなくても、体を温める習慣を意識することが大切です。
適度な運動を取り入れる
適度な運動も、高齢者の冷え性を改善するための生活習慣の一つです。
ウォーキングやストレッチなど、軽い運動を毎日続けることで血流が改善し、体温も上がります。
特に、太ももやふくらはぎの筋肉を動かす運動は効果的です。
無理のない範囲で「毎日10分歩く」など、継続できる目標を立てましょう。
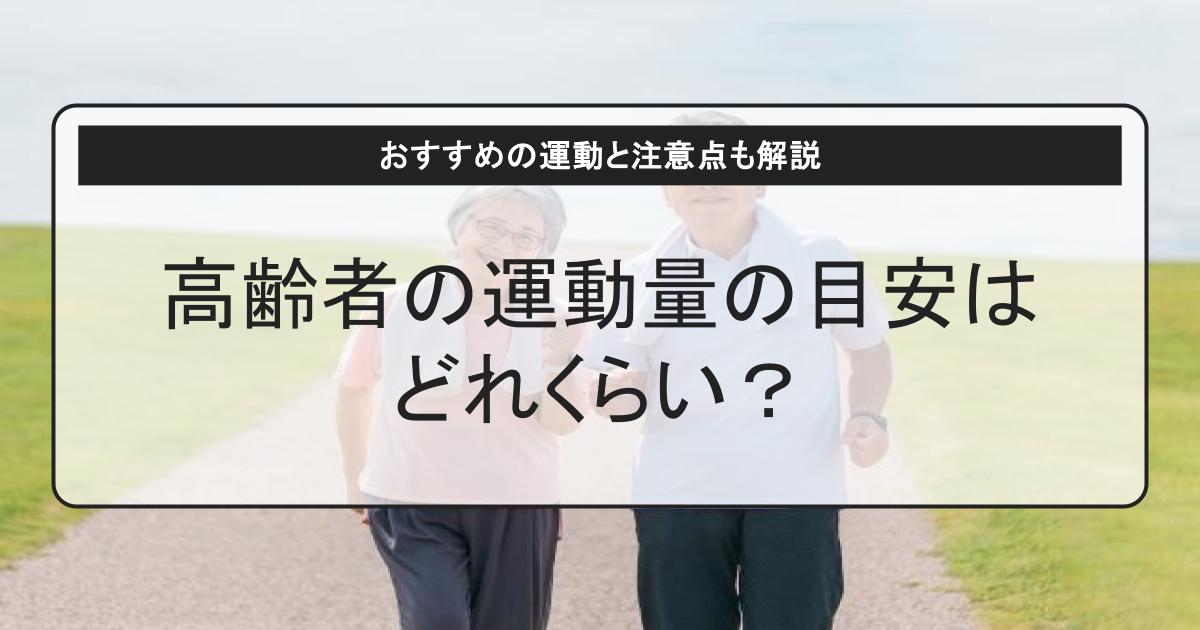
入浴で血流を促す
高齢者の冷え性では、入浴で血流を促すことも改善策の一つです。
お風呂にゆっくり浸かることで、体の芯から温まります。
38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど入るのがおすすめです。
シャワーだけでは十分に温まらないため、できるだけ湯船を活用しましょう。足湯や手浴も、冷えを感じるときに手軽に取り入れられます。
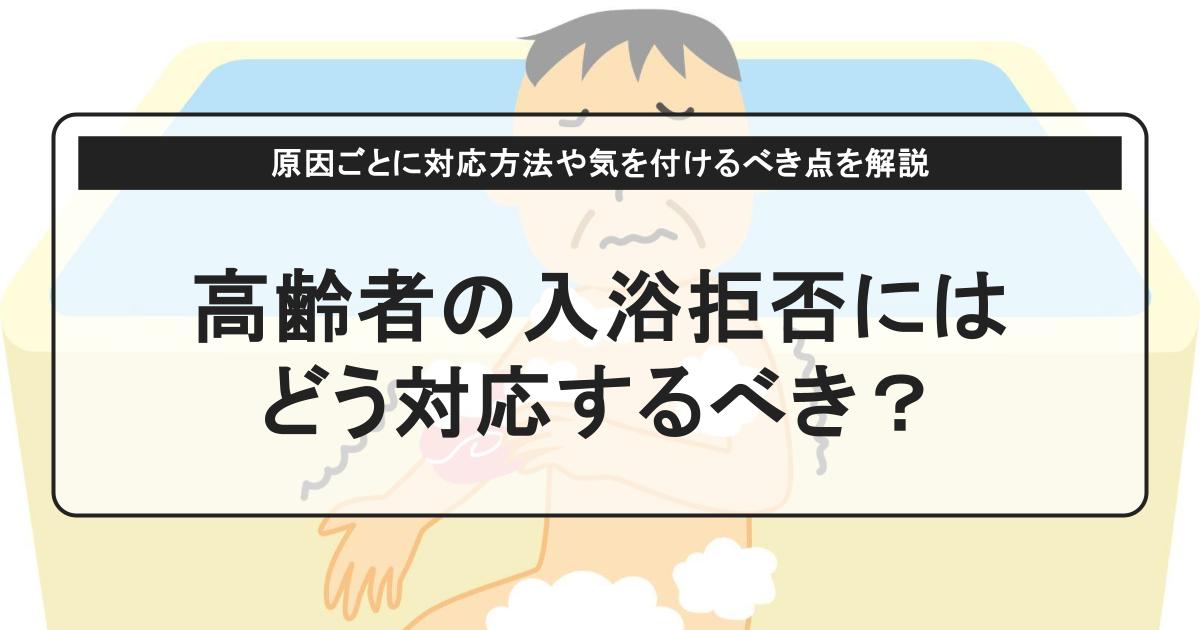
衣服の工夫
体を冷やさないためには、首・手首・足首を温めることがポイントです。
マフラーやレッグウォーマーを活用し、重ね着で温度調整を行いましょう。
外出時は風を通しにくい素材を選ぶと効果的です。
室内環境を整える
暖房だけに頼らず、加湿器を使って湿度を50〜60%に保つと、体感温度が上がります。
寝室では湯たんぽや電気毛布を安全に活用し、寝る前に部屋を軽く暖めておくのもおすすめです。
体の内側から温める!おすすめの食材と飲み物
体を温める代表的な食材には、以下のようなものがあります。
- かぼちゃ
- かぶ
- ニンニク
- ごぼう
- ピーマン
上記の食べ物は血行を促進し、代謝を高める働きがあります。
また、味噌やしょうゆなどの発酵食品も、腸内環境を整えることで体の冷えを改善する効果が期待できます。
飲み物では、白湯やしょうが湯、ハーブティーなどが効果的です。
カフェインの多いコーヒーや緑茶は体を冷やすことがあるため、飲みすぎには注意しましょう。
以下の記事では、高齢者の食事で気を付けたいことを解説しているので、合わせて参考にしてください。
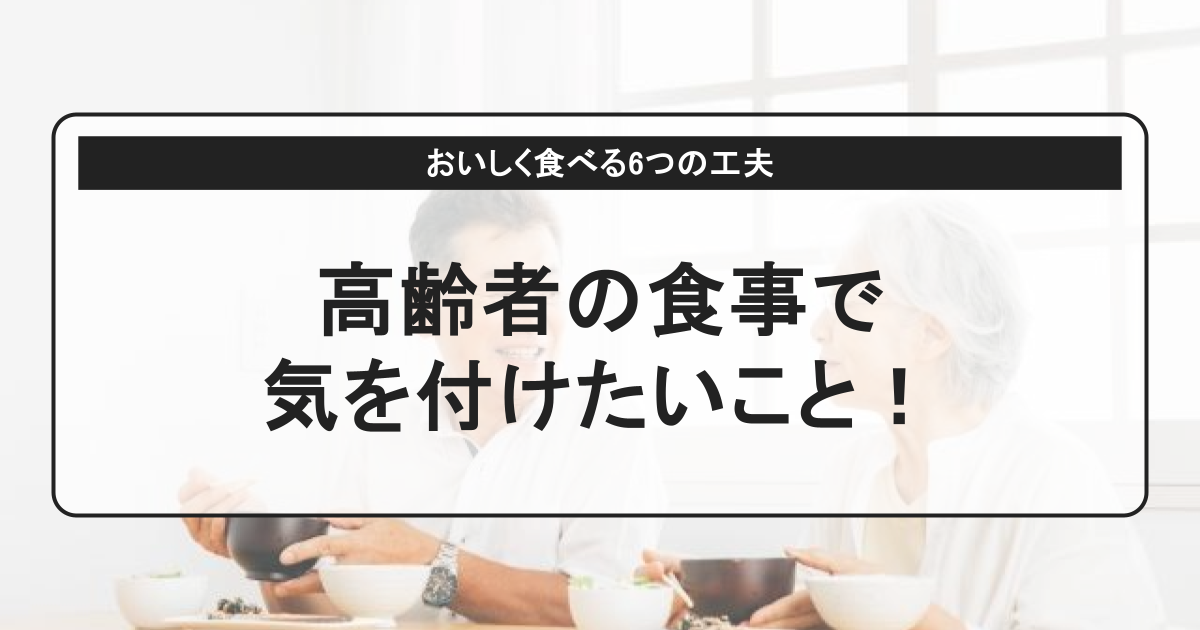
冷え性対策グッズ・機器も活用しよう
現代では、冷え性をサポートする便利なアイテムも増えています。
電気毛布や湯たんぽ、足温器などを上手に使えば、冬場の冷え対策がより快適になるでしょう。
特に就寝時は、足先を温めるだけでも眠りやすくなります。
ただし注意したいのは、低温やけどです。
長時間肌に直接当て続けるのは避け、必ず温度を確認してから使用しましょう。
また、加湿器を併用することで、乾燥による冷えも防げます。
まとめ:高齢者の冷え性は「原因を知ること」から始まる
高齢者の冷え性は、加齢による自然な現象と思われがちですが、実は体の不調のサインです。
筋肉量の減少や血流の悪化、自律神経の乱れなど原因を理解すれば、改善への道が開けるかもしれません。
食事・運動・入浴など、日々の生活習慣を少し見直すだけで、体は確実に温まりやすくなります。
冷えは放置せず、体調変化のサインとして早めに対処することが健康寿命を延ばす第一歩です。
家族と一緒に温かい食事を囲み、体を動かし、冷えに負けない毎日を過ごしましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









