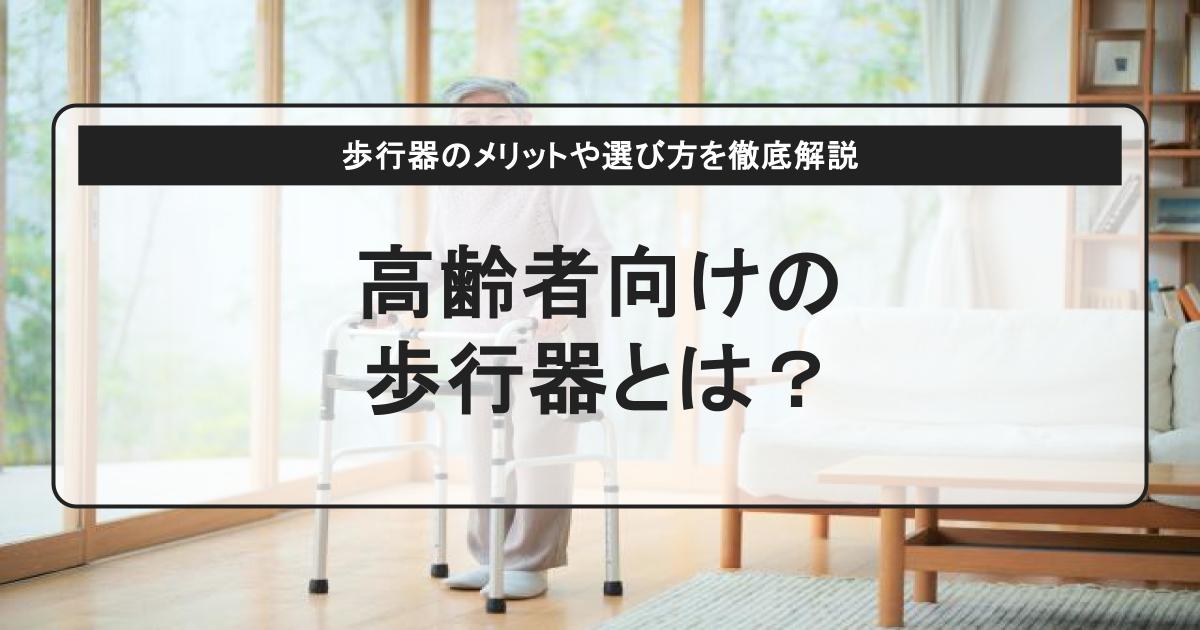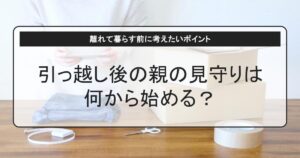「高齢者の親が歩くのが辛そう…」
「歩行器の利用で、少しでもラクになれる?」
高齢者の歩行をサポートする介護用品として、用いられる歩行器。
「歩く」という行為は、筋力を維持することで寝たきりを防ぐことができます。
ただし高齢になるにつれて歩く行為が億劫になり、外に出かけるのにも躊躇してしまうかもしれません。
そこでこの記事では、歩行器の特徴と使用することで得られるメリットを解説します。
また、歩行器の種類を紹介したうえで選び方も合わせて解説します。
「高齢者の歩行器って種類があるから、何を選べばいいのか分からない…」という方も、ぜひ参考にしてみてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら歩行器の特徴
歩行器は、介護保険を使ってレンタルできる介護用品の一つです。
車いすとは違って、立ったままの移動を助けてくれます。
歩行を補助する道具には「杖」もありますが、杖は1本の棒で支えるのに対し歩行器は4本足で囲むような作りです。
そのため、歩行器は体を安定して支えてくれます。
歩行器を使うことで体重を上半身に預けられるので、転びにくく足や腰の負担を減らしながら歩けるようになります。
また自分の足で歩けることは、生活の質(QOL)を上げて自信を保つのに役立つため、高齢者の心身の健康を支えるためにとても大切なのです。
歩行器を使うメリット
ここからは、歩行器を使うメリットを以下に分けて解説します。
- 足への負担を軽減できる
- 歩くときの姿勢が安定する
- 筋力低下を抑えられる
- 行動範囲が広がる
それぞれのメリットが理解できるように、詳しくチェックしていきましょう。
足への負担を軽減できる
高齢者が歩行器を使うことで、足への負担を軽減できる効果が期待できます。
歩くときに歩行器に少し体重をかけると、足腰にかかる重さが分散されて、歩きやすくなるのです。
特に「歩行車」と呼ばれる車輪のついたタイプだと、車輪の力でスムーズに進めるので、より一層体への負担が減り、楽に歩けるでしょう。
歩くときの姿勢が安定しやすくなる
歩行器を使うと、歩くときの姿勢が安定しやすくなります。
足腰の力が弱くなっていると歩くときにふらついたり、よろめいたりしやすいですが、歩行器に体を預けることでふらつきにくくなり、安定して歩けるでしょう。
特に高齢者の場合、ふらついたときに反応が遅くなるため、転びやすくなる傾向にあります。
歩行器を使って、しっかりと安定した姿勢を保つことが大切です。
筋力低下を抑えられる
歩行器を使用することで、筋力低下の予防も期待できます。
一般的に、年を取ると筋力がだんだん弱くなる傾向にあります。
筋力が落ちると、体を動かせる範囲も狭くなりがちです。
このようにまだ介護は必要ないけれど、介護が必要な状態に近づくことを「フレイル」と呼びます。
フレイルを防ぐためにはしっかり食事で栄養をとって、適度な運動をして筋力の低下を防ぐことが大切です。
そして歩行器を使って散歩をすることも、筋力を保つ助けになります。
なお、以下の記事では高齢者の食事について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
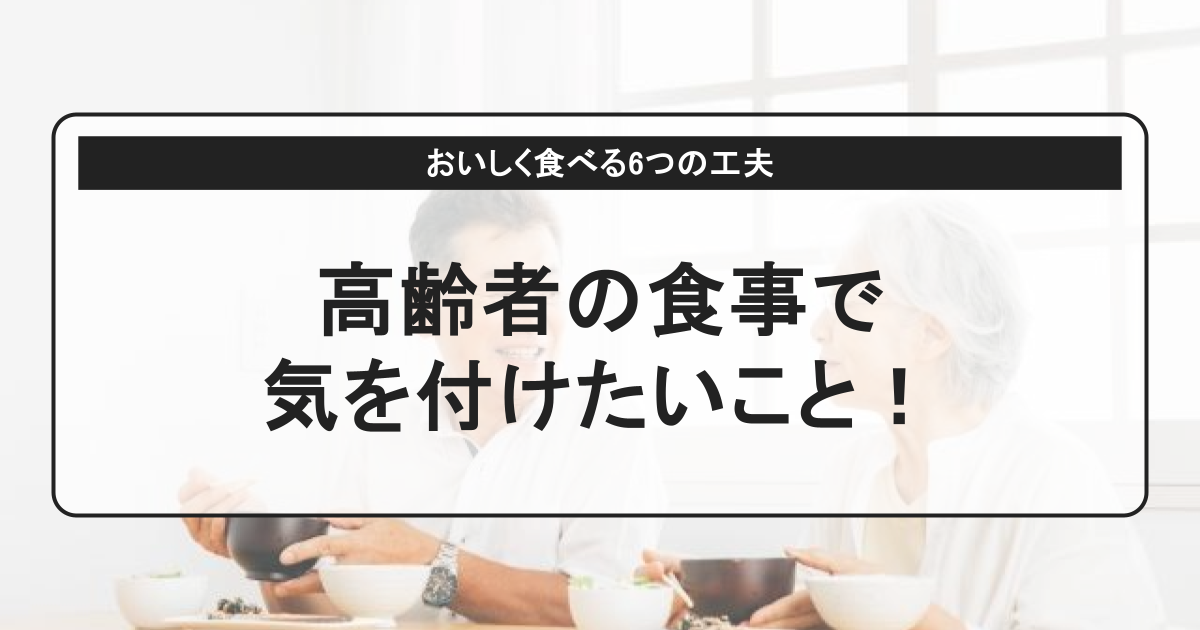
行動範囲が広がる
高齢者が歩行器を使うことで、行動範囲が広がります。
高齢になると歩ける距離が短くなり、行動できる範囲も狭くなりがちです。
国土交通省の「高齢者の生活・外出特性について」のデータによると、65歳以上の人のうち、休まずに1km以内しか歩けない人が約半数を占めていることがわかっています。
買い物や病院への通院など、すべての用事を1km以内で済ませるのは難しいことが多いです。
そんなときに歩行器を使うと歩きやすくなるため、行動範囲を広げられます。
足腰への負担も減るので、無理なく長く歩けるようになるでしょう。
歩行器の種類は主に3つ
ひと言で「歩行器」と言っても、様々な種類があります。
ここからは代表的な歩行器の種類を、以下に分けて解説していきます。
- 固定式歩行器(ピックアップ歩行器)
- 交互型歩行器
- キャスター付き歩行器(歩行車)
それぞれの歩行器の特徴が掴めるように、詳しく見ていきましょう。
持ち上げ型歩行器
持ち上げ型歩行器は、グリップを自分で持ち上げて前に進むタイプです。
この歩行器には、折りたたみ式と固定式があります。
折りたたみ式は狭いスペースに収納できるので、車の荷台に載せやすく外出先でも使えます。
ただし、折りたたみ部分の部品が増えるため、重くなりがちです。
また、このタイプは一般的に車輪が付いていないため、自立して歩く直前の歩行訓練に利用されます。
ただし持ち上げる際にバランスを崩しやすいため、筋力が低下している場合は注意が必要です。
前輪歩行器
前輪歩行器は、持ち上げ型歩行器の前の支柱に2つの車輪が付いたタイプです。
グリップに力をかけると、自動で車輪がロックされて動かなくなる仕組みになっています。
この歩行器はすべてを持ち上げる必要がないので、腕の筋力が弱くなっている方におすすめです。
キャスター付き歩行器(歩行車)
左右のフレーム下にキャスターや車輪がついており、押しながら歩くタイプの歩行器です。
両手や肘で支えるタイプがあり、ハンドブレーキや腰かけ、荷物入れがついているものがあります。
また、折りたたみ式や高さ調整が可能なタイプもあり、モーターや傾斜センサーが備わったものもあります。
折りたたみのタイプはバスなどの乗り物に便利で、坂道ではブレーキやモーター付きが安全ですが、その分重くなりがちです。
そのため、普段の生活環境や高齢者の体の状況に合わせて歩行器を選ぶようにしましょう。
歩行器の選び方のポイント
歩行器は、使用する方や状況によって選び方が変わります。
以下の項目を参考にして、高齢者が快適に歩行できるように、詳しくチェックしていきましょう。
- 使う目的で選ぶ
- 利用者の身体状況で選ぶ
- 身長の高さで選ぶ
使う目的で選ぶ
歩行器を選ぶときは、使う目的に合わせて選びましょう。
基本的に「持ち上げ型」の歩行器は室内での使用に向いています。持ち上げる力が必要になるので、段差が少なく、リハビリなどでの利用に適しています。
屋外で使う場合は、道の幅や段差の有無を確認しましょう。
段差が多い場所では持ち上げ型が便利で、道が狭い場所では幅を調整できる「折りたたみタイプ」がおすすめです。移動先で歩行器を車に乗せたいときも、折りたたみタイプが良いでしょう。
また、荷物を運びたいときは「シルバーカー」や椅子付きのタイプが便利です。
シルバーカーは、かごが付いているタイプや、休憩できる座面が付いたものなど、さまざまなタイプがあります。そのため、遠い先に買い物に行く際などにも向いているでしょう。
利用者の身体状況で選ぶ
歩行器を選ぶときは、以下の2つの身体の状態を確認しましょう。
- どれくらい力を入れられるか
- どの程度歩けるか
自立歩行ができて手すりの支えがあると歩ける場合は、「持ち上げ型歩行器」が適しています。
筋力が弱く、体重を少し支えながら歩きたい場合は「前輪歩行器」が良いでしょう。
歩くのが不安定でしっかりサポートが必要なら「四輪歩行器」を、自分で歩行を止められない場合や坂道などで使用するなら「ブレーキ付き」のものを選ぶと安心です。
身長の高さで選ぶ
歩行器は、使う人の身長に合った高さのものを選ぶことも大切です。
腕をグリップに乗せて使うタイプは、まっすぐ立って肘が90度に曲がる位置にグリップが来るように調整します。
グリップを握るタイプは、腕が30度ほど曲がる高さがちょうど良いでしょう。
また、身長に合わせたミニタイプや高身長用もあるので、利用者の身長や姿勢に合うものを選んでください。
高齢者に合った歩行器を選択して充実した毎日を!
歩行器には固定式やキャスター付きの歩行器など、様々なタイプがあります。
そのため、歩行器を使う高齢者や使用する用途に合わせて、正しく選ぶことが大切です。
歩行器を活用することで、足への負担を軽減して行動範囲を広げられます。
自分の足で歩けることは、生活の質(QOL)を上げられるため、高齢者の自信にも繋がるでしょう。
高齢とともに足の筋力が低下すると外出するのが億劫になり、寝たきりに繋がることもあるので、注意が必要です。
歩行器の種類にも様々なタイプがあるので今回紹介した選び方を参考にして、高齢者がスムーズに歩ける歩行器を検討しましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら