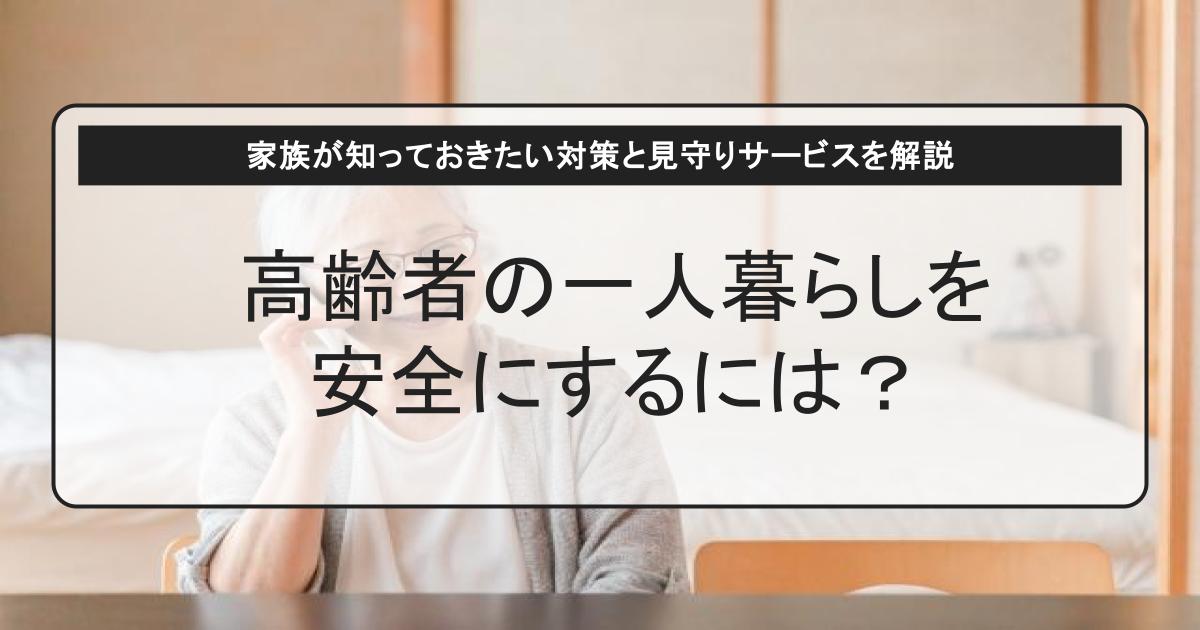「高齢者の親の一人暮らしが心配…」
「どうしたら安全に暮らせる?」
高齢の親が一人で暮らすようになると、自由で安心な生活を送れる反面、「本当に安全に過ごせているのだろうか」と心配になるものです。
特に離れて暮らす子ども世代にとって、その不安は毎日つきまとうかもしれません。
今回の記事では、高齢者の一人暮らしで起こりやすいリスクや家庭内での事故防止策、日常のちょっとした工夫を解説します。
また親の安心と安全を守るために、今からできる具体的な対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の一人暮らしの不安とは
近年高齢化が進むなか、一人で生活する高齢者は年々増加しています。
本人にとっては自由で気楽な生活ができる一方で、家族にとっては「安全に暮らせているのか」という心配がつきまといます。
まずは、高齢者の一人暮らしがどのような状況にあるのか、そして離れて暮らす子ども世代がどんな不安を抱えているのかを見ていきましょう。
高齢者の一人暮らしの現状
高齢者の一人暮らしは今後ますます増え、身近な問題になりつつあります。
総務省の統計によれば65歳以上の単独世帯は年々増加しており、都市部だけでなく地方でも目立ちます。
特に男性より女性の一人暮らしが多いのも特徴で、厚労省の調査では高齢女性の約2割が単身で生活しているとされているのです。
一人暮らしは本人の自由を尊重できる一方で、安全確保という課題を伴う点を忘れてはいけません。
子ども世代が抱える不安
離れて暮らす家族は、常に「もしも」の不安を抱えています。
高齢者の体調は急に変化しやすく、少しの事故が大事に発展するリスクが高いためです。
「昨日まで元気だったのに、今朝突然倒れて救急搬送された」「ガスを切り忘れて火災につながりかけた」といった事例は、決して珍しくありません。
こうした不安は毎日続くため、子世代にとって精神的な負担が大きくなるのです。
高齢者の一人暮らしに潜むリスク
高齢者が一人で生活するうえで心配なのは、ちょっとした出来事が大きな事故やトラブルにつながりやすい点です。
体力や判断力が若い頃に比べて低下しているため、家庭内での転倒や火の不始末、さらには孤独死といった深刻な問題も起こりえます。
ここでは、高齢者の一人暮らしで特に注意が必要なリスクを、具体的に見ていきましょう。
転倒や骨折など家庭内事故
高齢者の事故で最も多いのは転倒です。
加齢により筋力やバランス感覚が低下し、わずかな段差でもつまずきやすくなります。
浴室や階段、玄関の段差などが転倒の原因になりやすいと報告されています。
一度骨折すると寝たきりになるリスクが高く、生活の質が大きく低下するため、注意が必要です。
転倒予防については、以下の記事も合わせて参考にしてください。
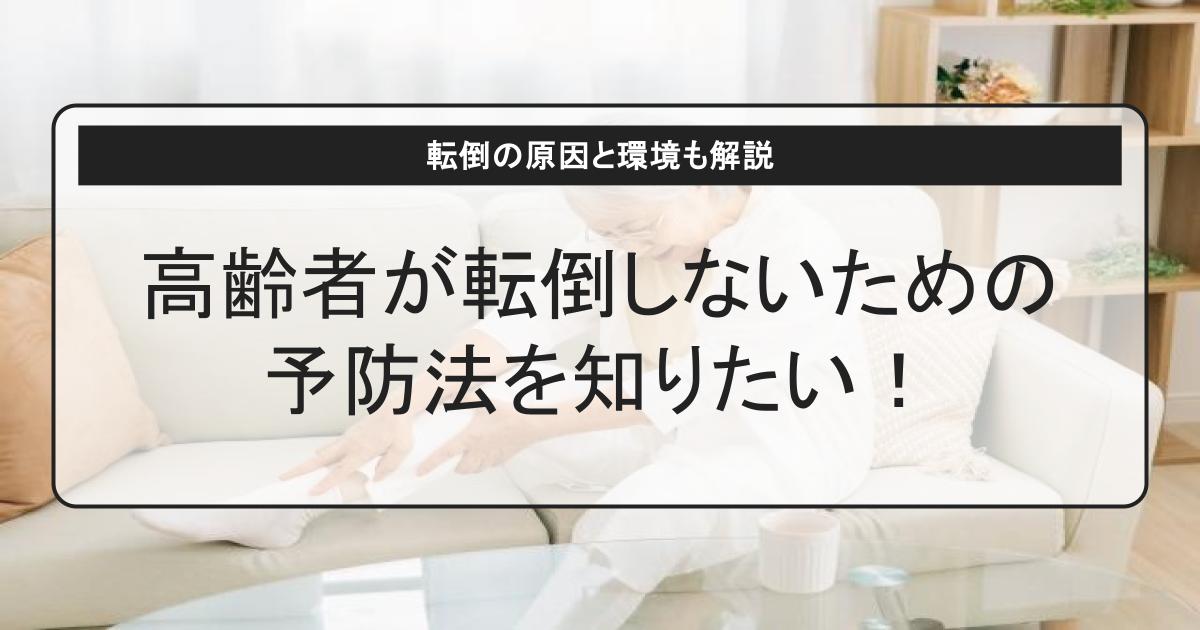
火の不始末や徘徊によるトラブル
認知症の初期症状がある場合、火や徘徊による事故リスクが高まります。
判断力や記憶力が低下すると「ガスを止め忘れる」「夜中に外へ出る」といった行動につながりやすいからです。
ガスコンロの火をつけたまま忘れてしまい、火事になりかけたケースや、深夜に外出して行方不明になり警察沙汰になったケースが挙げられます。
以下の記事では徘徊する高齢者を守るための対策を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

孤独死や急病の発見遅れ
高齢者の一人暮らしで最も深刻なのは「異変に気づかれないこと」です。
倒れても誰にも発見されなければ、救命のチャンスを失ってしまいます。
夏場の熱中症や冬のヒートショックは、短時間で命に関わる事態になることがあります。
家族が遠方に住んでいると、異変に気づくまでに数日かかってしまうケースも少なくありません。
高齢者が安全に暮らすための住環境の対策とは
特に家庭内での転倒やつまずきは大きなケガにつながりやすいため、住環境を整えることが欠かせません。
ここからは、日常生活の中で取り入れやすい住環境対策を具体的に紹介します。
段差解消や手すりを設置する
住宅内の転倒リスクを減らすにはバリアフリー化が効果的です。
家庭内事故の多くが小さな段差や浴室での滑りに起因するからです。
玄関の段差をスロープに変える、廊下や浴室に手すりを設置するだけで安全性は大きく向上します。
自治体の補助金制度を活用すればリフォーム費用の負担を軽減できます。
照明や家具配置を工夫する
明るく整理された環境は、事故防止につながります。
年齢を重ねると、視力の衰えによって暗い場所での段差や障害物が見えにくくなりがちです。
具体的には、廊下にセンサーライトを取り付ける、家具の配置を動線に合わせて整理するなどが挙げられます。
夜間のトイレ移動など、日常の動作を想定した環境改善が大切です。
ヒヤリハットを減らす整理整頓
「ヒヤリハット」とは、事故やケガには至らなかったものの、「ヒヤッとした」「ハッとした」出来事のことです。
ちょっとした不注意による事故は、整理整頓で予防できます。
床に物が置いてあるだけで高齢者にとっては大きな転倒リスクになるため、以下のような工夫が効果的です。
- 電気コードを壁際にまとめる
- カーペットのめくれをテープで固定する
- 滑り止めマットを敷くといった
また、家族が訪問した際に一緒に片付ける習慣を持つことで、無理なく安全な住環境を保ちやすくなります。
日常生活で安心を高める工夫とは
住環境を整えるだけでなく、日々の暮らしの中でちょっとした工夫を取り入れることも、高齢者の安全につながります。
ここからは、毎日の生活に取り入れやすい具体的な工夫を紹介していきます。
定期的な安否確認の習慣づけ
毎日のコミュニケーションは、異変の早期発見につながります。
普段の声や会話の内容から体調の変化を察知できるからです。
定期的な連絡によって、「電話で声が弱々しかった」「メールの返事が遅れている」など、小さな変化に気づけます。
近所・地域とのつながりを持つ
地域の人とのつながりは、安全ネットワークになります。
家族が見られない時間帯にも、周囲の人が気にかけてくれるからです。
民生委員や町内会の見守り活動を通じて、異変に気づいてもらえる可能性があります。
さらに高齢者本人も孤独感が和らぎ、精神的な健康にもつながるでしょう。
服薬や健康管理のサポート
日々の健康管理は、大きな事故を未然に防ぎます。
薬の飲み忘れや持病の悪化は、緊急搬送につながるためです。
近年では、服薬カレンダーやアラーム機能付きのピルケースも活用されています。
血圧計や体温計を使って、定期的に数値を記録する習慣を持たせるのも効果的です。
高齢者を見守るサービス3選
一人暮らしの高齢者を安全に見守るためには、家族だけで対応するのは限界があります。
そこで役立つのが、サービスを活用した見守りの仕組みです。
サービスを上手に取り入れることで、離れて暮らす家族も安心でき、万が一のときにも迅速に対応できます。
ここからは、特に利用しやすく効果的な3つの見守りサービスを紹介します。
見守りカメラや人感センサー
見守りカメラや人感センサーは、高齢者を見守るサービスでとても有効です。
スマホ連動のカメラやセンサーならリアルタイムで情報が届き、遠隔からでも親の様子を把握できます。
リビングに人感センサーを設置すれば、「動きが一定時間検知されない」と通知が来る仕組みを作れます。
プライバシーに配慮しつつ、設置場所を工夫することが大切です。

スマート家電やペンダント
スマート家電やペンダントも、おすすめの見守りサービスです。
スマート家電は、ガスや電気ポットの利用状況をチェックするだけで安否確認が可能です。
電気ポットを使った形跡がなければ「今日はまだ起きていないのでは?」と異変に気づけます。
また、緊急ボタン付きのペンダントを持たせれば、突然の体調不良にも即座に対応できます。


宅配・郵便を利用した訪問型見守りサービス
宅配業者や郵便局員が、訪問時に安否を確認してくれるサービスもあります。
例えば、郵便局の「みまもりサービス」では、配達の際に高齢者の様子をチェックし、家族へ報告してくれます。
また、宅配弁当などでも見守りサービスが付いている業者も増えてきています。
こういった訪問型のサービスでは、定期的に誰かと会話できる点で、孤独感の軽減にもつながるでしょう。
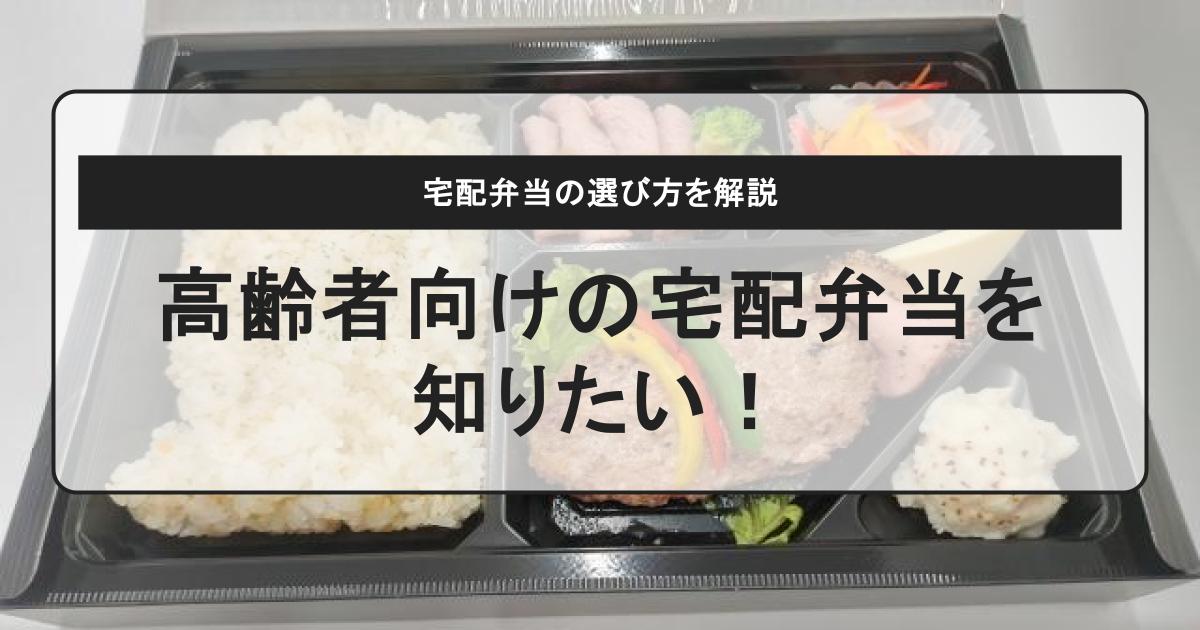
離れて暮らす家族ができること
高齢者の一人暮らしを支えるうえで、離れて暮らす家族の関わりは大きな安心につながります。
ただし、毎日付き添うことは現実的に難しいため、無理なく続けられる工夫やサービスの活用がポイントです。
ここでは、家族が日常的にできる具体的な方法を紹介します。
定期的な電話や訪問で安心感を与える
定期的な電話や訪問は、高齢の親に安心感を与えられます。
心の支えがあると高齢者の生活意欲が高まり、事故防止にもつながるでしょう。
毎週のビデオ通話や月1回の訪問など、決まったルールを設けると習慣化しやすいです。
形式にとらわれず「声を聞ける安心感」を優先することが大切です。
無理なく続けられる仕組みをつくる
続けられる工夫こそが、一番の見守りになります。
最初だけ頑張っても継続できなければ意味がありません。
兄弟で曜日を分けて電話をする、地域のサービスと併用するなど工夫すると良いでしょう。
家族全員で役割分担すれば、「一人で抱え込む」状態を避けられます。
まとめ|一人暮らし高齢者の安全は「工夫+サービス」で守れる
高齢者の一人暮らしには、転倒・火の不始末・急病といったリスクがつきものです。
家族の不安を軽減するには、住環境の改善・日常生活の工夫・見守りサービスの活用という3つの柱が欠かせません。
家族だけで見守りを続けるのは限界があります。
大切な親に安心して暮らしてもらうためにも、見守りサービスを上手に取り入れて、安全で穏やかな生活を支えていきましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら