「認知症の進行で徘徊してしまい、そのまま行方がわからなくなったらどうしよう」
「徘徊対策にはどんなものがある?」
上記のように認知症のご家族がいると、「知らない間に徘徊してしまうのでは」と不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、認知症による徘徊の原因やリスク、対策について解説します。
親御さんの徘徊を未然に防ぎ、危険から守りましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の徘徊による行方不明者数と死亡者数
高齢者の認知症による徘徊は、危険を伴う行為です。
2024年に認知症が原因で行方不明となった人は、1万8,121人にのぼります。
男女別では、男性が1万12人・女性が8,109人と、男性の割合が高い傾向です。
また行方不明者のうち491人が、徘徊中に死亡が確認されています。
引用:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和6年における行方不明者届受理等の状況」
認知症による徘徊の原因と特徴
認知症による徘徊は、脳の機能低下によって引き起こされる症状の一つです。
徘徊には以下の原因があり、理解を深めることで適切な対応が可能になります。
- 記憶障害
- 見当識障害
- 心理的要因
ここでは、徘徊をしてしまう原因について詳しく見ていきましょう。
また高齢者の認知症発症率については、以下の記事を参考にしてください。
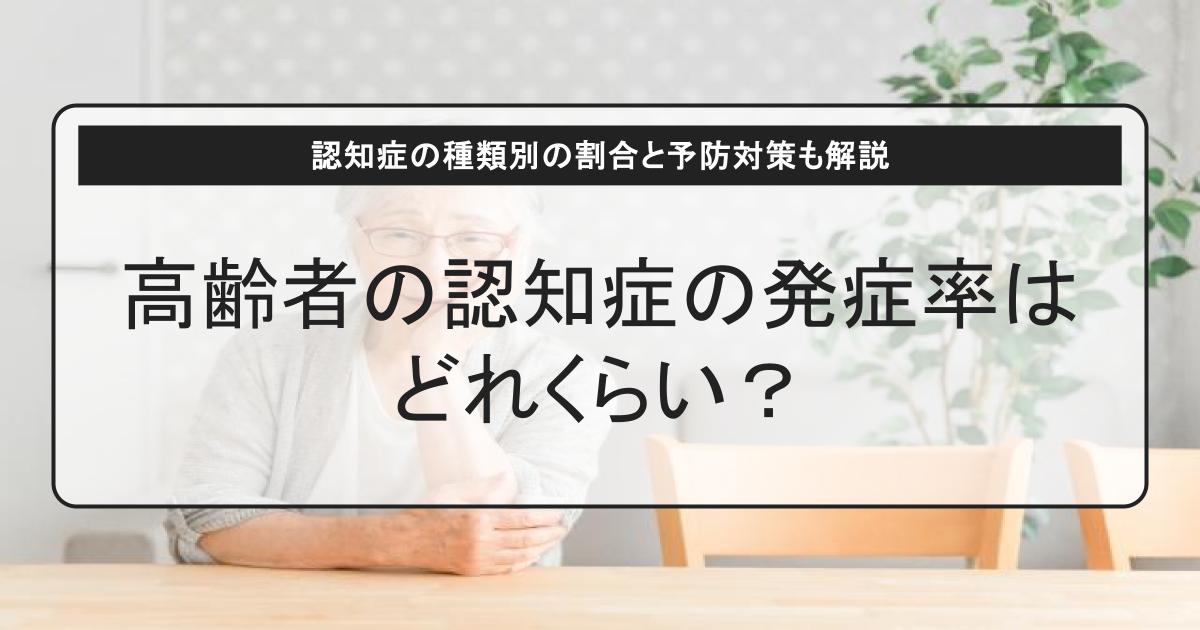
記憶障害
高齢者の認知症による徘徊の原因として、記憶障害が挙げられます。
記憶障害では、自分がどこにいるのか、どこから来たのかを忘れてしまい、家を探して徘徊してしまうのです。
現在の住まいを自分の家として認識できなくなり、過去に住んでいた実家や思い出の場所を探し求めて歩き続けるケースも多く見られます。
また、家族の顔を忘れてしまうことで、知らない人がいる場所だと感じて逃げ出そうとすることもあるでしょう。
記憶の混乱により、現在の状況を正しく理解できないため、安心できる場所を求めていると言えます。
見当識障害
認知症の高齢者の徘徊の原因として、見当識障害があります。
見当識障害とは、時間・場所・人の認識が難しくなり、現在の状況を正しく把握できなくなることです。
例えば、夜中でも「会社に行く時間だ」と思い込んでしまったり、真冬でも薄着で外出したりすることがあります。
時間の流れや空間の認識ができなくなることで、適切な行動判断が困難になるのです。
心理的要因
高齢者の心理的要因で、不安・焦り・孤独感が徘徊の引き金となるケースも考えられます。
環境の変化に対する戸惑いや、やることがない焦りから「どこかへ行かなければ」という衝動が生まれるのです。
また認知症により理解力が低下すると、些細な変化でも大きな不安を感じやすくなります。
家族がいない時間帯に一人でいることへの恐怖感や、自分の居場所がわからないという不安感から、安心できる場所を求めて外に出てしまいます。
高齢者がしてしまう徘徊の4つのパターン
認知症による徘徊には、以下のような代表的なパターンがあります。
- 帰宅願望による徘徊
- 役割探求型徘徊
- 日没症候群による徘徊
- 追跡型徘徊
それぞれについて解説していきます。
1.帰宅願望による徘徊
徘徊のパターンで最も多いのは、帰宅願望による徘徊です。
現在の家を自分の家と認識できず、昔住んでいた実家や故郷を探して歩き回るケースが挙げられます。
「ここは自分の家ではない」という思い込みから、本当の家を探そうと外出してしまうのです。
特に施設入所後や引越し後に多く見られ、慣れ親しんだ環境への強い帰宅欲求が徘徊行動となって現れます。
記憶の中にある昔の住所を目指して歩き続けるため、遠距離の移動になることも多く、発見が困難になりやすいでしょう。
2.役割探求型徘徊
高齢者が徘徊してしまう理由として、役割探求型徘徊があります。
役割探求型徘徊とは、過去の仕事経験や家事の習慣などが残り、「会社に行かなければ」「買い物に行かなければ」と外出してしまうことです。
退職から長い年月が経っていても、仕事への責任感や習慣が残っており、決まった時間になると職場に向かおうとする行動が見られるでしょう。
使命感がある過去の行動パターンは、徘徊につながりやすいのです。
3.日没症候群による徘徊
高齢者には、夕方から夜間にかけて起こりやすい「日没症候群」による徘徊も見られます。
時間の感覚が混乱して朝だと思い込んだり、薄暗くなる時間帯に不安が高まったりすることが原因とされているのです。
4.追跡型徘徊
高齢者の追跡型徘徊では、家族の後を追いかけて外に出てしまい、途中で見失って迷子になるケースです。
愛着のある人への依存心が強くなることで、その人が外出すると後を追って家を出てしまいます。
しかし、認知機能の低下により途中で目的を忘れてしまったり、道がわからなくなったりして迷子になってしまうのです。
認知症による徘徊がもたらすリスク
認知症による徘徊は、本人だけでなく家族全体に深刻な影響を与えかねません。
身体的な危険から精神的な負担まで、様々なリスクが存在するため、事前の理解と対策が不可欠です。
特に高齢者の場合、ちょっとした事故でも重篤な結果につながる可能性があります。
24時間の見守りが必要となることで、介護者の負担も限界に達するかもしれません。
行方不明や事故の危険性
高齢者の徘徊による最も深刻なリスクは、行方不明と事故といえるでしょう。
夜間や早朝の薄暗い時間帯での外出が、事故や死亡リスクを高める要因となっているのです。
季節を問わず軽装で外出してしまい熱中症や低体温症の危険や、長時間歩き続けることによる脱水や疲労状態に陥る場合も少なくありません。
河川や池への転落事故、段差での転倒による骨折なども重症に繋がります。
家族や介護者への精神や体への負担
高齢者の徘徊は、家族や介護者に大きな負担をもたらします。
精神面では、常に「いなくなるのではないか」という不安から、安心して眠ることができません。
また体への影響としては、24時間の見守りが必要となるため、介護者の睡眠不足や疲労の蓄積が深刻な問題となるでしょう
夜間に何度も起きて安全確認を行ったり、実際に捜索に出かけたりすると、周りの人の健康も損なわれがちです。
長期間こうした状況が続くと、介護うつや家族関係の悪化につながることもあります。
高齢者の認知症による徘徊を防ぐ4つの対策
認知症の高齢者の徘徊を防ぐためには、適切な対策を行いましょう。
高齢者の徘徊予防には、家庭内の環境を整えることや生活習慣の改善など、さまざまなアプローチが必要です。
完全に防ぐことは困難でも、発生頻度を減らしたり、早期発見につなげたりできれば負担を軽減できます。
ここでは家庭でできる対策について解説していきます。
1.家の中や玄関の安全リフォームによる徘徊リスク軽減
家の中や玄関の安全リフォームは、最も重要な徘徊対策です。
玄関には分かりにくい場所に補助錠を設置し、無断外出を防ぐ必要があります。
また窓やベランダにも安全対策を施し、転落防止柵を設置するなどの安全対策をしましょう。
2.運動や生活リズムの調整で予防
生活リズムを整えることで、徘徊の予防につながる効果が期待できます。
毎日同じ時間に起床・就寝し、食事時間を一定にすることで、体内時計を整えておきましょう。
日中に散歩や軽い体操、デイサービスでのレクリエーション活動などを取り入れる適度な運動は、高齢者の体にもいい影響を与えます。
日中の運動は夜間の良質な睡眠につながり、夜中の徘徊を減らす効果があるのです。
また水分摂取のタイミングを調整し、夜間のトイレ回数を減らせれば徘徊防止にも役立ちます。
昼寝の時間や長さを適切にコントロールし、夜間の睡眠に影響しないような配慮も大切です。
以下の記事では、高齢者の運動の目安を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
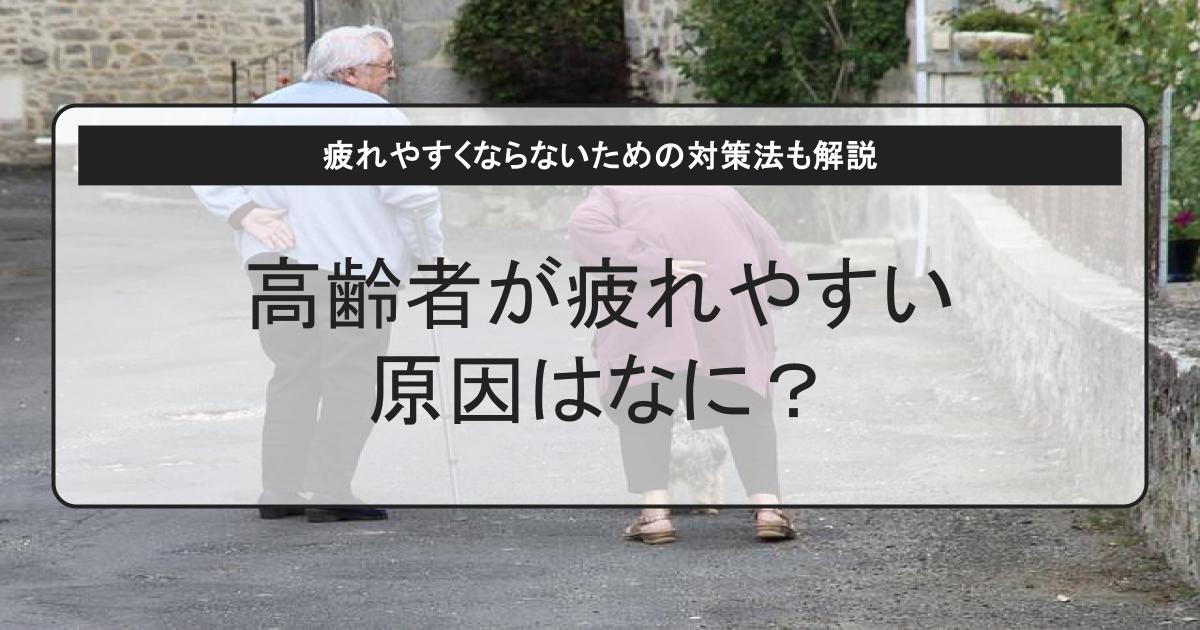
3.GPSやセンサーなど徘徊対策グッズの活用
現代ではさまざまな徘徊対策グッズが開発されており、適切な活用で安全性を大幅に向上させられるでしょう。
最新のIoT技術(機器をインターネットに接続する技術)を活用した見守りシステムでは、センサーが反応したり、AIが学習できる機能も登場しています。
GPS機能付きの小型端末を靴や衣服に装着すれば、万が一の際の位置特定が可能になります。
スマートフォンアプリと連動し、設定した範囲を離れた際にアラートが届く機能も便利です。
また赤外線センサーを活用したドア開閉感知システムでは、夜間の無断外出をいち早く察知できます。
高齢者を見守るGPSについて以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。
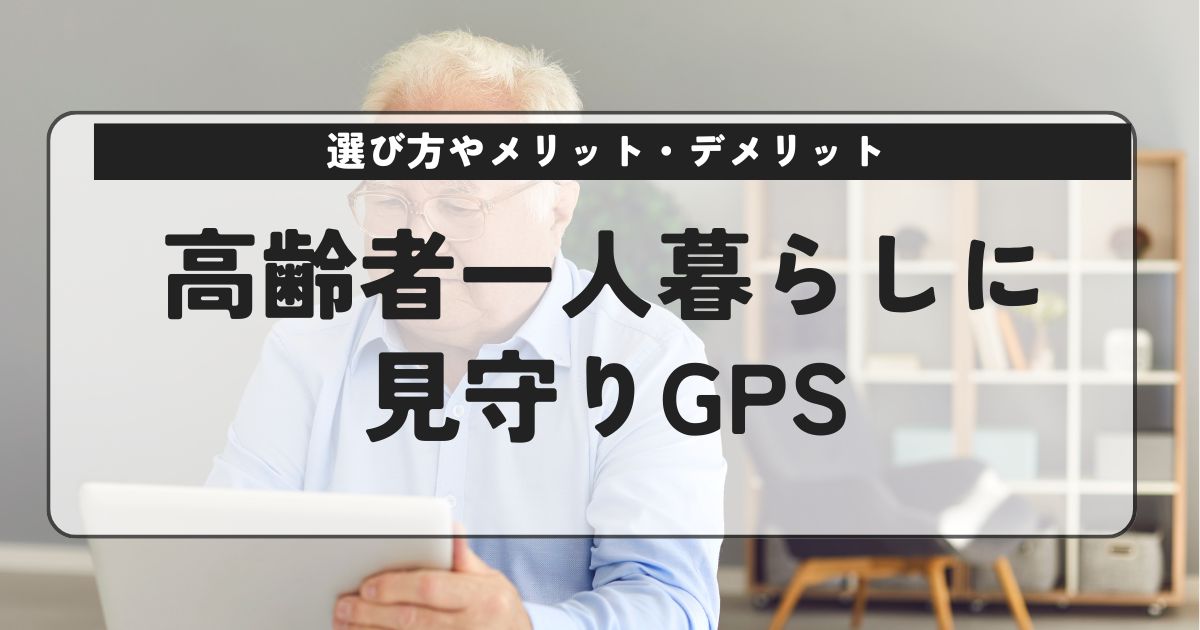
4.デイサービスや施設入所の検討
高齢者の徘徊対策において、家族以外の専門的な支援を受けることが可能です。
デイサービスの利用により、日中の安全な活動場所を確保し、夜間の徘徊リスクを軽減できます。
専門スタッフによる適切な対応とプログラムで、認知症の進行を緩やかにする効果も期待できるのです。
短期入所サービス(ショートステイ)を定期的に利用できれば、家族の休息時間を確保し、介護負担を軽減します。
徘徊が頻繁で家族での対応が困難な場合は、グループホーム(認知症の方が共同生活を送る施設)や特別養護老人ホームへの入所も選択肢となります。
「地域包括支援センター」では、個々の状況に応じた最適なサービスの紹介や調整を行っているため、家族では判断が難しい場合の相談先として活用してみましょう。
デイサービスのサービス内容やメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。

徘徊が起きたときの正しい対応
徘徊が実際に発生した際の対応は、高齢者の身を守るため早急に見つけ出す必要があります。
慌てて探しに出るよりも、まずは冷静な行動を取りましょう。
早期発見・保護のためには、事前準備と適切な連携体制が必要です。
発見後の接し方によっては、本人を更に混乱させてしまう恐れもあるため、正しい対応方法を知っておきましょう。
警察や地域との連携
高齢者の徘徊が発生した際は、速やかに警察署に行方不明者届を提出することが最優先です。
届け出る際には、以下のような情報提供が必要になります。
- 本人の写真
- 身体的特徴
- 着衣
- よく行く場所
- 徘徊の傾向
- 位置情報(GPS機能付きの機器を使用している場合)
同時に地域包括支援センターに連絡し、地域のネットワークを活用した捜索協力も依頼しましょう。
近隣住民や商店、交通機関への協力要請も有効です。
事前に都道府県や市町村の「徘徊高齢者SOSネットワーク」のような地域見守りシステムに登録しておくことで、迅速な対応が可能になります。
以下の記事では、地域包括支援センターの役割について詳しく解説しています。

発見時は優しく穏やかな接し方と声かけ
徘徊中の高齢者を発見した際、接し方や声のかけ方も大切です。
発見した際はまず慌てずに、優しく穏やかな口調で安心させる言葉をかけてください。
責めるような言葉は避け、無理に手を引いたり、強制的に連れ戻そうとしたりすると、恐怖心や反発心を生む可能性があります。
本人の気持ちに寄り添い、「一緒に帰りましょう」「お茶でも飲みませんか」など自然な流れで帰宅に導いてください。
高齢者に対して時間や場所の間違いを指摘するのではなく、本人の意向を尊重して話しましょう。
公的支援制度や介護保険で再発防止
高齢者の徘徊の再発防止には、公的支援制度や介護保険制度の活用が可能です。
地域生活支援事業として、「徘徊高齢者SOSネットワーク」への登録や、「QRコード」のシール配布サービスを無料提供している自治体も増えています。
自治体によっては、GPS機器の購入費用に対して補助金制度を設けているところもあります。
お住いの地域によって補助内容が異なりますが、受けられる支援をうまく活用していきましょう。
高齢者の身を守るために徘徊対策を行いましょう
認知症による徘徊は、高齢者の身に危険を及ぼす可能性があります。
認知症の症状を理解し、環境や生活習慣の改善、最新の見守り技術を組み合わせ、徘徊の軽減につなげましょう。
また家族だけで抱え込まず、公的支援制度や介護保険サービス、地域のネットワークを積極的に活用してください。
離れて暮らすご家族の場合は、見守りサービスの導入により、安全な環境に整えることも可能です。
正しい知識と対策を取り入れて、認知症の方もご家族も、より安心した生活を送れるようにしましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









