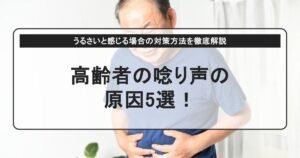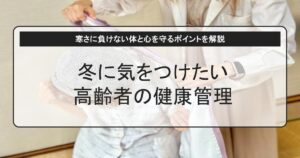「高齢者の親が最近やつれてきた気がする」
「高齢者の低栄養を見分ける方法はある?」
上記のように悩んでいませんか?
低栄養とは体に必要な栄養が不足し、健康に影響を及ぼす状態です。体重やBMI値、血液検査などから確認でき、原因には加齢や社会的な要因、心の状態も関係します。
今回の記事では、低栄養の原因やリスクを詳しく解説し、栄養バランスの取れた食事の工夫や楽しく食べるコツなど、実践しやすい対策法を紹介します。
健康的な食生活を続けるために、ぜひ最後までご覧ください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら低栄養とは
低栄養とは食欲が落ちたり、噛む力が弱くなったりすることで、食事の量が減ってしまう状態です。体を動かすためのエネルギー・筋肉・皮膚・内臓を作るたんぱく質などの栄養が不足してしまいます。
厚生労働省の調査(令和元年度 国民健康・栄養調査)によると、65歳以上で低栄養傾向のある人(BMI20以下)は、男性の約12%、女性の約21%でした。特に85歳以上では、男性17%、女性28%とさらに割合が増えています。つまり、年齢が上がるほど低栄養のリスクも高くなるのです。
さらに、「要介護の高齢者の約20~40%、入院中の高齢者の約30~50%が、低栄養の状態にある」といわれています。
低栄養になる原因
低栄養の原因はさまざまで、大きく分けて以下の3つの要素が関係しています。
- 身体の変化
- 社会との関わりの変化
- 心の状態
加齢や病気による影響だけでなく、食事の環境や気持ちの変化も低栄養を引き起こす要因になります。
それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。
身体の変化
低栄養の原因の1つ目が、身体の変化です。
筋力が弱くなったり足の痛みがあったりすると、長い距離を歩くことや重い荷物を持つのが困難になり、外出が面倒に感じることがあります。
そのため買い物に行っても、軽くて持ち運びやすい即席麺やパンなどを選びがちです。
また、調理する人が腰や膝の痛みで長時間立つのがつらくなると、料理を簡単に済ませるようになるかもしれません。
調理済みの加工食品を利用したり、品数を減らしたりすることも増えるでしょう。
さらに噛む力の衰えや味覚の変化、消化の不調(下痢や便秘など)によって食欲が落ち、食事の回数が3食から2食に減ることもあります。
社会との関わりの変化
社会との関わりの変化も、低栄養の原因の1つです。
一人暮らしや社会とのつながりが少ないと、外に出る機会が減って買い物の回数も少なくなりがちです。
また交通手段が限られている地域では、買い物に行くのが大変になることもあります。
さらに近くに生鮮食品を売っている店がないと、腐りやすい食品を買うのを控え、代わりに保存しやすい菓子パン・加工食品・即席麺・レトルト食品などを選びがちです。
経済的に厳しい場合も生鮮食品の購入を控えたり、食べる量を減らしたり、食事の内容が偏ったりすることにつながります。
「買い物に行くのが面倒で大変…」という方は、宅配弁当の利用がおすすめです。以下の記事で宅配弁当について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
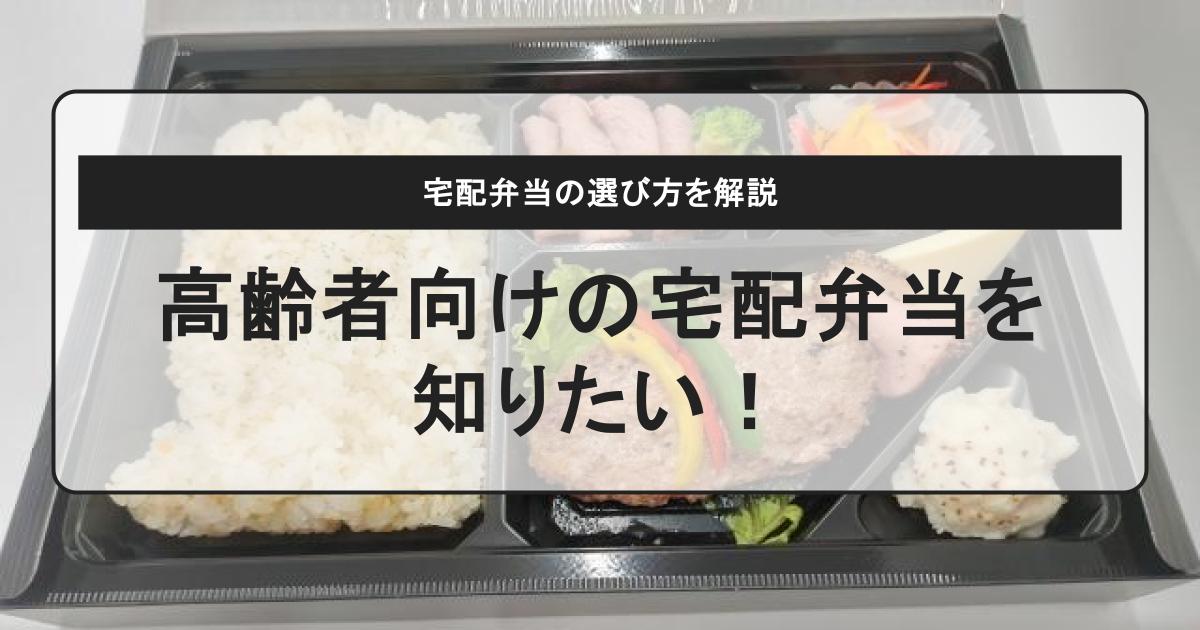
心の状態
心の状態によっても、低栄養になることがあります。
高齢者は、配偶者やペットを失うことで大きな精神的ストレスを感じ、食欲が落ちることがあるのです。
また年を重ねるにつれて、これまでできていたことが難しくなることも喪失感につながります。
例えば以下の変化に気づくと、自信を失ってストレスを感じる傾向にあります。
- 歩くのが遅くなった
- 耳が聞こえにくくなった
- 食事中にむせたり食べこぼしたりするようになった
- 車の運転がうまくできなくなった
また認知機能が低下すると、買い物で同じものばかり買ったり、味付けがおかしくなったりする場合もあるかもしれません。
このような状況になると本人だけでなく、一緒に暮らしている家族の栄養状態にも影響が出ることがあります。
認知症について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせて参考にしてください。

低栄養への対策法
低栄養を防ぐためには、食事に気をつけることがとても大切です。
日々の食事習慣や栄養バランス、食事の楽しさが健康に大きな影響を与えるかもしれません。
ここからは、低栄養を予防するための具体的な対策方法を紹介します。
1日3食摂る
低栄養への対策方法の1つ目が、1日3食摂ることです。
1回の食事で食べる量が少なく1日3食しっかり食べないと、必要なエネルギーやたんぱく質が足りなくなってしまいます。
また規則正しい食事の習慣は、生活全体を整えることにもつながります。
規則正しく活動することで空腹感を感じ、自然と食事をしっかり摂るようになるでしょう。
栄養バランスの良い食事を摂る
栄養バランスの良い食事を摂ることも、低栄養を防ぐための手段の1つです。
甘い菓子パンやカップラーメン、袋麺などの加工食品で食事を済ませてしまうと、栄養が偏る可能性があります。
肉・魚・卵・乳製品・大豆製品など、たんぱく質が豊富な食品を毎食のおかずに1品加えるようにしましょう。
特に、日本食は「一汁三菜」と呼ばれ、栄養バランスが整いやすい食事スタイルです。
主食・主菜・副菜を選ぶ際には好きなものだけに偏らず、さまざまな種類の食品を取り入れると、バランスの良い栄養を摂ることができます。
ただし、塩分が多くなりがちなので、汁物は1日1杯程度にするよう心がけましょう。
以下の記事では高齢者のたんぱく質の重要性について解説しているので、合わせて参考にしてください。

栄養補助食品を摂る
低栄養を防ぐための1つに、栄養補助食品を摂る方法もあります。
栄養補助食品は、毎日の食事だけでは不足しがちな栄養素を補うために便利な食品です。
また低栄養の方だけでなく、口の機能が低下して固形物が食べにくい方にも向いています。
栄養補助食品はゼリーやドリンクタイプが多く、デザート感覚で食べやすく工夫されているものが多いです。
また高カロリーでエネルギーを補うもの、たんぱく質を補うもの、ビタミンを補うものなど、目的に応じた種類がたくさんあります。
栄養補助食品は、大型薬局やスーパーで購入できますが、選ぶ際には、かかりつけの薬剤師や医師に体の状態や食生活を伝えて、最適なものを選んでもらうことをおすすめします。
低栄養に気づくためのポイント
「低栄養」は本人が気づかないうちに進んでしまうことが多いため、周りの人が早めに気づいて予防することが大切です。
以下のチェックポイントを参考にして、低栄養になっている可能性があるかを確認してみましょう。
- 食事の量が減ってきている
- 卵・肉・魚を食べないときがある
- 起き上がったり立ち上がったりすることがきつい
- 過去3か月で体重が2~3㎏減った
- BMI(体格指数)が20未満
なおBMIは、体重(kg)÷「身長(m)×身長(m)」という計算になります。
もし1つでも当てはまる場合は、低栄養に気をつける必要があります。
日常生活の中で、少しずつ改善に取り組んでいきましょう。
高齢者と低栄養でよくある質問
高齢者の低栄養については、多くの疑問や不安があるかもしれません。
ここからは低栄養とフレイルの関係や、低栄養が続くとどのような影響があるのかについて、詳しく解説します。
高齢者の低栄養とフレイルの関係は?
低栄養は、フレイル(虚弱)の大きな原因のひとつです。
フレイルとは、高齢者にみられる体重の減少や疲れやすさ、歩く速さや筋力の低下などの状態を指し、このまま進行すると要介護のリスクが高まります。
フレイルが進むと、筋肉量の低下を引き起こす「サルコペニア」や、骨や関節、筋肉の衰えによって歩行や日常生活に支障をきたす「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」につながることが知られています。
最終的には寝たきりの状態になる可能性もあり、この「負の連鎖」を防ぐためにも、低栄養を早めに改善することが大切です。
高齢者のフレイル予防について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

高齢者の低栄養が続くとどうなる?
高齢者の低栄養が続くと、さまざまな健康障害を引き起こします。
免疫力が低下して感染症にかかりやすくなるほか、床ずれや傷の治りが遅くなることがあるのです。
また筋肉や骨の量が減少し、転倒や骨折のリスクが高まります。
特に高齢者は骨折やケガの回復が遅く、痛みの影響で動くことが減ると、筋肉量や筋力がさらに低下してサルコペニア(筋肉量や筋力の低下)の状態になります。
その結果1日のエネルギー消費が減り、食欲が低下して食事の量も減ってしまい、さらに低栄養が進むという悪循環に陥る可能性があるため注意が必要です。
高齢者の低栄養は早めに対策をとろう
高齢者の低栄養は食欲の低下や身体の変化、社会との関わりの減少、心の状態などが原因で進行する傾向にあります。
低栄養が続くと免疫力の低下や筋力の衰え、転倒・骨折のリスクが高まり、フレイルやサルコペニアにつながる可能性があります。
しかし、一人暮らしの高齢者や遠くに住む家族の体調の変化に気づくのは難しいでしょう。
そんな方は、当社の「ハローライト」をご検討ください。
こちらのサービスは、電気のオン・オフを感知し、一定時間操作がないと異変を察知して家族に知らせます。
例えば「朝になっても電気がつかない、夜になっても消えていない」といった変化をキャッチします。
特に食事や活動量の減少が心配な高齢者にとって、生活リズムの乱れは重要なサインです。
手軽に設置できる「見守りライト」で、大切な家族を優しく見守りましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら