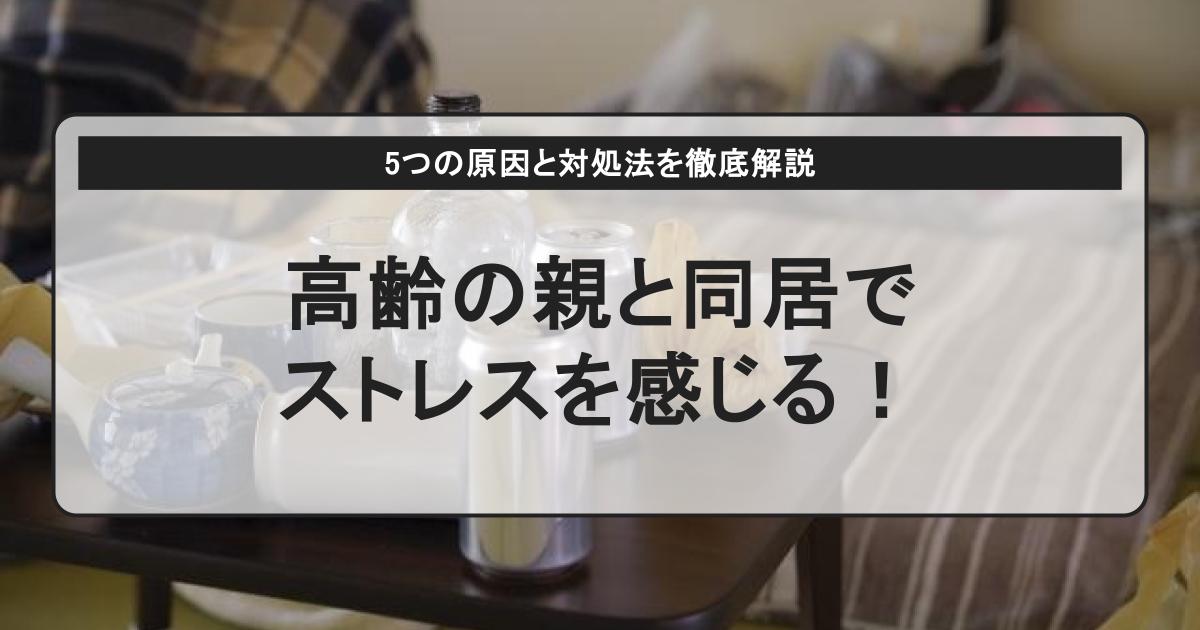「高齢の親との同居がストレスになる…」
「同居のストレスはどうやって対処するべき?」
上記のように、高齢の親との同居で感じるストレスに悩んでいる方も多いでしょう。
本記事では、高齢の親との同居でストレスを感じる原因から対処方法まで詳しく解説していきます。
また、親との同居が難しいと感じている方のために、同居以外の選択肢も提案しているので、ぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢の親との同居でストレスを感じる原因5選
高齢の親との同居でストレスを感じる原因として、以下の5つが挙げられます。
- 生活習慣や価値観の違いによる摩擦
- プライバシーの欠如
- 介護や家事の負担の偏り
- 親の言動による心理的ストレス
- 夫婦関係や子育てへの悪影響
それぞれの原因を詳しく解説していくので、自分に当てはまる原因がないかをチェックしておきましょう。
ストレスを感じている原因をしっかりと理解するだけでも、高齢の親との同居によるストレスを軽減できます。
生活習慣や価値観の違いによる摩擦
高齢の親との同居でストレスを感じる原因の1つ目は、生活習慣や価値観の違いによる摩擦です。
例えば、以下のような日常の行動に違いがあると、ストレスを感じやすくなります。
- 起床時間
- 就寝時間
- 食事の量
- 食事の味付け
- テレビの音量
- 入浴の順番
このような些細な違いで、高齢の親との小競り合いが増えてしまう恐れがあります。
しかし、育った時代や健康状態の違いなどによって、生活習慣に違いが生まれるのは仕方のないことです。
また、「もったいない」「こうするべきだ」などの価値観の違いも、親子関係に摩擦が生じてしまう原因の1つです。
生活習慣や価値観の違いが悪いというわけではありませんが、思いやりに欠けた発言をしてしまうと、同居時にストレスを感じてしまいます。
プライバシーの欠如
高齢の親との同居でストレスを感じる原因の2つ目は、プライバシーの欠如です。
実際に高齢の親と同居している方の中には、「自分の時間や空間が守れない」という不満を抱えている方が多くいます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 常に親の生活音が聞こえる
- 勝手に部屋に入られる
- 来客者を勝手に自宅に入れる
共有スペースが多い間取りの場合、日々の生活で気配りをする時間が増えるため、十分に休養を取れる時間がありません。
自分の空間を守ることは、心身の回復に必要不可欠であるため、しっかりとプライバシー対策をしていくことが重要です。
介護や家事の負担の偏り
高齢の親との同居でストレスを感じる原因の3つ目は、介護や家事の負担の偏りです。
高齢の親と同居する場合は、介護度の有無にかかわらず、以下のようなサポートが必要になります。
- 通院の同行
- 服薬管理
- 見守り
- 食事作り
- 買い出し
- 洗濯
高齢者は一人でできることが少なくなるため、日常のあらゆる活動でサポートしなければなりません。
これらの介護や家事は、家族内で公平に役割分担されているケースが少なく、高齢の親と同居している人に負担がかかりがちです。
高齢の親の介護に加えて、育児や仕事などの負担がある場合は、さらにストレスがかかります。
親の言動による心理的ストレス
高齢の親との同居でストレスを感じる原因の4つ目は、親の言動による心理的ストレスです。
加齢によって、記憶力・判断力・聴力などが低下したり、イライラしやすくなったりします。
加齢による変化は、親に悪意がない場合でも親子関係の摩擦を生みやすいです。
心理的ストレスになる例として、以下のような言動が挙げられます。
- 同じ話の反復
- 否定的な言い回し
- 子育てや家事への過干渉
しかし、これらの言動に悪意があるわけではなく、高齢の親の不安や孤独感が原因である可能性も考えられます。
高齢の親に孤独を感じさせないためにも、孤独な老後を過ごす人の特徴を把握しておきましょう。
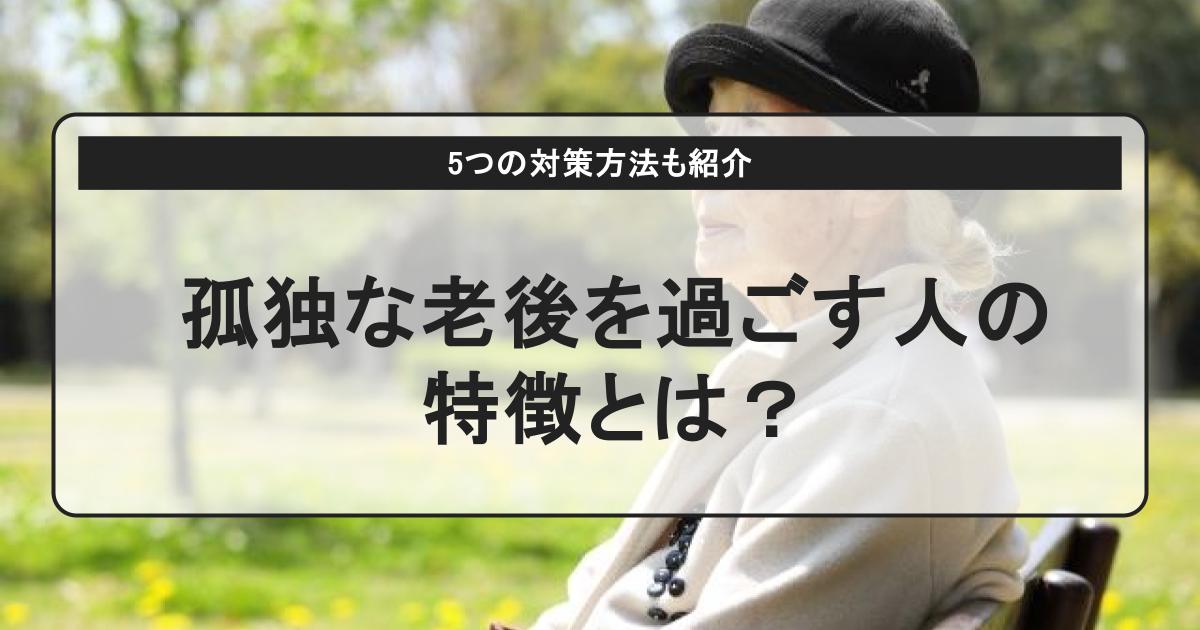
また、高齢者がイライラする原因については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
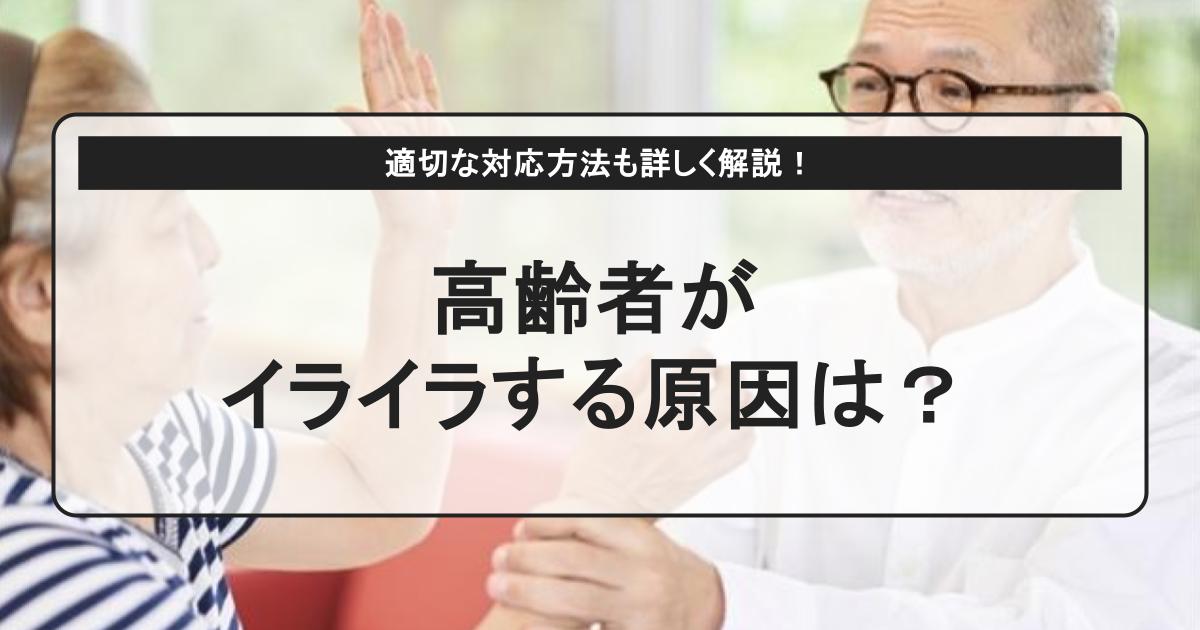
夫婦関係や子育てへの悪影響
高齢の親との同居でストレスを感じる原因の5つ目は、夫婦関係や子育てへの悪影響です。
高齢の親との同居によるストレスが原因で、配偶者や子供に八つ当たりをしてしまうと、家族関係が悪化する可能性があります。
また、高齢の親に、子育て方針や生活リズムについて口出しをされるケースも少なくありません。
例えば子育てにおいて、しつけ・勉強方法・生活習慣などの口出しが増えると、家庭内で2つのルールを抱えることになり、子供が混乱します。
子供が祖父母や親の意見が食い違う場面を日常的に目にすると、どちらの言葉を信じればよいか迷い、悪影響を及ぼしてしまいます。
高齢の親との同居によるストレスの対処方法5つ
高齢の親との同居によるストレスの対処方法として、以下の5つを解説していきます。
- 物理的・心理的に適度な距離感を保つ
- お互いを尊重するコミュニケーションを取る
- 家事や介護の役割分担を明確にする
- ケアマネや地域包括支援センターを頼る
- 自分自身の心身をケアする
ストレスを感じる原因を把握できたら、次にそれぞれの対処方法を実践していくことが大切です。
ストレスを感じたまま高齢の親と同居を続けていると、さらに親子関係が悪化する可能性が高まります。
親子関係を改善するためにも、紹介する内容を参考にしながら、しっかりと対策をとっていきましょう。
物理的・心理的に適度な距離感を保つ
高齢の親との同居によるストレスの対処方法1つ目は、物理的・心理的に適度な距離感を保つ方法です。
同居生活では、常に一緒にいる時間が増えるため、無意識にストレスが溜まるケースも少なくありません。
ただ高齢の親と距離を取るのではなく、心地良い距離感を意識するのが大切です。
例えば、リビングで一緒に過ごす時間と、自室でゆっくりと過ごす時間を設ける方法があります。
「1日3時間は自室でゆっくり過ごす」などのルールを決めておけば、ストレスを軽減できます。
また、親と同居していると自宅でゆっくり過ごせないという方は、外出をするのもおすすめです。
高齢の親に「一人の時間も大切にして欲しい」と伝えたり、デイサービスを利用してもらう方法も、適度な距離感を保つために効果的です。
お互いを尊重するコミュニケーションを取る
高齢の親との同居によるストレスの対処方法2つ目は、お互いを尊重するコミュニケーションを取ることです。
親の考えや気持ちを完全に否定するのではなく、ひとつの意見として受け止めてみましょう。
否定的な返答をすると、親も反発して否定的な発言をしてしまう場合があります。
そのため、意見が違うと感じても「そう感じるんだね」と優しく受け止めるのが大切です。
また、どうしても感情的になってしまう場合は、一度深呼吸をして時間を空けてから離すことも効果的です。
少し時間を置くだけでも、怒りは静まりやすくなります。
お互いを思いやるコミュニケーションで、親子の関係を良好に保ちましょう。
高齢者とのコミュニケーションについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
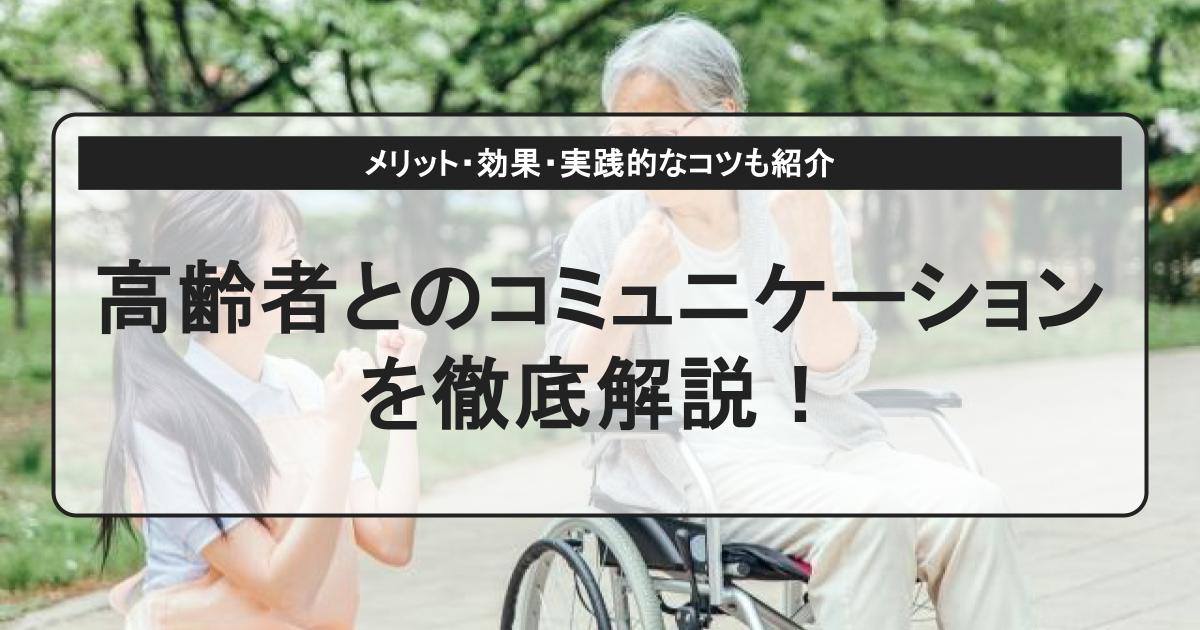
家事や介護の役割分担を明確にする
高齢の親との同居によるストレスの対処方法3つ目は、家事や介護の役割分担を明確にすることです。
家事や介護自体に不満がない場合でも、負担が一方に偏れば不公平感でストレスを感じるというケースも多くあります。
同居していない兄弟姉妹がいる場合にも、家事や介護の役割分担を決めておく必要があります。
例えば、同居している家族は日常の家事や病院の付き添いを担当して、遠方に住む家族は介護費用の一部を負担するなどのルールを話し合う方法もおすすめです。
ケアマネや地域包括支援センターを頼る
高齢の親との同居によるストレスの対処方法4つ目は、ケアマネージャーや地域包括センターを頼ることです。
「家族のことは自分たちだけで解決する必要がある」と考えている方も多いですが、第三者のサポートを活用して同居のストレスを軽減することも重要です。
ケアマネージャーは介護保険のサービス調整を行っており、地域包括支援センターは相談全般を受け付けてくれます。
例えば「デイサービスを利用して親の外出時間を増やしたい」「介護用品で負担を軽減したい」といった要望を伝えれば、現実的な支援策を考えてもらえます。
第三者に相談をするだけで、高齢の親との同居によるストレスが和らぐケースも多いです。
自分自身の心身をケアする
高齢の親との同居によるストレスの対処方法5つ目は、自分自身の心身をケアすることです。
親の世話や気配りに追われると、自分の健康や感情を後回しにしてしまう方も多いです。
疲れ切ってしまうと、高齢の親に優しく接することができなくなり、関係性が悪化する恐れもあります。
最低でも週に1度は好きなことをする時間を設けるのがおすすめです。
運動・趣味・友人との会話など、リフレッシュできる時間が心の安定につながります。
高齢の親との同居を避ける選択肢3選
高齢の親との同居でストレスを感じている場合は、同居を避けるという選択肢もあります。
高齢の親との同居を避ける選択肢として、以下の3つを紹介していきます。
- すぐに会える距離で別居する
- 見守り・家事支援サービスを活用する
- 高齢者向け施設に入居してもらう
それぞれの方法を詳しく解説していくので、親との同居が難しいと感じている方は参考にしてください。
すぐに会える距離で別居する
高齢の親との同居を避ける選択肢の1つ目は、すぐに会える距離で別居する方法です。
車で10~30分ほどの距離に住めば、必要な時にすぐ駆け付けられるうえ、普段はお互いに気兼ねなく生活できます。
用事がない場合は会いに行かないというわけではありません。
「週末は一緒に食事を楽しむ」「体調が悪い時は泊まりに行く」など、定期的に会う機会を設けるのがおすすめです。
柔軟に関わり方を調整できるため、高齢の親にストレスを抱えることなく、快適に過ごせるでしょう。
また、地方自治体では、高齢の親と同居・近居する場合の支援補助金を出している場合があります。
例えば、千葉県松戸市では「親元近居・同居住宅取得支援」が利用できます。
お住いの自治体で、支援を受けることができるかどうかを確認してみましょう。
見守り・家事支援サービスを活用する
高齢の親との同居を避ける選択肢の2つ目は、見守り・家事支援サービスを活用する方法です。
同居を避けて親を一人暮らしさせるうえで、親の生活に不安を抱いている方も多いでしょう。
見守りサービスや家事支援サービスを取り入れれば、同居していなくても安心を確保できます。
見守りサービスには、センサーやカメラを設置して生活の変化を通知したり、電気やガスの使用状況を確認したりできるタイプなど、さまざまな形があります。
また、家事支援・買い物代行・食事の宅配などを組み合わせれば、親が一人暮らしでも安心できるでしょう。
高齢者の見守りサービスについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
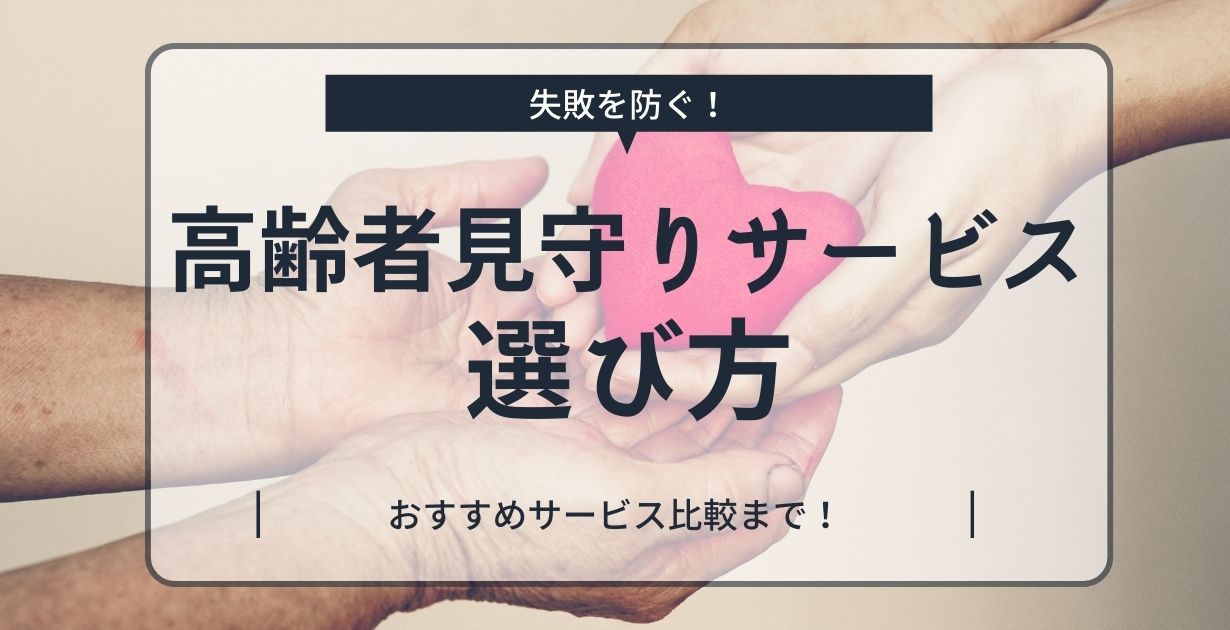
高齢者向け施設に入居してもらう
高齢の親との同居を避ける選択肢の3つ目は、高齢者向け施設に入居してもらう方法です。
施設では、24時間の見守りや医療機関との連携が整っているため、親の生活に不安を抱える必要がありません。
食事・入浴・掃除などの日常的な支援を受けられるため、高齢の親も快適に生活を送れます。
さらに、同年代の入居者と交流できるため、コミュニケーション不足による寂しさも感じづらいです。
また、親を施設に入れると後悔するのではないかと不安を感じている方は、以下の記事も参考にしてください。
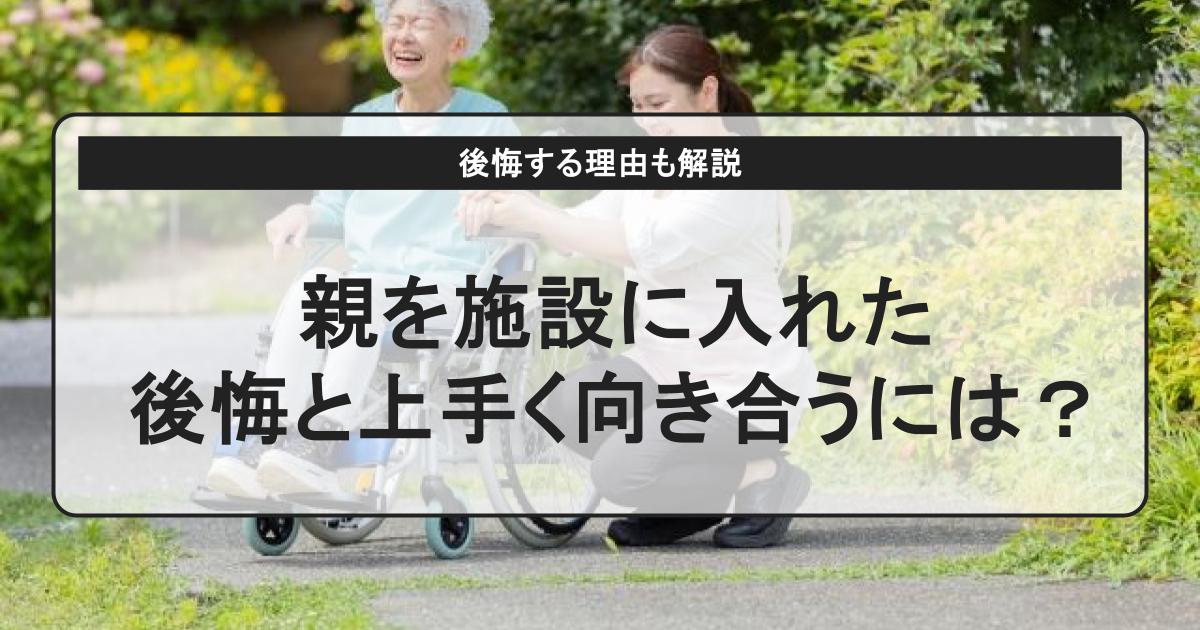
高齢の親との同居ストレスに関するQ&A
高齢の親との同居でストレスを感じている方からよくある質問をまとめました。
親との関係で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
Q1:同じ話を何度もされてイライラしてしまう
高齢になると記憶力の低下や不安感から、同じ話を繰り返すことがあります。
大切なのは「またその話?」と否定せず、一度共感を示すことが重要です。
例えば「そうだったね」と受け止めてから、自然に話題を変えましょう。
また、テレビや写真など別の関心ごとに誘導するのも効果的です。
無理に我慢せず、イライラしたら一度席を外したり、深呼吸をしたりするなど、距離を取るのが大切です。
Q2:親が物を捨てられず部屋が片付かない
高齢者にとって、物は思い出であるため、無理に捨てさせようとすると反発を招く恐れがあります。
まずは「安全のために通路だけ確保しよう」など、小さな目標から始めましょう。
感情的にならず、片付けの専門家や自治体のごみ屋敷対策支援・整理収納アドバイザーを頼るのも有効です。
第三者が入ることで親も納得しやすく、家庭内の衝突を防げるでしょう。
Q3:金銭感覚の違いで衝突してしまう
高齢の親と子供の間で、お金の使い方や節約意識に差があるのは仕方のないことです。
トラブルを防ぐには、感情論ではなく数字で共有することが大切になります。
例えば、家計簿アプリやノートを使い、収支を数字で見えるようにするのがおすすめです。
「誰が何にどれくらい支払うか」を明確にしておけば、不信感や不公平感が減ります。
特に介護費や食費など共有支出は、毎月記録しておくと安心です。
Q4:配偶者がストレスを感じている場合どうする?
同居によるストレスは、親よりも配偶者に負担が集中することも少なくありません。
親の前で無理に良い顔をせず、別居やデイサービス利用などを検討して、夫婦が心地よく過ごせる形を一緒に探すことが大切です。
夫婦の仲が悪くなれば、親へのサポートを続けられなくなる恐れもあるため、まずは配偶者のストレスを気にかけてあげましょう。
親との同居で感じるストレスと上手く付き合おう|まとめ
本記事では、親との同居によるストレスについて詳しく解説しました。
高齢の親との同居は、安心感や助け合いの面で大きなメリットがある一方で、生活習慣の違いやプライバシーの欠如、介護負担の偏りなど、ストレスの原因も多く存在します。
適度な距離感を保ち、感情的にならないコミュニケーションを意識して、役割分担や専門機関の活用で負担を分散させましょう。
それでも難しいと感じる場合は、近居や見守りサービス、施設入居などを検討してください。
ストレスを抱え込まず、支援制度や周囲の助けを上手に使いながら、長く安心できる親子関係を築いていきましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら