「最近、高齢の親が”ふんふん”と声を出すようになり、何かの病気ではないかと心配している」
「認知症の初期症状なのかわからず、不安で対応に困っている」
上記のように親の介護をしている中で、親が「ふんふん」や「んーんー」という声を頻繁に出すようになり、気になっている方はいませんか?
本記事では、高齢者が「ふんふん」と声を出す原因や注意すべきポイント、家族がとるべき対応方法について詳しく解説します。
最後まで読むと、高齢者の声が出る背景を正しく理解し、適切で冷静な対処ができるようになります。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者が「ふんふん」言う5つの原因と注意すべきポイント
高齢者が「ふんふん」などの声を出す背景には、加齢・病気・心理的な不安など、さまざまな要因が関係している可能性があります。
安易に「大丈夫」と決めつけず、正しい知識をもとに観察することが重要です。
ここでは、代表的な原因を5つに分けて解説します。
1. 加齢による自然な変化
高齢者が発する「ふんふん」という声は、加齢による自然な変化として表れることがあります。
年齢を重ねると、のどや口の筋肉が衰え、呼吸に伴って無意識に声が漏れてしまうのです。
特に会話がないときや睡眠中に目立ちやすく、本人に自覚がない場合も少なくありません。
加齢による変化の場合、日常生活に大きな支障がなければ、過度に心配する必要はないでしょう。
2.認知症の初期症状
高齢者の「ふんふん」という声は、認知症の初期症状である可能性があります。
認知症は脳の働きが低下し、感情や行動に変化を引き起こします。
症状の特徴としては、時間や場所への混乱が見られたり、同じ動作や発声を繰り返したりすることがあります。
また、夕方から夜間にかけて症状が悪化する「夕暮れ症候群」と呼ばれる現象も認知症の特徴的な症状です。
症状が継続したり、他の認知機能の低下が見られる場合は、早めに専門医の診察を受けましょう。
高齢者の認知症で起こりうるリスクついては、以下の記事で詳しく解説しています。

3.せん妄状態による一時的な症状
せん妄とは、急激な環境の変化や体調不良によって起こる一時的な意識の混乱状態のことです。
認知症とは異なり、適切な治療により改善する可能性があります。
せん妄の特徴として、症状の程度が時間帯によって変動することや、注意力の低下が見られ、幻覚・錯覚を伴うことです。
症状は数日から数週間で変化するため、認知症と区別して考える必要があります。
発熱や脱水、薬の副作用などが原因となるケースが多く、原因を取り除くことで改善に期待ができます。
4.神経系疾患による影響
パーキンソン病や発声障害のような神経系疾患によって、発声に影響が出ることがあります。
これらの疾患では、筋肉の制御が困難になり、意図しない発声が起きてしまうのです。
注意すべき症状には、手足の震え・動作のにぶさ・歩行時のバランス困難が挙げられます。
また、表情の変化が乏しくなったり、声の大きさや明瞭さに変化が現れたりすることもあります。
なお、「チック症」のような反復的な動作や発声は小児期に多いので、高齢になって現れた場合は、別の神経疾患による影響と考えられるでしょう。
日常生活に支障がある場合は、早めに神経内科医に相談してください。
5.不安や孤独など心理的要因の影響
高齢者が「ふんふん」と声を出す背景には、心理的な要因も関係している可能性があります。
一人で過ごす時間が長くなると、不安や孤独感から無意識に声を出して気持ちを落ち着かせることがあります。
また、周囲の反応を求めているケースもあり、心のサインである可能性があるため、否定せず優しく見守ることが大切です。
医師への相談が必要なケースと判断基準
高齢者が「ふんふん」と声を出す原因が病気でなかった場合でも、医師への相談が必要になることがあります。
体に異常がなくても、生活への影響や人間関係のストレスを引き起こすことがあるためです。
ここでは早急な相談が必要なケースと、様子を見るケースを解説します。
早急な相談が必要なケース
以下のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 急激に症状が悪化
- 発熱や意識レベルの低下
- 幻覚や妄想などの精神症状
- 日常生活に著しい支障
様子を見ながら相談を検討するケース
高齢者の発声頻度が徐々に増えている場合や、夜間の睡眠が妨げられている場合は、様子を見ながら相談を検討しましょう。
家族の介護負担が大きくなっている場合や、本人が困惑や不安を示している場合も同様です。
意思疎通が図れる場合は、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談することで、適切な対応策が得られるでしょう。
「ふんふん」言う高齢者へ家族ができるサポート5選
高齢者が「ふんふん」と声を出す行動に対して、周囲の対応はとても重要です。
「ふんふん」と言う原因が病気であっても無意識であっても、適切な環境や関わり方を工夫することが、症状の緩和や安心感につながります。
ここでは、家族が実践しやすいサポート方法を5つにわけて紹介します。
1.環境の見直しと安心できる空間づくり
高齢者が静かで安心できる空間を整えることが、心の安定に役立ちます。
騒音を減らして静かな環境を作り、部屋に季節感のある装飾を加えることで、リラックスできる雰囲気を演出できます。
また照明を柔らかくし、室温や湿度を適切に保つことも大切です。
高齢者が過ごしやすい住環境の改善は、声の頻度や強さにも良い影響を与えることがあります。
2.否定せずに寄り添うコミュニケーションを意識する
「ふんふん」と声を出す高齢者に対して、「うるさい」「やめて」と否定的な言葉をかけることは避けましょう。
本人は気づいていないケースも多く、家族から否定されることで不安や混乱が強まる可能性があります。
「どうしたの?」と優しく問いかけたり、「大丈夫だよ」「一緒にいるよ」など安心感を与えたり、寄り添いを示すような声かけが効果的です。
穏やかに声をかけ寄り添う姿勢が、安心できる関係と信頼感を生み出します。
高齢者とのコミュニケーションは以下の記事を参考にすると、より効果的です。
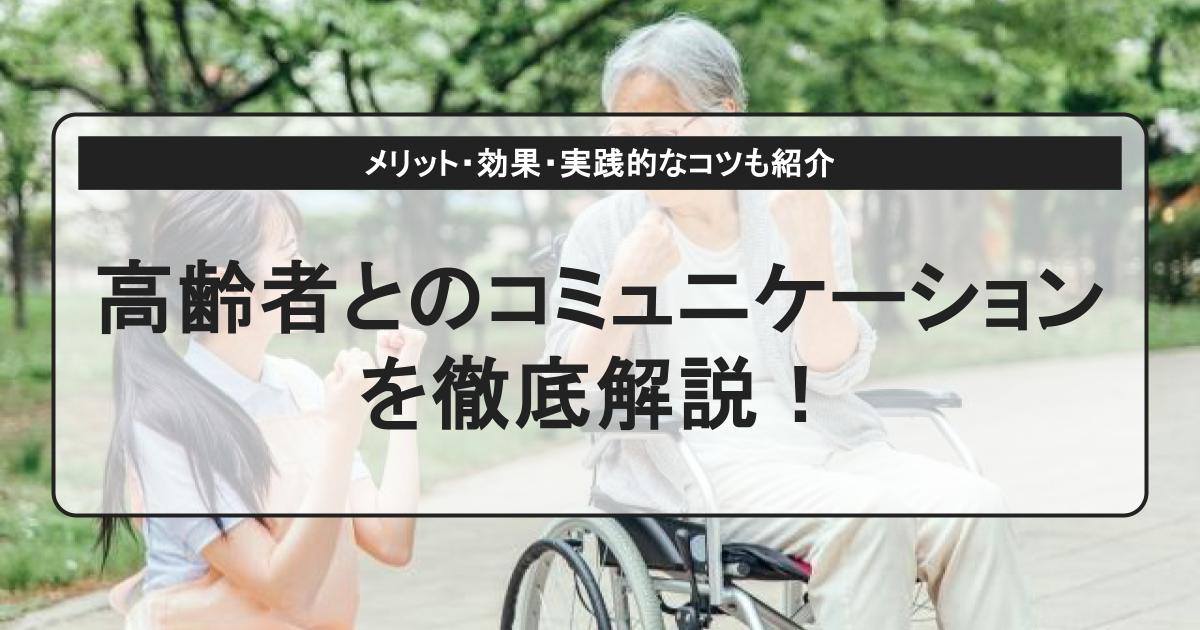
3. 声の頻度や様子の記録を習慣にする
高齢者が「ふんふん」と声を出す頻度や時間帯などの状況を記録することは、原因の把握や医師への相談時に役立ちます。
記録する際は、発声の時間帯(朝・昼・夕方・夜間)や継続時間、声の大きさや種類を記録しましょう。
またその時の状況(食事前後・入浴後など)や、他に気になる症状があるかどうかも一緒に記録しておくと役立ちます。
「夜間に多い」「食事後に増える」などの傾向が分かれば、より的確な対応が可能になります。
手帳やスマートフォンのメモアプリなど、すぐに記録できて続けやすい方法を選びましょう。
4.高齢者と関わる時間を増やす
高齢者の発する声を「困った行動」ととらえるのではなく、関わるきっかけと捉えると、前向きに対応しやすくなります。
高齢者にとっては、以下のような小さな関わりも心の安定につながるでしょう。
- 声が聞こえたときに話しかける
- 隣に座って手を握る
- お茶の時間を共に過ごす
以下の記事を参考に、自宅でゆっくり親子の時間を過ごしてみてください。
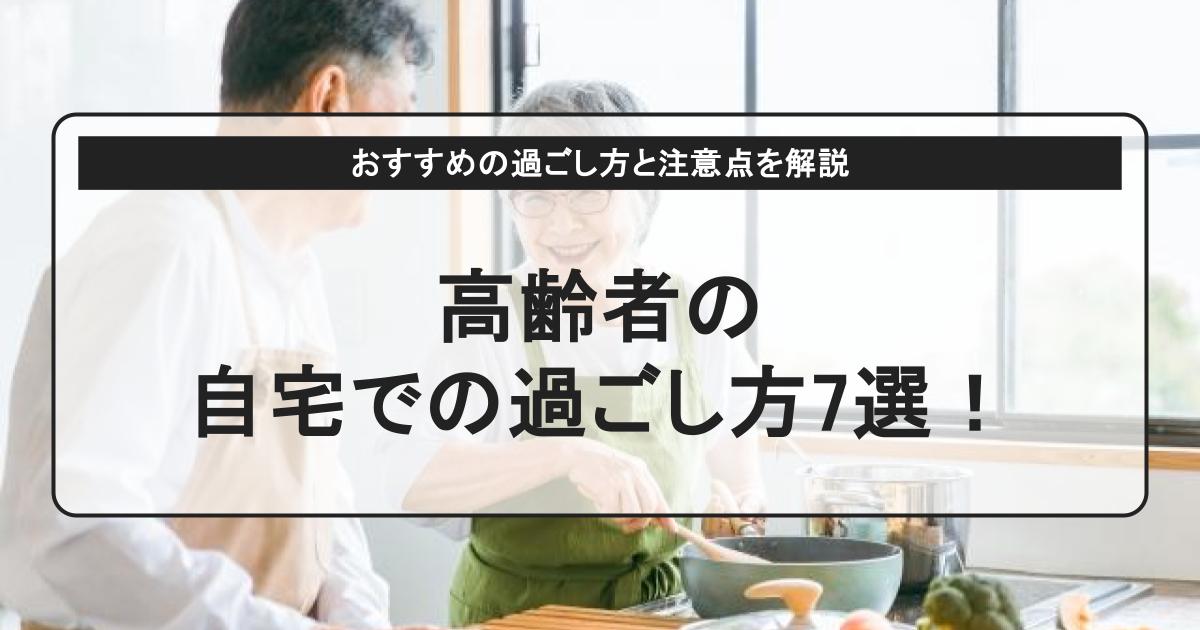
5.自分たち家族の負担軽減に向けた相談の場や支援を活用する
介護を担う家族の負担は、想像以上に大きいものです。
すべてを自分たちで抱え込まず、適切な支援を受けることが大切です。
地域包括支援センターやかかりつけ医、介護相談窓口への相談から始めましょう。
デイサービスや訪問介護、レスパイトケア(一時的な介護代替サービス)などの外部サービスを利用することで、家族が休息を取る時間も確保できます。
家族も支援を受けることは、結果として双方の心身の健康を守れるのです。
地域包括支援センターについての詳細は、以下の記事で解説しているので、あわせて読んでみてください。

「ふんふん」言う高齢者への介護に疲れきる前に家族が知っておくべきこと
高齢者の「ふんふん」という声にをはじめとする日々の対応の中で、家族が疲れてしまうのは自然なことです。
介護に疲れ切る前に、家族が知っておくべきことを紹介します。
「完璧でなくても良い」という心構え
介護は一人ひとり条件が異なるため、正解はありません。
その日その日でできることをするだけで十分です。
完璧を求めすぎず「今日はこれだけできた」と、小さな成果を認める心構えで過ごしましょう。
一人で抱え込まないことの重要性
「家族だから」「親だから」と一人で責任を背負う必要はありません。
支援を受けることは決して甘えではなく、より良い介護を継続するための賢明な選択です。
自分自身の健康管理
介護者自身の健康管理も重要です。
定期的な休息・適度な運動・バランスの取れた食事を心がけましょう。
自分が健康でいることが、結果的に被介護者のためにもなります。
周囲と連携して「自分も大切にする介護」を意識しましょう。
心にゆとりが生まれれば、本人との関係もより良いものになります。
介護と仕事の両立につらさを感じている方は、以下の記事も参考にしてください。
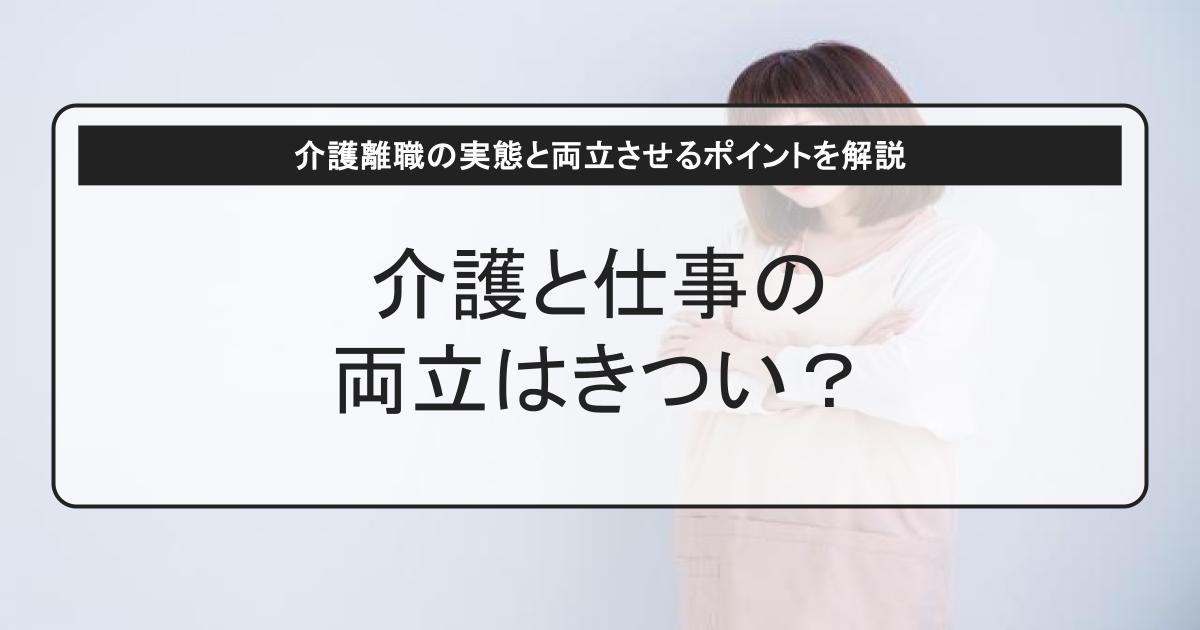
「ふんふん」言う高齢者には生活の様子をよく観察しておきましょう
高齢者が「ふんふん」と声を出す行動には、さまざまな原因が考えられます。
加齢による自然な変化から、認知症やせん妄、心理的要因にいたるまで幅広い可能性があります。
大切なのは、否定せずに寄り添い、適切な観察と記録を行うことです。
一人で悩まず、必要に応じて医療機関や支援サービスを活用しましょう。
家族や自分自身の負担を軽くしながら、温かいケアを継続していくことが大切です。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









