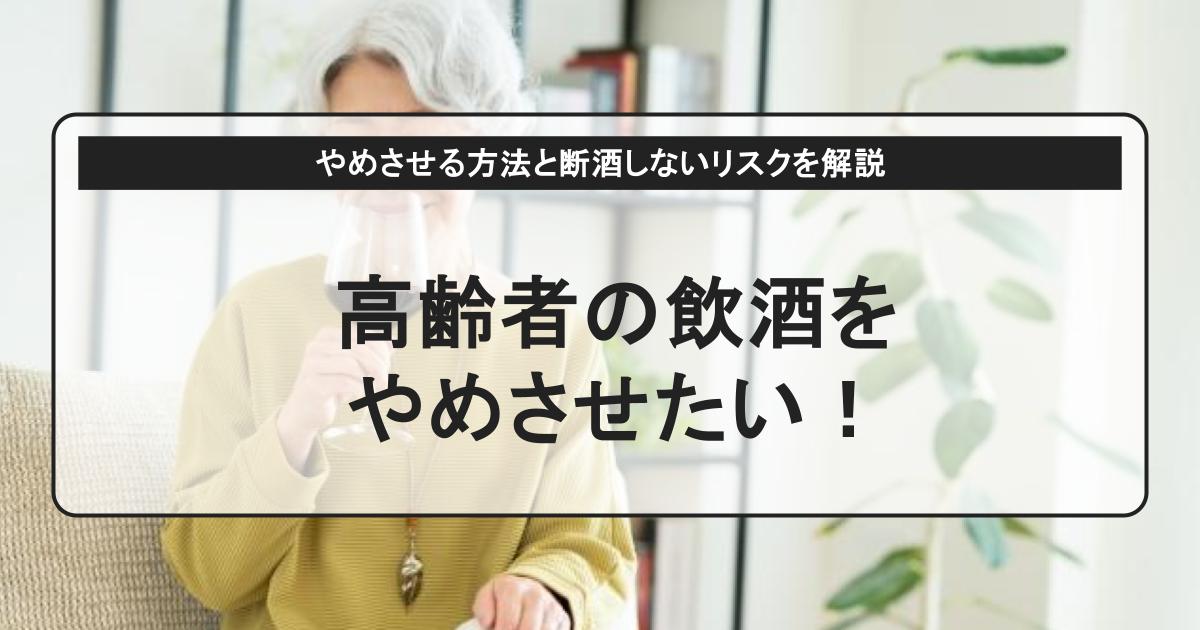「高齢者の飲酒をやめさせたい!」
「高齢者が飲酒を続けるリスクは?」
上記のように、高齢者が飲酒を続けることを不安に感じている方も多いでしょう。
高齢者が飲酒を続けることで、怪我をしやすくなったり、認知機能が低下したりするなど、さまざまなリスクが伴います。
本記事では、高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法について詳しく解説していきます。
また、高齢者が飲酒を続けるリスクも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者が飲酒を続けるリスク5つ
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法を紹介する前に、飲酒を続けるリスクについて理解しておきましょう。
高齢者が飲酒を続けるリスクは、以下の5つが挙げられます。
- 転倒・骨折しやすくなる
- 病気にかかりやすくなる
- 認知機能が低下する
- 家族や周囲の方に迷惑がかかる
- 経済的な負担が増える
リスクを理解しておけば、高齢者を断酒させることがいかに重要かを理解できます。
また、高齢者の飲酒をやめさせる際に、説得材料として使用することも可能です。
転倒・骨折しやすくなる
高齢者が飲酒を続けるリスクの1つ目は、転倒・骨折しやすくなる点です。
アルコールは中枢神経に作用して、バランス感覚を低下させてしまいます。
高齢者は、加齢が原因で筋肉量が減少しているため、転倒リスクが高まります。
さらに、骨密度が低下している高齢者も多いため、転倒時に骨折をして大腿骨頸部骨折や脊椎圧迫骨折など、重大な怪我につながる可能性が非常に高いです。
また、判断力の低下によって、危険な場所での行動が増えるケースも少なくありません。
特に飲酒によって排尿頻度が増加している場合は、夜にトイレへ向かう最中で転倒する可能性があります。
そのほか、自転車で出かける機会が多い高齢者も転倒や骨折のリスクが高まります。
自転車は軽車両として扱われ、飲酒した高齢者が乗ると、飲酒運転になる点にも注意が必要です。
自転車に乗ることをやめて欲しい場合は、以下の記事も参考にしてください。
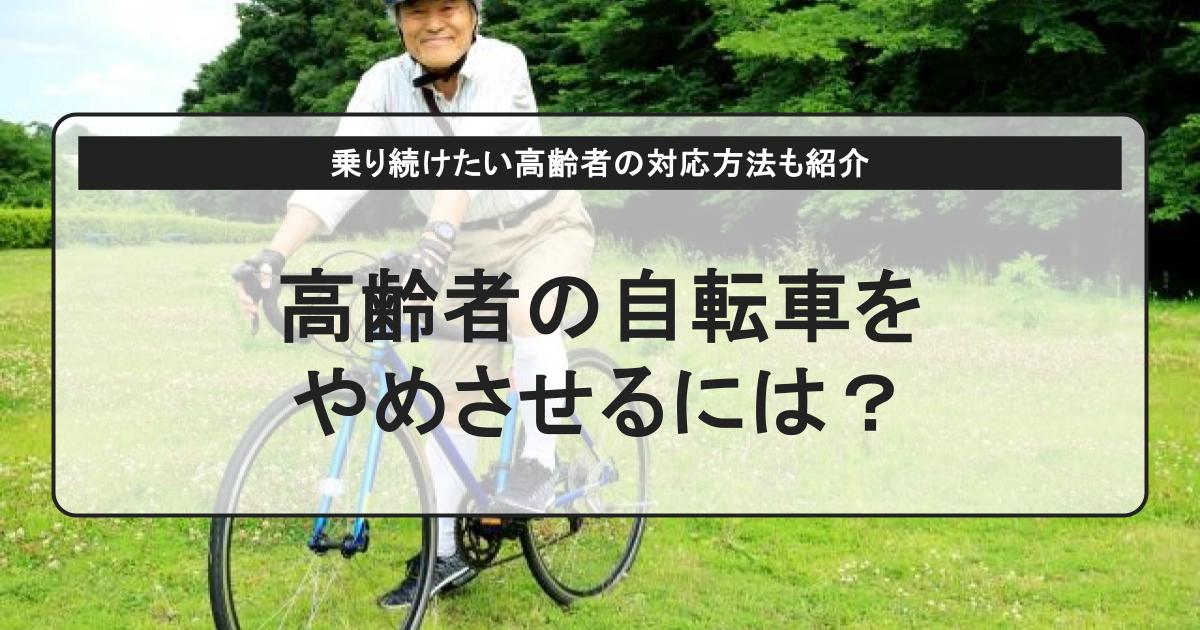
病気にかかりやすくなる
高齢者が飲酒を続けるリスクの2つ目は、病気にかかりやすくなることです。
長期間の飲酒は、免疫システムの機能を低下させて、感染症などへの抵抗力を弱めてしまう恐れがあります。
免疫機能の低下は、アルコールが原因で白血球の機能が阻害されることが原因です。
免疫機能が低下した状態では、肺炎・尿路感染症・皮膚感染症などの罹患リスクが増加します。
さらに、肝臓への慢性的な負担によって、アルコール性肝炎・肝硬変・肝がんなどに発展する可能性も増えてしまいます。
そのほか、以下のように消化器系や心血管系の疾患への影響も大きいです。
- 胃炎
- 胃潰瘍
- 食道がん
- 膵炎
- 高血圧
- 不整脈
- 心筋症
- 脳卒中
- 心筋梗塞
高齢者が飲酒を続けることでさまざまなリスクが増加する点に注意が必要です。
また、すでに病気に罹患している場合は、症状を悪化させる可能性も考えられます。
認知機能が低下する
高齢者が飲酒を続けるリスクの3つ目は、認知機能が低下する点です。
アルコールは脳細胞に直接的にダメージを与えると言われており、特に記憶・学習に関わる海馬や前頭葉の機能に損傷を与えます。
長期間の飲酒は脳を委縮させてしまい、新しい情報を記憶できなくなったり、判断力や問題解決能力などの機能が低下したりします。
物忘れや見当識障害などの症状から、人格変化や日常生活動作の困難などに進行していき、アルコール性認知症になるケースも少なくありません。
また、既に認知症に罹患している方の場合、認知機能の低下を加速させてしまいます。
また、アルコールの分解にはビタミンB1が必要になるため、多量の飲酒はビタミンB1の欠乏につながります。
ビタミンB1が不足すると、意識障害や眼球運動障害などの症状が現れる「ウェルニッケ脳症」をはじめとする深刻な病気に発展するため、注意しなければなりません。
家族や周囲の方に迷惑がかかる
高齢者が飲酒を続けるリスクの4つ目は、家族や周囲の方に迷惑がかかる点です。
過度な飲酒による性格の変化や暴言、暴力行為などは、家族関係を悪化させてしまう恐れがあります。
例えば、飲酒が原因の異常行動や徘徊が原因で、家族や配偶者などが24時間の見守りを強いられてしまい、睡眠不足や精神的な疲労が蓄積します。
さらに、近隣住民への迷惑行為・深夜の騒音・不適切な外出などの行動が続くと、地域社会との関係性も悪化しかねません。
飲酒による判断機能の低下により、詐欺に遭うリスクが増加することもあります。
詐欺被害の後始末を家族や周囲の人が行う事態が生じるなど、家族全体の生活の質に大きな悪影響を与えるケースも多いです。
また、高齢者がイライラしているのは、飲酒以外が問題になっていることもあります。
イライラの原因について詳しく解説した以下の記事も参考にしてください。
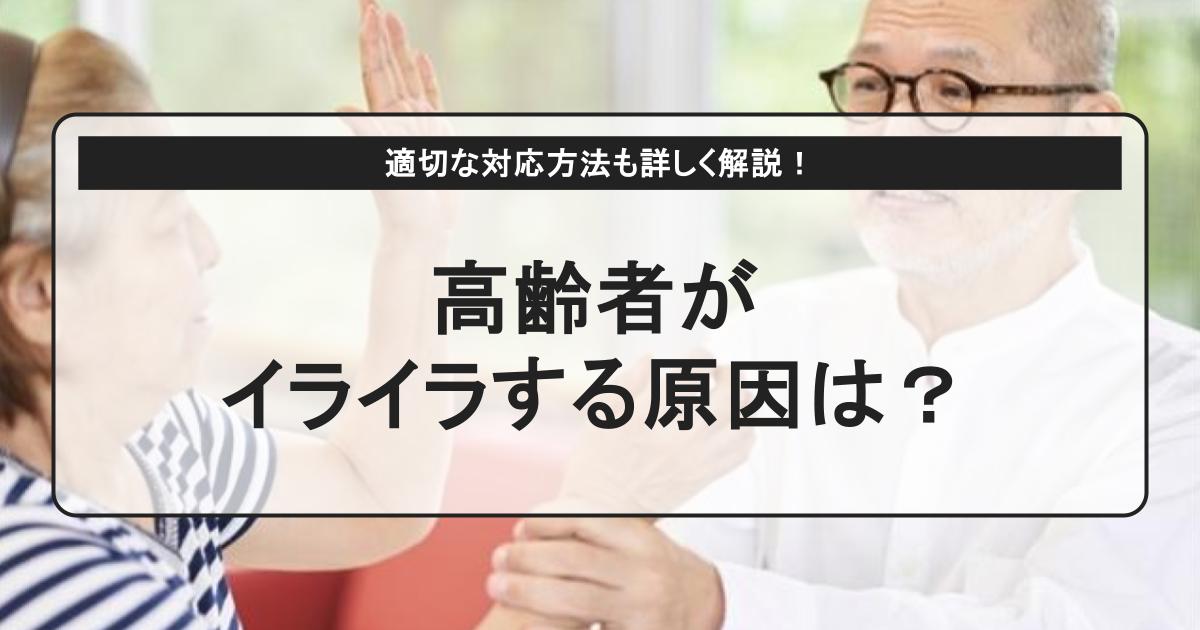
経済的な負担が増える
高齢者が飲酒を続けるリスクの5つ目は、経済的な負担が増えることです。
お酒の種類や飲む量によっても必要な費用は異なりますが、高齢者が飲酒を続けることによる経済的な負担は無視できません。
限られた年金収入の中から生活費だけではなく、飲酒代をまかなうことになると、生活が苦しくなってしまいます。
さらに、高齢者の飲酒による医療費の増加も大きな問題です。
肝疾患・心疾患・消化器疾患などの治療費や入院費用によって、経済的な負担は非常に大きくなります。
そのほか、転倒・骨折リスクも増加するため、手術費用やリハビリにかかる費用も必要になる可能性も高いです。
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法として、以下の3つがあります。
- 飲酒以外の楽しみを見つける
- カウンセリングを活用する
- 医療機関を受診する
いきなり高齢者に断酒を強要すると、抵抗感を感じてしまう場合も多いため、段階的に飲酒をやめてもらうことが重要です。
「自分の力で断酒ができた」という達成感は、高齢者の自己肯定感につながります。
また、高齢者の飲酒をやめさせたい場合は、話し方にも気を付けることが重要です。
以下の記事では、高齢者とのコミュニケーションについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
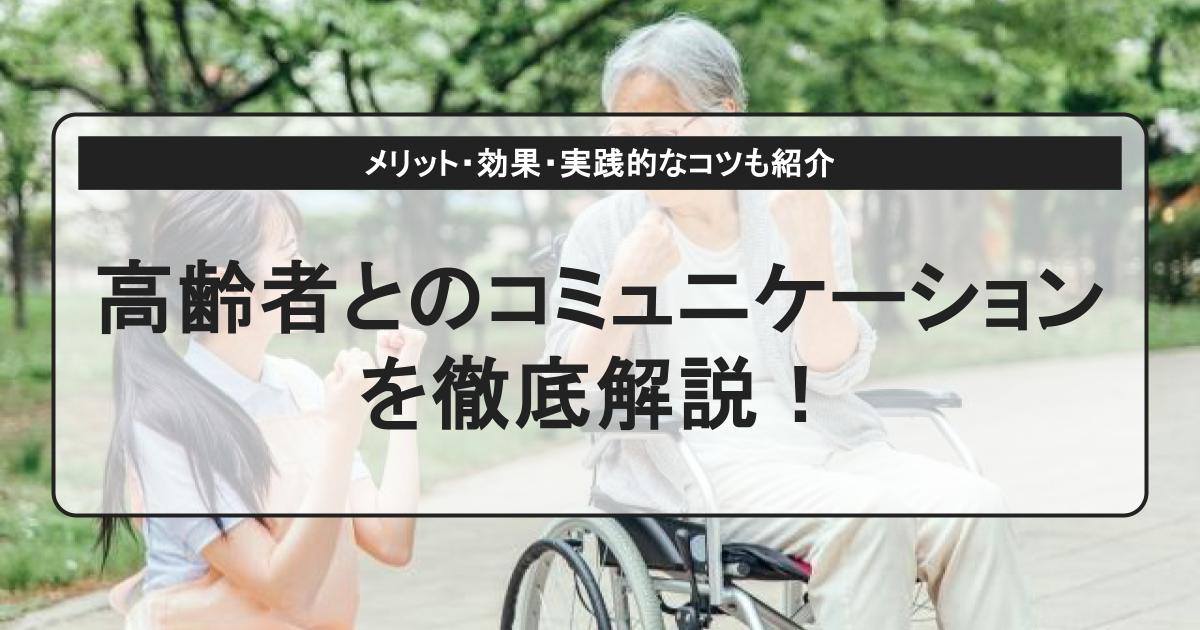
飲酒以外の楽しみを見つける
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法の1つ目は、飲酒以外の楽しみを見つける方法です。
飲酒よりも楽しい活動を見つければ、アルコールがない状態でも充実した日々を過ごせます。
飲酒以外の楽しみとして、趣味を探すことがおすすめです。
園芸・読書・音楽鑑賞などの創造的な活動や、散歩・水泳・ハイキングなどの身体機能を維持する活動も良いでしょう。
身体機能や認知機能の低下を抑えられるだけではなく、達成感や自己肯定感を高めるきっかけにもなります。
また、地域のボランティア活動や老人クラブなどへの参加も検討してみましょう。
社会的なつながりが生まれることで、生きがいになる場合もあります。
そのほか、ペットを飼えば日常の楽しみが生まれたり、お世話をする責任を感じたりすることで、断酒しやすくなるケースも多いです。
趣味を始めたりペットを飼ったりすることを検討している方は、以下の記事も参考にしてください。
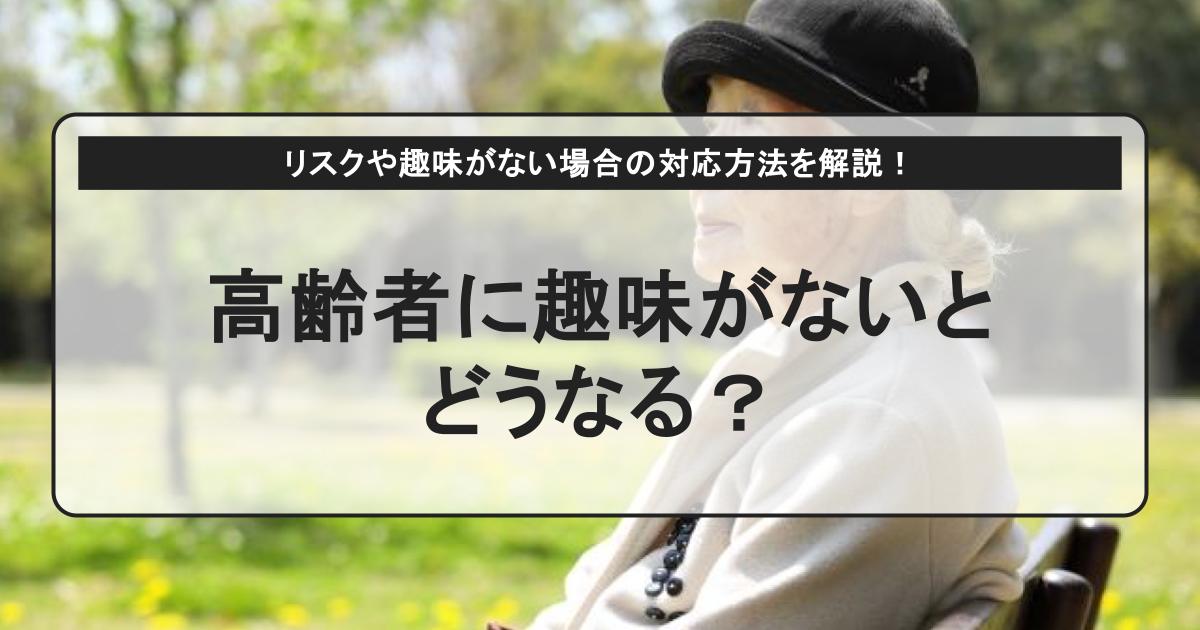

カウンセリングを活用する
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法の2つ目は、カウンセリングを活用することです。
断酒のためのカウンセリングとして、認知行動療法やグループカウンセリングなどがあります。
認知行動療法は、飲酒をしてしまう思考パターンや行動の癖を特定して、より健康的な対処方法を考えていく方法です。
グループカウンセリングでは、断酒に挑戦している高齢者同士で集まり、同じ経験を共有することで「自分だけではない」という安心感を得られます。
周囲の人物に断酒を宣言することで、集団での責任感・連帯感を作り出します。
断酒に向けての進捗状況などを確認し合うことで、モチベーションを維持することが可能です。
高齢者の飲酒をやめさせたいと考えている方は、カウンセリングも積極的に活用していきましょう。
医療機関を受診する
高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法の3つ目は、医療機関を受診することです。
まずは、内科や精神科を受診して、身体的な健康状態を評価してもらいましょう。
肝機能・心機能・認知機能の検査をして、既に生じている健康被害の程度を把握するのが重要です。
状態に応じて、薬物療法を実施したり、すでにアルコール依存症の場合は離脱症状の管理を行ったりします。
また、高齢者は複数の疾患を抱えているケースも多いため、現在服用している薬とアルコールの相互作用リスクも評価しておく必要があります。
通院するだけでは高齢者の断酒が難しい場合、入院治療も可能です。
医療機関で医師や看護師の管理のもと、安全に断酒に挑戦することができます。
高齢者の飲酒をやめさせたいなら別の楽しみを見つけよう!
本記事では、高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法について詳しく解説しました。
高齢者が飲酒を続けるリスクとして、認知機能の低下・経済的負担の増加・周囲の負担増加などさまざまな問題があります。
リスクを避けるためにも、本記事で紹介した「高齢者の飲酒をやめさせたい場合の対応方法」を参考にしながら、適切に対処しましょう。
いきなり医療機関を受診したり、カウンセリングを受けたりすることに抵抗がある場合は、趣味やボランティア活動など飲酒以外の楽しみを見つけることがおすすめです。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら