「高齢者にGPSを持たせるメリットは?」
「高齢の親がある日突然いなくならないか心配」
高齢者にGPSを持たせることは、現在地の把握だけでなく、本人の自立と家族の安心を両立できるツールとして活用できます。
近年、認知症高齢者の増加や自治体の補助制度拡大により、GPS導入のハードルが下がり、日常生活に取り入れやすくなってきました。
たとえば、旅行や買い物などの外出支援、災害時の居場所確認、健康管理などGPSには多彩な活用シーンがあります。
GPSの装着スタイルやレンタル制度も充実しており、本人の尊厳を守りながら利用できる工夫も可能です。
本記事では、高齢者の暮らしをGPSで支えつつ、家族も安心できる環境づくりに役立てる方法を詳しく解説します。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者のGPS活用シーン4選
GPSは位置を追跡するだけでなく、高齢者の暮らしをより豊かにするツールとして活用できます。
ここでは、4つの活用法を紹介します。
1.外出支援になる
高齢者がGPSを使えば、旅行や散歩などの日常の外出を安心しながら、自立した楽しい暮らしを続けられます。
リアルタイムで位置情報を把握できるため、迷子になった場合も家族がすぐに確認でき、迅速に対応可能です。
もし高齢者が買い物中に道に迷っても、スマホアプリで位置を特定できれば、短時間で安全に合流できます。
また、旅行先でも同様に活用でき、離れていても安心です。
高齢者の外出時の不安を減らし、「好きなときに好きな場所へ行く」という本人の自由を守れる点が、GPSを外出支援に取り入れる最大の利点です。
2.健康管理になる
高齢者GPSは歩数や移動距離を自動で記録できるため、日々の健康管理にも役立ちます。
運動量を数字で把握することで、リハビリやウォーキングの成果を実感しやすく、自然に意欲が高まります。
散歩のあとにスマホアプリで歩数や移動距離を確認すると、「昨日より多く歩けた」と達成感を得られるでしょう。
小さな成功体験を積むことで自信にもつながり、リハビリ中の方も回復状況を客観的に確認できて安心です。
見守りだけでなく、運動習慣やリハビリを支える健康管理ツールとしても、高齢者GPSは大きな役割を果たします。
高齢者の運動習慣の目安については、以下の記事で解説しています。
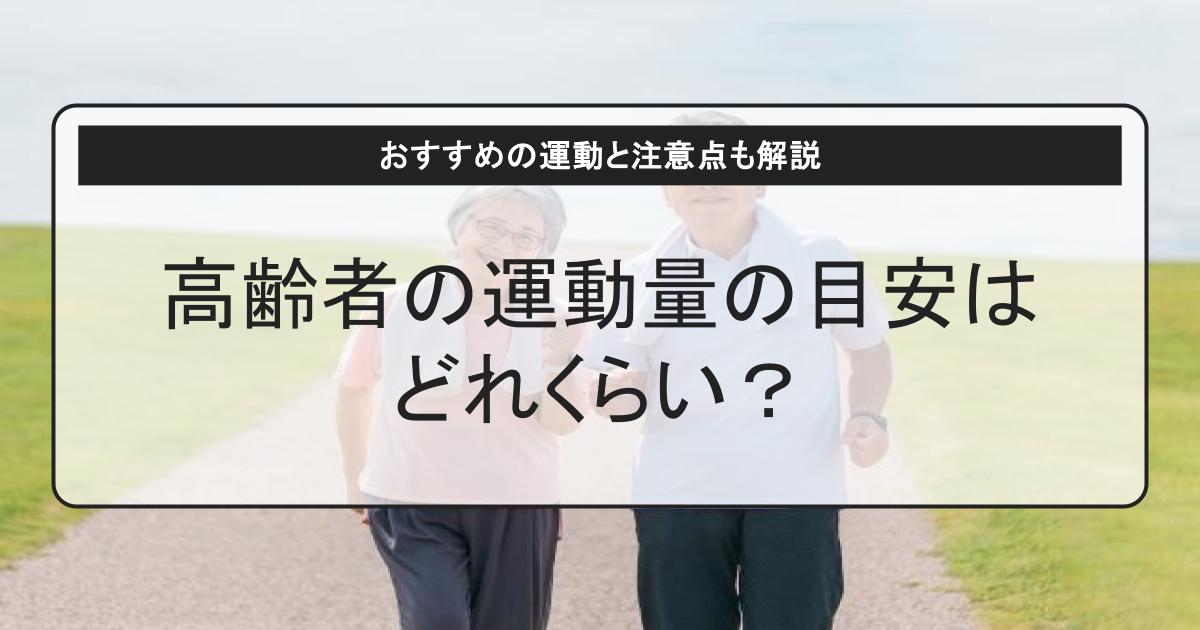
3.災害や緊急時でも安心できる
災害や急な体調不良などの緊急時にも、GPSは高齢者の安心を支えます。
リアルタイムで位置情報を確認できるため、すぐに駆けつけられない場合でも適切に対応できます。
また、地震や豪雨で連絡が取りづらい状況でも、GPSを使えば安全確認がスムーズです。
防災バッグにGPSを常備しておくと、避難時にも役立ちます。
家族が離れていても位置を把握できるGPSは、万一のときも迅速な行動と安心を両立させるでしょう。
4.地域コミュニティと連携できる
GPSは地域コミュニティと連携して高齢者の見守り体制を強化できるのも魅力です。
自治体やボランティアのネットワークとつながることで、行方不明になった場合も高齢者の特徴や位置情報を迅速に共有でき、捜索がスムーズに進みます。
市町村の見守りメール配信サービスと連携すれば、近隣住民へ一斉通知が可能となり地域全体に協力をお願いできます。
家族だけでなく地域全体で支え合える仕組みは、高齢者がGPSを持つ大きな安心材料になるでしょう。
認知症を患う高齢者に徘徊の恐れがある場合は、安全確保のため以下の記事を参考に未然に防いでください。

高齢者が嫌がらないGPSの導入方法
GPSを導入する際、本人の同意がないまま使用すると家族への不信感や気持ちのすれ違いにつながります。
高齢者の尊厳を守りつつ家族の安心を叶えるために、嫌がりにくいGPSの導入方法を3つ紹介します。
1.同意を得るための声かけをする
高齢者が嫌がらずにGPSを受け入れるには、前向きな説明で安心感を与えることが重要です。
「お守り代わり」や「健康管理に役立つ」などポジティブな理由を添えて伝え、抵抗感を減らしましょう。
特に「これがあれば散歩や外出も安心して楽しめるよ」「みんなが安心できるから持っていてくれると助かる」など、本人の自由や家族の思いを尊重した声かけが効果的です。
相手の気持ちに寄り添うことで、高齢者も安心してGPSを受け入れやすくなります。
高齢者とのコミュニケーションが難しいと感じる方は、以下の記事も参考にしましょう。
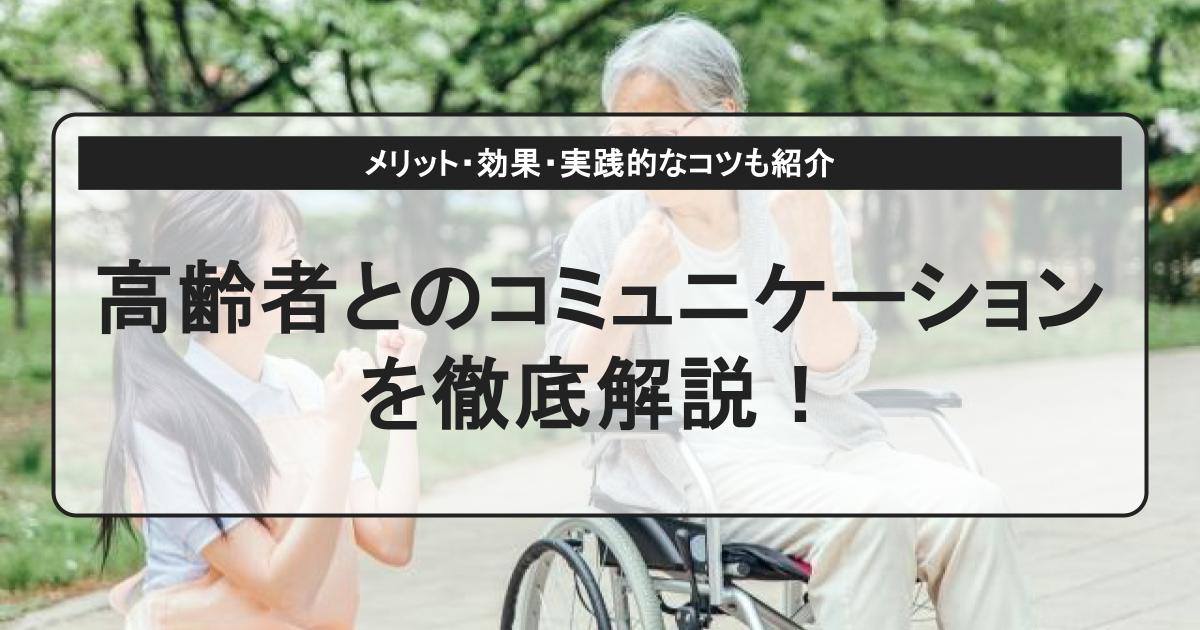
2.装着スタイルを工夫する
GPSにはさまざまな種類があり、抵抗感がある高齢者には、装着スタイルを工夫するのがおすすめです。
アクセサリー型や、靴中敷き型など自然に持てるデザインが好まれやすいでしょう。
いつも愛用しているアイテムに装着すれば、GPSの着け忘れを防げます。
3.お試し期間を活用する
高齢者がGPSを導入する際は、レンタルや短期契約で、使用感や安心感を確かめることも大切です。
GPSを使用時に、装着したアイテムを忘れて出かけたり、外してしまわないかも確認しましょう。
高齢者が慣れるまで家族も一緒に試すと、より安心感や不信感も軽減されます。
GPS導入に向けて調べておきたい3ステップ
スムーズにGPSを導入するために、事前に調べておいた方がいいことや、やっておきたいことを3つ紹介します。
1.1週間の外出と生活パターンの把握する
まずは、高齢者の外出や生活のパターンを把握することが大切です。
高齢者のパターンを理解することで、どの時間帯に外出するかや、よく身に着けるアイテムを把握でき、GPSを効果的に活用できます。
たとえば、いつもの外出時にGPSを忘れそうな日があれば、そのタイミングで声をかけをして持たせることが可能です。
外出や生活の習慣を事前に把握すると、GPS利用の定着と本人の安心につながります。
2.自治体の補助やレンタル情報を調べる
自治体ごとに利用できるGPSの機種や補助内容は異なるため、事前に確認しておくとスムーズに導入できます。
補助制度やレンタル対象のGPSに関する情報を押さえることで、費用や手続きの不安を減らせるでしょう。
たとえば神戸市の場合、GPS端末は3種類から選べ、初期費用と月額利用料の半額を市が負担してくれる制度があります。
まずはお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
3.必要機能を決めて候補を絞る
GPSの必要機能を整理して候補の機種を絞りましょう。
GPS機器には種類が多く、候補が多すぎると本導入までに時間がかかります。
必要な機能やあると便利な機能を事前に決めておくと、比較検討がスムーズに進むでしょう。
使いたい機能を明確にすることで、高齢者に合ったGPSを効率的に選べます。
GPSの選び方については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
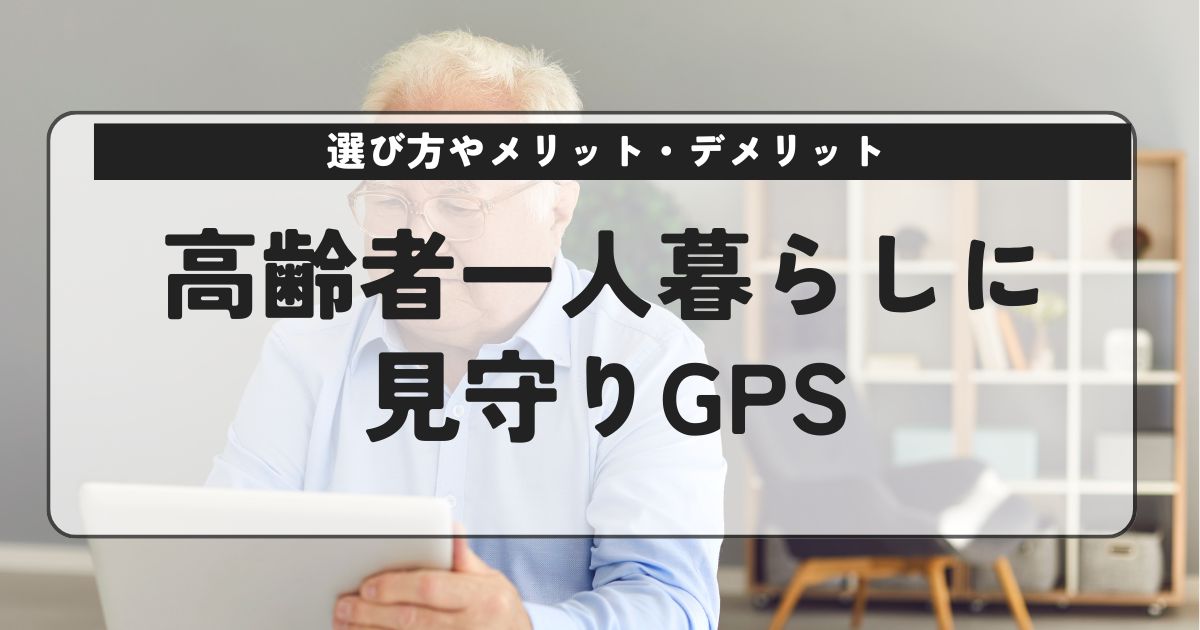
まとめ|高齢者と家族が笑顔で過ごすためのGPS活用
GPSは高齢者の現在地の把握だけでなく、本人の自立支援にも役立ちます。
高齢者と家族の安心を両立させるには、心理面の配慮・コスト・機能のバランスが重要です。
日々の小さな備えに加え、GPSの技術を上手に活用することで、本人らしい暮らしを大切にしつつ、家族も安心できる環境が整えられます。
GPSをうまく取り入れ、高齢者の自立と家族の安心を両立させ、みんなが笑顔で過ごせる生活をサポートしましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









