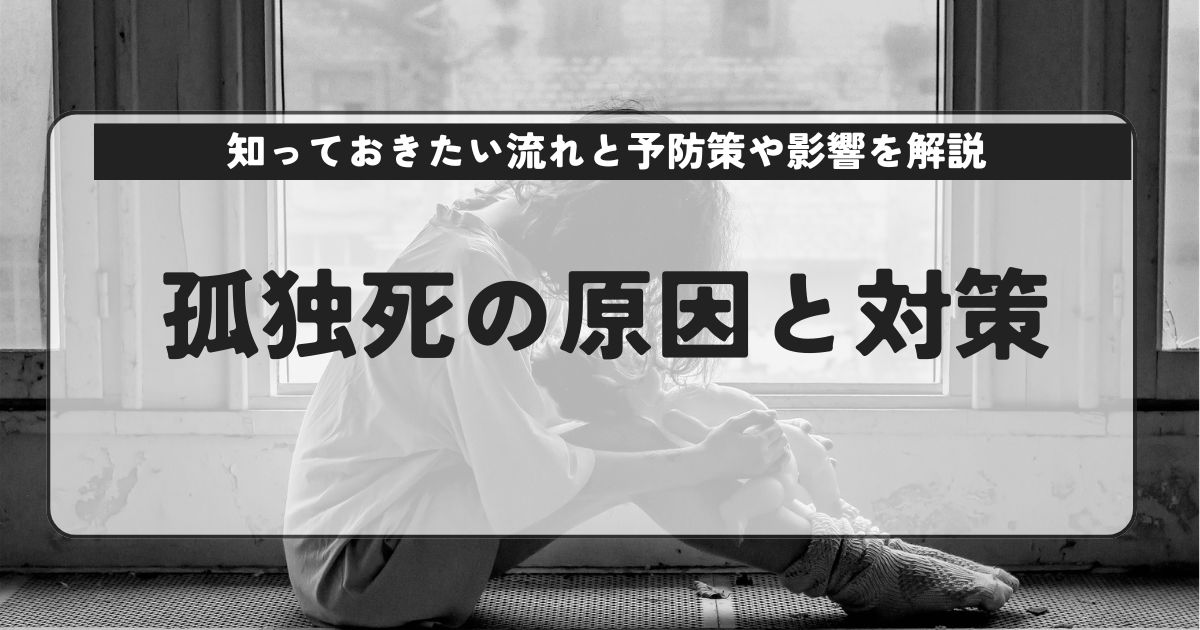孤独死とは、一人暮らしの人が誰にも気づかれずに亡くなることです。
孤独死は、高齢化や社会的孤立などの要因で増加しています。
本人だけでなく、遺族や近隣住民にも大きな影響を与えます。
この記事では、孤独死の原因と対策について、具体的な流れと予防策や影響を解説します。
孤独死を防ぐためには、生活習慣や人間関係を見直すことが大切です。この記事を読むことで、孤独死のリスクを減らし、安心して一人暮らしをする方法を学べます。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら孤独死を引き起こす3つの要因
孤独死に対して、誰にも気づかれずに死ぬという恐怖や悲しみを感じる人が多いでしょう。そこで、孤独死を引き起こす代表的な3つの要因について、詳しく解説します。
- 社会的孤立
- 心身の健康問題
- 経済的困難
これらの要因は、相互に影響し合って、孤独死のリスクを高めます。孤独死の原因を理解することで、状況を見直してみてください。
社会的孤立
社会的孤立とは、家族や友人、地域社会などとの交流が少ない状態を指します。
社会的孤立は孤独感や不安感を増幅させ、心理的なストレスを引き起こすので注意が必要です。また、社会的孤立は健康や生活習慣にも悪影響を及ぼし、病気や事故に対する予防や対処が困難になります。
さらに、その人の存在意義や価値観を見失わせ、生きる意欲を低下させるのです。
心身の健康問題
心身の健康問題とは、精神的な疾患や身体的な障害など、心や身体に異常がある状態を指します。
心身の健康問題は、孤独死の直接的な原因となる場合もあるので注意が必要です。心身の健康問題を抱える人は、自分の状況を理解してくれる人が少ないと感じたり、周囲に迷惑をかけると思ったりして、人との関わりを避ける傾向があります。
また、心身の健康問題を抱えると、自分の能力や自信が低下し、社会的な役割や責任を果たせないと感じることもあるのです。
経済的困難
経済的困難とは、収入が少なく、生活費や医療費などの支払いが困難な状態を指します。経済的困難は、孤独死の直接的な原因となる場合や、社会的孤立を促進する要因です。
経済的困難に陥る人は、自分の生活水準を維持できなくなり、周囲との共通点や話題が減少します。
また経済的困難に陥ることで、自分の貧困を恥じたり他人に頼ることを嫌ったりして、人との交流を断つことがあるのも特徴です。
さらに、自分の将来に対する希望や夢を失い、生きる目的を見出せなくなることがあります。
孤独死の主な原因疾患
孤独死の原因としては、病気や自殺、事故などがありますが、その中でも最も多いのが病気による死亡です。
ここでは孤独死の主な原因疾患として、心臓病・脳卒中・認知症の3つについて、それぞれの症状を紹介します。
心臓病とその症状
心臓病とは、心臓の構造や機能に異常がある状態を指します。心臓病は、虚血性心疾患・心筋症・弁膜症・不整脈などです。心臓病の症状は、種類によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- 胸痛や胸圧感
- 呼吸困難や息切れ
- 動悸やめまい
- 疲労感や倦怠感
- むくみや体重増加
- 発汗や冷や汗
- 吐き気や嘔吐
心臓病は、重篤な場合には心筋梗塞や心不全などを引き起こし、死に至ることがあります。心筋梗塞は、心臓の血管が詰まって心筋に血液が届かなくなることで起こる病気です。心筋梗塞の症状は、激しい胸痛や胸圧感・動悸・呼吸困難・冷や汗・吐き気などです。心不全は、心臓のポンプ機能が低下して血液の循環が悪くなることで起こります。心不全の症状は、呼吸困難や息切れ・むくみ・体重増加・疲労感・倦怠感などです。
脳卒中とその症状
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりして、脳に血液が届かなくなることで起こる病気です。脳卒中には、脳梗塞と脳出血の2種類があります。脳梗塞は、脳の血管が詰まって血流が止まることで起こる病気です。脳出血は、脳の血管が破れて血液が漏れ出すことです。脳卒中の症状は、以下のとおりです。
- 顔の一部がしびれたり、歪んだりする
- 腕や足の一部がしびれたり、動かなくなったりする
- 言葉が出にくくなったり、話すことや理解することが困難になったりする
- 視力が低下したり、視野が欠けたりする
- めまいやふらつき、立ちくらみなどの平衡感覚の障害
- 激しい頭痛や吐き気、嘔吐など
脳卒中は、脳の機能が障害されることで、意識障害・麻痺・失語症・認知症などの後遺症を残すことがあります。また、重篤な場合には死に至ることもあります。
認知症とその症状
認知症とは、脳の機能が低下して、記憶や判断、思考などに障害が生じる病気です。認知症には、アルツハイマー型認知症・脳血管性認知症・レビー小体型認知症などがあります。認知症の症状は、以下のとおりです。
- 物事を忘れたり、繰り返したりする
- 日常生活のことができなくなったり、困難になったりする
- 時間や場所、人物などがわからなくなったり、混乱したりする
- 言葉が出にくくなったり、話すことや理解することが困難になったりする
- 性格や感情が変わったり、不安やうつなどの精神症状が出たりする
- 幻覚や妄想などの錯覚症状が出たりする
認知症は進行性の病気であり、治ることはありません。しかし適切な治療やケアによって、症状の悪化を遅らせたり、生活の質を向上させたりすることができます。認知症は、自分で自分の状態を把握できないことが多く、周囲の人のサポートが必要です。そのため、認知症の人は自分の安全や健康を守ることができないこともあり、孤独死のリスクが高くなります。
孤独死の予防策として心の健康を保つためにできること
孤独死は心身の健康にも関連し、孤独感や不安感、うつ病などの精神的な問題や、心臓病や脳卒中などの身体的な問題で引き起こされることがあります。孤独死を予防するためには心の健康を保つことが重要です。そこで、心の健康を保つためにできることについて解説します。
定期的な運動
運動は、心の健康にとって有効な方法の一つです。運動によって、ストレスホルモンの分泌が抑えられて気分が良くなります。
また、運動によって血液の循環が良くなり、心臓や脳の働きが改善していくのです。さらに免疫力も高まり、病気にかかりにくくなります。
運動は、自宅でできるものや近所でできるもの、スポーツクラブやジムでできるものなど、さまざまな種類があるので選択することが可能です。自分に合った運動を選んで定期的に行ってください。運動は、1日に30分程度、週に3回以上が目安です。
健康的な食事
食事は、心の健康にも影響を与えます。
食事によって、体に必要な栄養素を摂取することが可能です。
栄養素には、体の機能を維持するために必要なものや、神経伝達物質の生成に関係するものなどがあります。神経伝達物質は、脳内で情報伝達を行う物質で、気分や感情にも影響を与えるのが特徴です。
例えばセロトニンは、安心感や幸福感をもたらす神経伝達物質です。ただし、その生成にはトリプトファンというアミノ酸が必要です。トリプトファンは、肉や魚や卵、乳製品や大豆製品などに含まれています。健康的な食事とは、バランスよく、食べ過ぎないことです。
特に野菜や果物、海藻などの食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な食品を積極的に摂るように心がけてください。
ストレス管理
ストレスは、心の健康に悪影響を及ぼす要因の一つです。ストレスは、心臓病や高血圧などの身体的な病気や、うつ病や不安障害などの精神的な病気の原因になることがあります。ストレスは、完全になくすことはできませんが、適切に管理することが可能です。ストレス管理の方法は、人によって異なりますが、以下のようなものがあります。
- 自分の感情を素直に表現する
- 趣味や好きなことに時間を割く
- リラックスできる方法を見つける(音楽を聴く・本を読む・入浴するなど)
- 呼吸法や瞑想法などのリラクゼーション技法を学ぶ
- 心配事や悩み事を人に相談する
- 専門家に相談する
ストレス管理は、心の状態を客観的に把握することから始めるのが大切です。感情や思考に気づき、それがストレスになっているかどうかを判断することができれば、対処法を考えられます。ストレスは溜め込まずに、適度に発散することが重要です。
孤独死の予防策として社会的つながりを築くための方法
孤独死を予防するためには、社会的つながりを築くことが重要です。
社会的つながりを築くことで孤立感や孤独感を減らし、精神的な支えや助け合いを得ることができます。ここでは、社会的つながりを築くための方法を解説しますので、孤独死の予防策として参考にしてください。
地域活動への参加
地域活動とは、自分の住む地域の住民と共に行うさまざまな活動のことです。地域活動には自治会や町内会・老人会・子育て支援・防災訓練・清掃活動・祭りやイベントなどがあります。
地域活動に参加することで、近所の人との交流や信頼関係を深めることが可能です。また地域の問題やニーズに対して、自分の意見や提案を発信したり、協力したりすることができます。地域活動に参加することは、自分の居場所や役割を見つけることにもつながるでしょう。
ボランティア活動
ボランティア活動とは、自分の時間や能力を無償で提供して、社会や他者のために貢献する活動のことです。
ボランティア活動には、福祉や教育、環境や災害、国際協力や人権など、さまざまな分野やテーマがあり、自分の興味や関心に沿った活動を選ぶことが可能です。また、同じ目的や価値観を持つ人との交流や協力を経験することができます。
自分の能力や自信を高めることにもつながりますので、ボランティア活動に参加することも一つの手段です。
趣味やクラブ活動
趣味やクラブ活動とは、自分の好きなことや楽しいことをするために行う活動のことです。
スポーツや音楽、芸術や手芸、読書や映画など、さまざまなジャンルやカテゴリーがあります。趣味やクラブ活動に参加することで、自分の好きなことに没頭したり、スキルや知識を向上させたりすることが可能です。
また、同じ趣味や興味を持つ人との交流や刺激を得ることができます。趣味やクラブ活動に参加して、自分の心や身体をリフレッシュすることも大切です。
孤独死の危険度を高める3つの要素
孤独死とは、社会とのつながりが希薄で、死亡後に長期間発見されないことを指します。孤孤独死の危険度を高める3つの要素は、以下のとおりです。
- 高齢化
- 家族構造の変化
- 社会的なつながりの欠如
高齢化
日本は、世界でも有数の高齢化社会です。高齢化は、孤独死の危険度を高める要因の一つと言われています。高齢になると、身体的な衰えや病気により、自立した生活が困難です。
また、配偶者や友人などとの死別や離別により、孤立感や孤独感を抱くことがあります。高齢者の中には自宅に引きこもってしまう人や、誰とも話さなくなる人もいるでしょう。これらの状況は、孤独死のリスクを高めることになります。
家族構造の変化
日本の家族構造は近年大きく変化しています。核家族化や少子化により、家族の人数や規模が減少ぎみです。さらに、未婚率や晩婚化も進んでいます。家族構造の変化は、孤独死の危険度を高める要因の一つです。家族の人数や規模が減少すると、高齢者の支えや見守りが不足することがあります。
また未婚や晩婚により、高齢者に子どもや孫がいない場合もあるのです。これらの状況は、高齢者の孤立や孤独を招くことになります。
社会的なつながりの欠如
社会的なつながりとは、地域や職場、趣味やボランティアなどで、他者との交流や協力を行うことです。社会的なつながりは、心の健康や生きがいにとって重要な要素になります。
社会的なつながりの欠如は、孤独死の危険度を高めます。社会的なつながりが欠如すると、心の支えや助け合いを得ることができません。そのため、高齢者や一人暮らしの人が死亡したときには、発見が遅れて孤独死になりやすいのです。
孤独死した人の体はどうなるのか
孤独死をした場合、発見されるまで日にちがかかる場合があります。孤独死した人の体は、発見までにどのように変化していくのでしょうか。
発見されるまでの時間や遺体の状態、遺体の処理によって、さまざまな変化を起こします。
発見までの時間
孤独死した人の体は、発見されるまでの時間によって、死後変化の程度が異なります。死後変化とは、死亡した後に起こる体の変化のことで、死斑や硬直、腐敗などのことです。
死斑とは、血液が重力によって体の下側に赤紫色の斑点ができることを指します。死斑は、死後数時間から現れ、数日で消えるのが特徴です。
硬直とは、筋肉の収縮によって体が硬くなることで、死後数時間から始まって数日で解けます。腐敗とは、細菌や酵素の作用によって体が分解されることです。
腐敗は死後数日から進行し、数週間で完了します。孤独死した人の体は、発見までの時間が長いほど、死後変化が進んでいることが多いのです。
遺体の状態
孤独死した人の体は、遺体の状態によって、見た目や臭いなどが異なります。遺体の状態とは死後変化のほかに、死因や季節、温度、湿度などの影響を受けることです。遺体の状態によって、以下のような特徴があります。
遺体の状態は、死因によって外傷や出血、病変などの痕跡が残ることがあります。例えば自殺や事故死の場合、遺体には切り傷や打ち傷、骨折などの外傷が見られることが特徴です。病死の場合、遺体にはがんや肝硬変、心筋梗塞などの病変が見られることがあります。
また、季節によって、遺体の腐敗の速度や虫や動物の被害が異なります。例えば、夏の場合は遺体の腐敗は早く進み、臭いや液体が発生しやすいです。遺体にハエやゴキブリなどの虫や、ネズミやカラスなどの動物が寄ってきて、遺体を食い荒らすことがあります。一方、冬の場合は遺体の腐敗は遅く進み、臭いや液体が発生しにくくなるのです。冬の場合、遺体は虫や動物の被害が少なくなります。
さらに、温度や湿度によって、遺体の腐敗の速度や乾燥やカビの発生が異なります。例えば、温度が高くて湿度が高い場合は遺体の腐敗は早く進み、臭いや液体が発生しやすいです。また温度が高くて湿度が高い場合、遺体にはカビが発生しやすくなります。一方、温度が低くて湿度が低い場合は遺体の腐敗は遅く進み、臭いや液体が発生しにくくなるのが特徴です。温度が低くて湿度が低い場合、遺体は乾燥してしまうこともあります。
遺体の処理
孤独死した人の体は、遺体の処理によって埋葬や火葬などの方法が決まります。遺体の処理とは、遺体を発見した後に行う手続きや作業のことです。遺体の処理には、遺体の確認・搬送・埋葬や火葬があります。
遺体の確認では、遺体を発見した場合、まずは警察に通報することが必要です。警察は、遺体の身元や死因、死亡時刻などを調べます。遺体の身元が分かる場合は、遺族に連絡します。遺体の身元が分からない場合は、指紋や歯型、DNAなどを調べて、身元を特定します。
遺体の確認が終わったら、遺体を搬送します。遺体の搬送は、遺族の希望や遺体の状態によって異なります。遺族の希望がある場合は、遺体を葬儀社や斎場などに搬送します。遺族の希望がない場合や遺族がいない場合は、遺体を監察医務院や市区町村の施設などに搬送します。
遺体の搬送が終わったら、遺体を埋葬や火葬にします。遺体の埋葬や火葬は、遺族の希望や宗教や文化によって異なります。遺族の希望がある場合は、遺体を葬儀や法要などによって埋葬や火葬にすることが可能です。遺族の希望がない場合や遺族がいない場合は、遺体を無縁仏として埋葬や火葬にします。
孤独死と心の病の関係
孤独死は、心の病と深い関係があります。孤独によって、うつ病や統合失調症などの精神疾患のリスクが高まります。
また心の病によって、社会的なつながりが失われ、孤独死に至る可能性が高くなります。
うつ病と孤独死
うつ病とは、気分が落ち込んだりやる気がなくなったりする病気で、孤独死の原因の一つです。うつ病になると、自分の価値や意味を見失って、生きる希望がなくなります。自分に自信がなくなり、何をしても楽しくないと感じるのが症状です。また、周囲の人とのコミュニケーションが減少し、孤立することがあります。そのため人と話すのが億劫になったり、人間関係に悩んだりします。
うつ病の人が一人暮らしをしていると、自殺や事故などで亡くなってしまうことがあります。自殺は、うつ病の最も重大な合併症です。うつ病の発症件数は、コロナ禍で増加しています。新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言などによって、人との接触が減り、不安やストレスが増えました。孤独感は、うつ病の発症や自殺念慮に強い影響を与えています 。孤独感は心の健康にとって有害な要因です。
うつ病と孤独死を防ぐためには、早期発見と適切な治療が重要です。うつ病の症状に気づいたら、医療機関に相談しましょう。うつ病は、放置すると悪化する可能性があります。医師やカウンセラーなどの専門家から、薬物療法や心理療法などの治療を受けることができます。治療は個人に合わせて行われます。また家族や友人など、信頼できる人とのコミュニケーションを大切にしてください。人と話すことは、気分を明るくしたり悩みを共有したりすることができます。
孤独感を感じる人は、電話やインターネットなどで相談や支援を受けることができます。孤独死を防ぐためには、社会的なつながりや支えが必要です。孤独死は誰にでも起こりうる現象です。心の健康に注意を払い、周囲の人との関係を大切にしましょう。
認知症と孤独死
認知症とは、記憶や判断力などの認知機能が低下する病気です。認知症も孤独死の原因の一つです。認知症になると、自分の生活を管理することが困難になります。また周囲の人とのコミュニケーションが減少し、孤立することがあります。認知症の人が一人暮らしをしていると、病気や食事不足などで亡くなってしまうことがあります。認知症の発症件数は、高齢化に伴って増加しています。
認知症の予防や早期発見、適切な医療や介護が、孤独死を防ぐために重要です。認知症の予防には、健康的な食生活や運動、脳トレなどが効果的です。認知症の早期発見には、定期的な検査や自己チェックが必要です。認知症の適切な医療や介護には、専門医やケアマネージャーとの連携や、家族や地域のサポートが欠かせません。認知症の人にとって、安心して暮らせる環境や人間関係が、孤独死を防ぐために大切です。
孤独死がもたらす悲劇
孤独死とは、社会とのつながりが希薄で、死亡後に長期間発見されないことを指します。
孤独死は、遺された人々の心身の健康にも悪影響を及ぼします。孤独死がもたらす悲劇には、以下のようなものがあります。
家族への影響
孤独死は、家族にとっても大きなショックや悲しみをもたらします。家族は、孤独死した人との最期の別れや想い出を共有することができません。また家族は、孤独死した人の死因や死亡時刻などの詳細を知ることができない場合があります。
孤独死した人の遺体の状態や処理に直面することになるのです。さらに遺体の状態は、死後変化や虫や動物の被害などによって、損傷や悪臭などの問題が起こることがあります。
遺体の処理では、葬儀や法要などの手続きや費用などが必要です。これらのことは、家族にとって、精神的な苦痛や負担を増やすことになります。
社会への影響
孤独死は、社会にとっても大きな問題や費用をもたらします。
社会は、孤独死した人の身元や死因などの調査や確認を行い、孤独死した人の遺体の搬送や埋葬などの処理も行うことが必要です。
さらに社会は、孤独死した人の遺体の状態や処理に伴う衛生や環境などの問題に対処する必要があります。これらのことは、社会にとって、人的な資源や経済的な費用などを消費することになります。
個人への影響
孤独死は、本人の健康や生活の質が低下していっただけでなく、死後の処理や遺品整理にも困難が伴います。
孤独死は、病気や事故などの突然死が多く、遺言や葬儀の希望などを伝える機会がない場合が多いものです。また孤独死の現場は、遺体の腐敗や虫の発生などで不衛生な状態になっていることが多く、清掃や消毒に費用や時間がかかります。
孤独死は、本人の尊厳や人権を損なうことにもなるのです。
孤独死を防ぐために必要なこと
孤独死とは、社会とのつながりが希薄で、死亡後に長期間発見されないことを指す現象です。
孤独死は、心身の不健康が悪影響を及ぼしたものです。孤独死を防ぐために必要なことは、以下のようなものがあります。
社会的な支援
社会的な支援とは、地域や行政、福祉などの機関や団体から、孤独死の予防や対策に関する情報やサービスを受けることです。社会的な支援を受けることで、孤独死のリスクを低減することができます。提供している社会的な支援は、以下のとおりです。
- 孤独死の予防などに関する情報をパンフレットやウェブサイトなどで提供
- 孤独死の遺体の処理などに関するサービスを電話やメールなどで提供
- 孤独死の見守りなど定期的支援を行う
社会的支援では、孤独死の原因や影響、予防方法などに関する情報をパンフレットやウェブサイトなどで提供することで、孤独死への認識や意識を高めることができます。また孤独死の発見や通報、遺体の処理などに関するサービスを、電話やメールなどで提供します。これにより、孤独死の被害や問題を軽減することができます。さらに、孤独死への見守りや支援が必要です。孤独死の危険にさらされている人やその家族に対して、定期的な訪問や連絡、相談や助言などを行います。これにより、孤独死の予防や回避につなげることができます。
健康管理
健康管理とは、自分の体や心の状態に注意して病気や不調を予防したり、早期に発見したり、治療したりすることです。健康管理を行うことで、孤独死のリスクを低減することができます。健康管理には、以下のようなものがあります。
- 定期的に健診や検査を受ける
- 適切な食事や運動を行う
- 心のケアやリラックスを行う
定期的に健診や検査を受けることで、自分の身体の状態や病気の有無を把握することができます。病気や不調を早期に発見し、治療や予防につなげることが可能です。また適切な食事や運動を行うことで、自分の体の機能や免疫力を維持することができます。これにより、病気や不調を予防したり、回復したりすることが可能です。さらに心のケアやリラックスを行うことで、自分の心の状態やストレスをコントロールすることができます。うつ病や不安障害などの心の病を予防したり、治療したりすることが可能です。
コミュニケーションの重要性
コミュニケーションの重要性とは、人との交流や会話を大切にすることです。コミュニケーションを行うことで、孤独死のリスクを低減することができます。コミュニケーションには、以下のような効果があります。
- 孤独感や孤立感を減らす
- 社会的な支えや助けを得られる
- 自分の存在や状況を伝えられる
コミュニケーションを行うことで、人とのつながりや関係を築くことができます。これにより、孤独感や孤立感が減り、心の健康や生きがいを高めることができます。また、社会的な支えの情報やアドバイス、援助や協力などを得ることができます。これにより、困難や問題に対処することが可能です。さらに、自分の存在や状況を人に伝えることができます。万が一の場合に、早期に発見や救助される可能性が高まるでしょう。
電球型見守りサービスを活用した孤独死予防策を紹介
孤独死は高齢者だけでなく、若者や女性にも増えている社会問題です。また、遺体の損傷や悪臭、住宅の修復などによって、賃貸物件のオーナーや管理会社にも大きな負担がかかります。
孤独死を防ぐためには、入居者の生活状況や安否を定期的に確認することが必要です。ただし、プライバシーの問題やコストの問題などがあります。そこで、電球型見守りサービスを活用した孤独死予防策を紹介します。
電球型見守りサービスとは
電球型見守りサービスとは、通信機能付きの電球「HelloLight」(ハローライト)と、安否確認を行うコールセンターのサービスを組み合わせたサービスです。このサービスを利用するには、以下のような手順があります。
- トイレの電球をHelloLightに交換する
- HelloLightの中にあるSIMカードで、入居者のスマートフォンとペアリングする
- 入居者が設定した間隔に従って、HelloLightが点灯・消灯を検知する
- 点灯・消灯が2日間行われないと、コールセンターに通知が届く
- コールセンターが入居者や緊急連絡先に安否確認を行う
- 応答がない場合はオーナーや管理会社に連絡する
電球型見守りサービスのメリット
電球型見守りサービスには、以下のようなメリットがあります。
- プライバシーを侵害しない
- コストが抑えられる
- 信頼性が高い
電球型見守りサービスは、センサーやカメラなどを設置する必要がなく、入居者のプライバシーを守ることができます。入居者の同意がないとサービスを利用できないため、入居者の意思を尊重することが可能です。電球型見守りサービスは、Wi-Fiや電池などを別途導入する必要がなく、初期費用や月額料金も低価格で利用できます。
また、孤独死の発見が早まることで、遺体の損傷や悪臭、住宅の修復などにかかる費用を抑えることが可能です。さらに、トイレは毎日使用する場所であり、点灯・消灯の検知は入居者の生活状況を反映すると考えられます。コールセンターは24時間体制で安否確認を行い、異常があればすぐに連絡することができます。
電球型見守りサービスは、孤独死の予防に効果的なサービスです。賃貸物件のオーナーや管理会社は、このサービスを導入することで、入居者の安全や満足度を高めるとともに、自身の経営や管理の効率化、リスク軽減につなげることができます。
詳しくは、HelloLightの公式サイトをご覧ください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちらまとめ
孤独死は、社会とのつながりが希薄で、死亡後に長期間発見されないことを指す現象です。
心身の不健康が悪影響を及ぼし、家族や社会にも大きな負担をかけます。孤独死の主な原因は、高齢化や家族構造の変化、社会的なつながりの欠如などです。孤独死の対策には、社会的な支援や健康管理、コミュニケーションの重要性などがあります。
孤独死を防ぐためには、自分自身や周囲の人の生活状況や安否に注意し、必要なら専門家やサービスに相談することが大切です。孤独死は、誰にでも起こりうる現象ですので、孤独死を予防することは、自分や他人の幸せや尊厳を守ることにもつながります。
孤独死に関する知識や意識を高め、孤独死をなくす社会を目指してください。