「そろそろ主人の介護も年齢的にしんどくなってきた…」
「親が老老介護をしているけど、無理していないか心配」
上記のように日本では「老老介護」が増え、誰にとっても他人事ではありません。
核家族化の進行や寿命と健康寿命の差、経済的な理由などを背景に、介護する側・される側の双方が心身ともに追い詰められやすい状況です。
実際に、介護疲れによるうつや体調不良・孤立・経済的困窮が深刻化し、「共倒れ」に至るケースも少なくありません。
本記事では、老老介護の背景や、子世代にできるサポート方法を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら老老介護とは
「老老介護」は、現代の日本の高齢化社会で深刻な課題の一つです。
高齢化の進行に伴い介護を必要とする人だけでなく、介護を担う人も高齢化しているため、老老介護は多くの家庭が直面する課題です。
国民生活基礎調査によると、要介護者とその主な介護者がともに65歳以上の組み合わせは年々増加しており、2022年時点では「65歳以上同士」が63.5%、「75歳以上同士」も35.7%に達しています。
老老介護はすでに特別な状況ではなく、誰にとっても起こり得る状況といえるでしょう。
引用:厚生労働省 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況「IV 介護の状況 」
老老介護が増えている3つの理由
老老介護が増えている背景には、いくつかの社会的な要因があります。
高齢者が増えているだけでなく、家族の在り方や健康の変化、経済状況などが複雑に関係しているのです。
ここでは、老老介護が増加している主な3つの理由を紹介します。
1.核家族化・単身世帯の増加
現在では、都市化や働き方の変化により核家族や単身世帯が急増し、高齢者を支える家族がそばにいない状況が増えています。
65歳以上の高齢者がいる世帯では、夫婦のみの世帯が増加しており、世帯員数の減少に伴って、若い世代や複数人で支え合う予備力も失われつつあります。
さらに、地域や近隣のつながりも希薄になり、昔のような「助け合い」は機能しにくい状況です。
こうした背景から、高齢者を日常的に支える家族や地域の力が不足し、老老介護の課題は一層深刻化しています。
2.寿命と健康寿命の差が広がっている
平均寿命は年々延びていますが、健康寿命(自立して生活できる期間)との間に差があるため、高齢者が要介護状態で過ごす期間は長くなる傾向にあります。
加齢とともに病気や認知症のリスクが高まり、体力や機能が低下する高齢者が増えています。
医療技術の進歩で寿命は延びたものの、自立した生活を続けるのが難しいケースも少なくありません。
結果として、家族や支える側も長期間にわたって介護を担うことが増えています。
3.経済的な理由で外部サービスが使いにくい
介護サービスには自己負担があり、年金収入や貯蓄だけでは支払いが大きな負担となって利用できないケースもあります。
地域によって料金や利用条件に差があり、介護人材の不足や提供体制の限界、施設の入居待機や通所サービスの枠不足なども重なり外部サービスに頼りきれないのが現状です。
老老介護が抱える深刻な3つのリスク
老老介護では、介護する側もされる側も高齢であることから、心身への負担や生活面でのリスクが大きくなります。
ここでは、老老介護が抱える3つの深刻なリスクについて詳しく見ていきましょう。
介護する側・される側が心身ともに疲弊する
老老介護は、介護者自身の健康や生活に深刻な影響が及ぶ恐れがあります。
高齢の介護者は、持病や体力の低下を抱えながら介護を続けており、腰痛や関節痛、慢性疲労などの身体的負担が大きいです。
また、抑うつや燃え尽き症候群といった精神的ストレスも起こりやすく、夜間対応や徘徊への対応、介護回数の増加が重なることで、睡眠障害や疲労の蓄積につながっています。
老老介護は介護される側だけでなく、介護する側の健康や生活の質にも影響を及ぼす深刻な問題です。
高齢者の徘徊対策については、以下の記事をあわせて読んでみてください。

孤立が進み相談先がなくなる
老老介護では、介護が続くことによる外出や交友の機会の減少、地域や近隣とのつながりが希薄化する可能性があるため、介護者が助けを呼びづらく、孤立しやすい環境にあります。
また相談機関の存在を知らなかったり、利用を躊躇(ちゅうちょ)することも少なくありません。
同じ境遇の人と交流する場がないことから、孤独感や閉塞感が強まり、ストレスがさらに増す状況が生まれています。
こうしたことから、老老介護者は社会的に孤立しやすく、精神的・心理的負担が大きくなるという課題があります。
共倒れや介護放棄の危険が高まる
老老介護では、介護者自身が健康や生活を維持できなくなり、双方が支えを失う共倒れのリスクがあります。
疲労や精神的な負担が限界に達し、介護放棄に至る事例も報告されています。
また自殺や事故、孤独死などの深刻なケースが起こることもあり、誰にも気づかれずに見守りが途切れてしまう危険もあります。
老老介護は介護する側・される側の両方に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早い段階から支援や見守り体制を整えることが大切です。
老老介護の子世代ができるサポートとは?
老老介護は、介護者だけでなく子世代のサポートもとても重要になります。
しかし、何をどのように、どの程度サポートしたらいいかわからないと考えている方が多いのではないでしょうか。
「自分に何ができるか?」と迷っている方は、次の方法をぜひ参考にしてください。
親の介護状況を定期的に声かけして確認する
高齢者の変化や異変を早期に把握するには、日常的な観察とコミュニケーションが欠かせません。
具体的には、食欲や歩行、忘れ物などの変化を観察し、定期的な連絡や訪問で様子を確認しましょう。
小さな困りごとや不安を話せる関係を保つことも大切です。
またチェックリストを活用して見逃しを防ぐと、より確実に状況を把握できます。
介護サービスや地域支援の情報を一緒に調べる
高齢者を支援するには、地域包括支援センターや自治体のサービスの積極的な活用も大切です。
まずはサービス一覧を確認し、デイサービスや訪問介護、ショートステイなど利用可能な支援を探しましょう。
さらに、見守りサービスや安否確認サービス、見守りカメラなども検討すると安心です。
他の家庭の成功事例や体験談を参考にすることで、サービスの活用方法や注意点を知ることができます。
見守りカメラを嫌がる場合は、以下の記事を参考にしてください。

また、地域包括支援センターについては、以下の記事で詳しく解説しています。

経済的・精神的な支援を分担する
高齢者の介護を支えるには、金銭的・手続き的・心理的なサポートを組み合わせることが大切です。
具体的には、介護サービス利用費や介護用品購入の補助といった金銭的支援を行い、申請手続きや制度利用の案内などのサポートも可能です。
また親の話し相手や相談相手、休暇取得や定期的な訪問で、介護者の負担を無理なく分散できます。
親が安心できるつながり作りを手助けする
高齢者の孤立を防ぐためには、地域とのつながりや見守り体制、デジタルツールの活用も重要です。
自治会や見守りネットワークへの参加、高齢者サロンや地域活動への参加、見守りサービスや安否確認ネットワークへの登録もサポートできます。
さらに、安否確認アプリやビデオ通話などのデジタルツール導入を手助けすることで、遠方にいる家族も含めた見守りが可能になります。
高齢者におすすめの見守りアプリは、以下の記事で紹介しております。
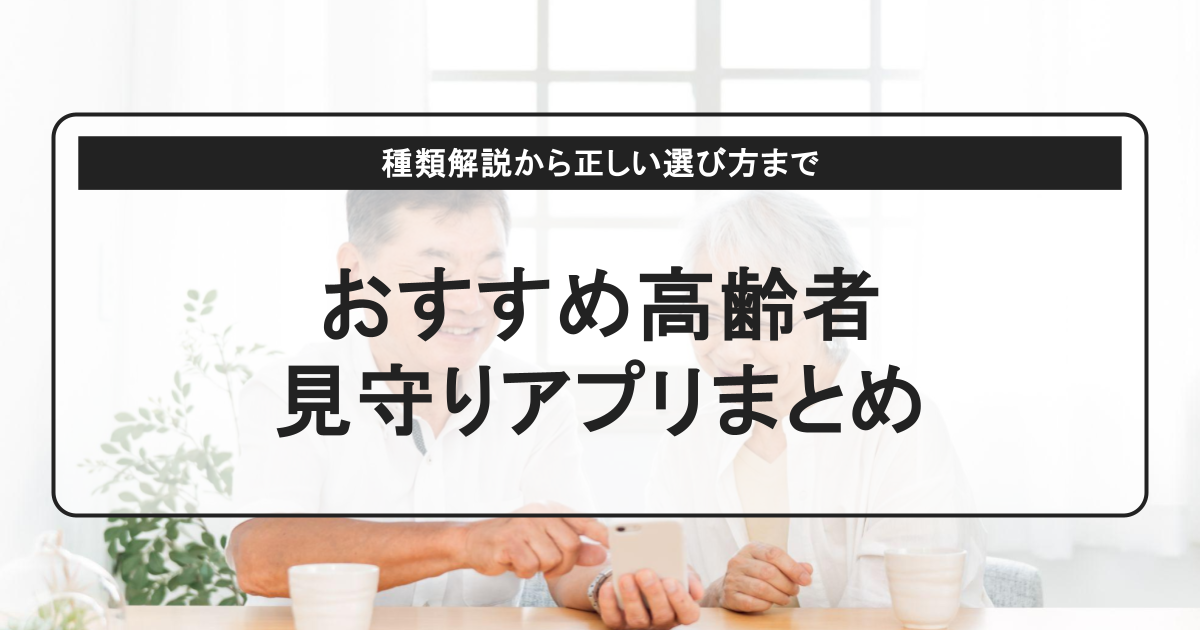
介護の現状と制度を知ることが不安を軽減する第一歩
老老介護は、共倒れや心身疲弊、孤立といったリスクがあるため、漠然とした不安を抱えがちです。
しかし、現状やリスクを正しく理解するだけでも、不安の軽減ができます。
まずは介護制度やサービスの種類、利用条件を知り、外部支援を活用する方法を把握しましょう。
さらに、経済的・精神的サポートの方法や地域ネットワークを知ることで、家族だけで抱え込まず安心感を得られます。
少しずつ情報を集め、老老介護の支援体制を整え、家族も高齢者も安心できる環境づくりを目指しましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









