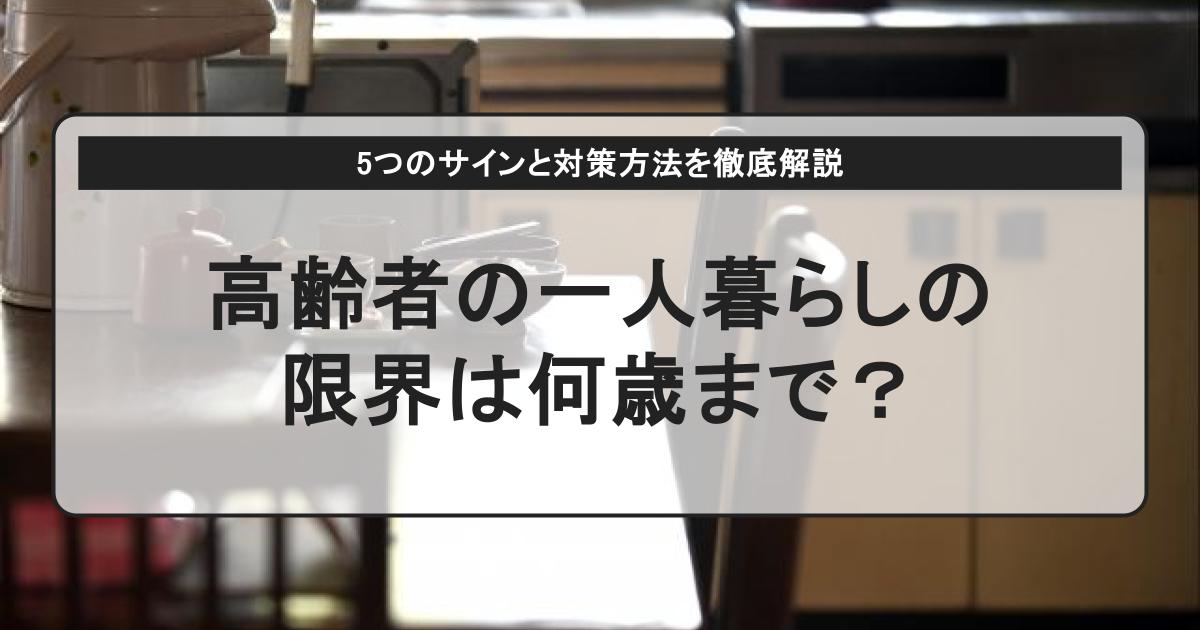「高齢者の一人暮らしの限界はいつ?」
「一人暮らしをそのまま続けることはできる?」
上記のように、高齢者の一人暮らしの限界に関して気になっている方も多いでしょう。
本記事では、高齢者の一人暮らしの限界について詳しく解説していきます。
高齢者の一人暮らしの限界を示す5つのサインや3つの対策方法を紹介します。
また、限界を迎えても一人暮らしを続けたい高齢者に向けて、おすすめのサービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら【年齢】高齢者の一人暮らしの限界は何歳まで?
「高齢者の一人暮らしの限界は何歳まで?」と疑問を抱いている方も多いでしょう。
しかし、結論から伝えると、高齢者の一人暮らしの限界を年齢で線引きすることはできません。
健康状態が良く、体力や認知機能の低下などが見られない場合は、80代以降も一人暮らしを続けている高齢者もいます。
ただし、一般的に後期高齢者と呼ばれる75歳前後の年齢になると、身体機能や判断力の低下が目立ち始めて、一人暮らしが難しくなりやすいです。
実際に厚生労働省の調査でも、要支援・要介護認定を受ける人の割合は75歳以降に急増しています。
高齢者の一人暮らしの限界は、年齢だけで判断できず、体力・認知機能・地域のサポート体制などによって異なります。
「いつが限界なのか知りたい」という方は、高齢者の一人暮らしの限界を見極めるための5つのサインを紹介しているので、そちらをご覧ください。
高齢者の一人暮らしの限界を示す5つのサイン
高齢者の一人暮らしの限界を示す5つのサインを紹介していきます。
- 家事・掃除・買い物などの日常生活が回らなくなる
- 栄養バランスが崩れて体重減少や体調不良が続く
- 転倒や軽い怪我が増える
- 外出や人との交流が減り孤独感が強くなる
- 判断力や記憶力の低下でミスやトラブルが増える
当てはまるものがある場合は、一人暮らしをやめるタイミングかもしれません。
それぞれのサインを詳しく解説していくので、該当するものがないかチェックしてみましょう。
1.家事・掃除・買い物などの日常生活が回らなくなる
高齢者の一人暮らしの限界を示すサインの1つ目は、家事・掃除・買い物などの日常生活が回らなくなることです。
具体的には、以下のような問題点が現れてきます。
- 洗濯物が溜まっている
- 冷蔵庫が空の状態になっている
- 賞味期限が切れた食品が置いてある
- 床にほこりやゴミが放置されている
小さな変化だと思う方も多いですが、積み重なると一人暮らしの安全性や衛生環境が一気に悪化する可能性があります。
特に家事は、体力・記憶力・段取り力が必要な作業です。
そのため加齢によって、認知機能や身体機能が低下すると、家事を実行することができなくなります。
一人暮らしの高齢者が困っていることについて、より詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
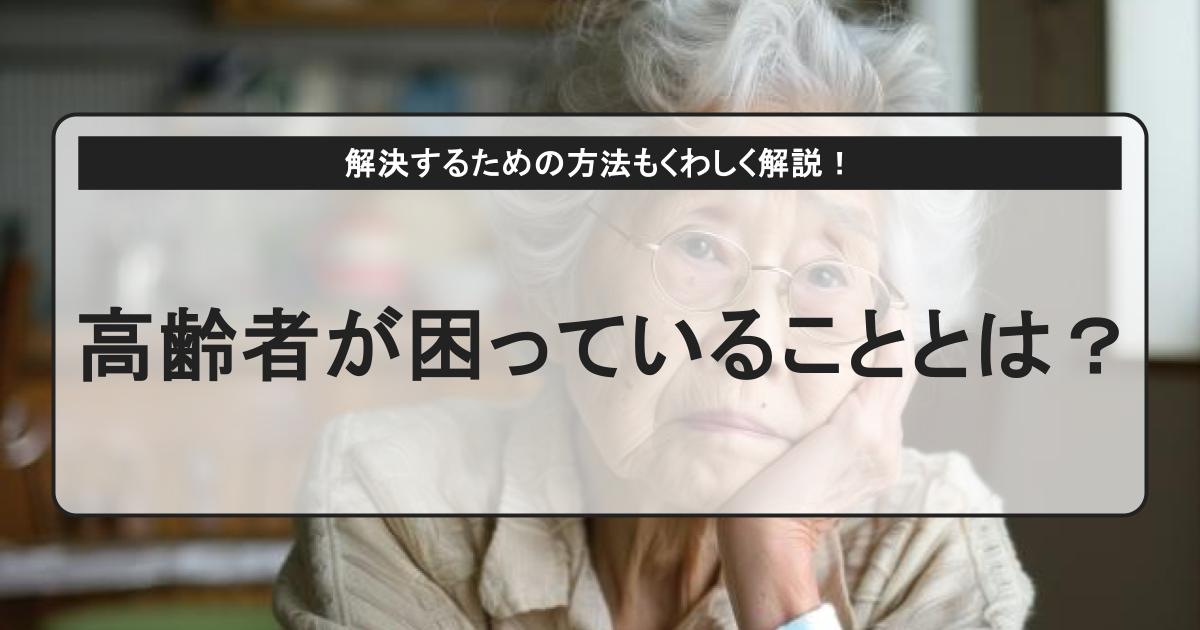
2. 栄養バランスが崩れて体重減少や体調不良が続く
高齢者の一人暮らしの限界を示すサインの2つ目は、栄養バランスが崩れて体重減少や体調不良が続くことです。
加齢による筋力の低下が原因となり、買い物や調理が負担になると、手軽な食品を食べる傾向が高まります。
手軽な食品としてパン・お菓子・インスタント麺などを食べ続けていると、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの重要な栄養素が不足します。
栄養不足によって筋力が低下して疲れやすくなったり、食欲や免疫力の低下を招いたりするのです。
長期間栄養バランスが乱れたままでいると体重減少や体調不良が続いて、高齢者の一人暮らしは限界を迎えます。
3.転倒や軽い怪我が増える
高齢者の一人暮らしの限界を示すサインの3つ目は、転倒や軽い怪我が増えることです。
筋力や骨密度が低下した高齢者は、転倒時に骨折をするリスクが高まっています。
高齢者の骨折は寝たきりの原因になり、一人暮らしが困難になる可能性が高いです。
また、筋力だけではなく、バランス感覚や反射神経の低下によって、ちょっとした段差でつまづきやすくなります。
「つまづくことが増えた」「階段が怖い」などの訴えが増えた場合は、高齢者の一人暮らしの限界を示すサインかもしれません。
4.外出や人との交流が減り孤独感が強くなる
高齢者の一人暮らしの限界を示すサインの4つ目は、外出や人との交流が減り孤独感が強くなることです。
体力だけではなく、気力が低下すると「今日はやめておこう」と外出を先延ばしにするケースが増加します。
また、人との交流が減ると脳への刺激が少なくなり、認知機能の低下を招きやすくなります。
高齢者が「久しぶりに会話ができた」「最近は誰とも会話をしていない」などの発言をしている場合は、要注意です。
人との関わりが減ると、一人暮らしをしている高齢者の体調の変化に気付いてくれる人がいなくなるため、異変を見逃してしまう可能性が高まります。
高齢者が外出しないとどうなるのかについて気になる方は、以下の記事も参考にしてください。
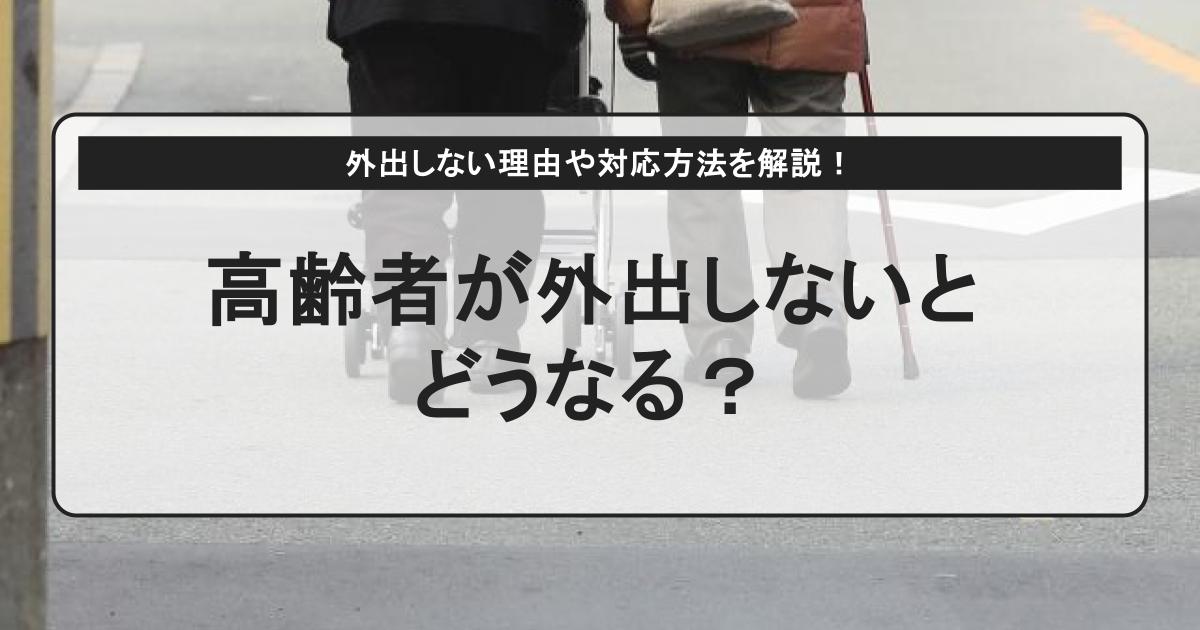
5.判断力や記憶力の低下でミスやトラブルが増える
高齢者の一人暮らしの限界を示すサインの5つ目は、判断力や記憶力の低下でミスやトラブルが増えることです。
具体的には、以下のようなミスやトラブルが挙げられます。
- 公共料金などの支払いを忘れる
- 服薬のタイミングを間違える
- 約束を忘れる
- 詐欺被害に遭う
- 電話で話をした内容を覚えていない
- 以前購入した物と同じ物を購入する
一見すると小さなミスに見えますが、高齢者の一人暮らしを脅かす問題に発展する可能性も否定できません。
記憶力や判断力の低下は脳の処理速度が落ちて、情報の整理や優先順位付けが難しくなることで起こります。
高齢者が一人暮らしをするうえで欠かせない契約・金銭管理・服薬などが難しくなる場合は、一人暮らしの限界を示すサインです。
高齢者の一人暮らしが限界になる前にできる3つの対策
高齢者の一人暮らしが限界を迎える前にできる3つの対策を紹介していきます。
- 生活支援サービスの活用
- 見守り・緊急通報システムの導入
- 定期的な健康チェックと家族・地域とのつながり維持
「一人暮らしの限界が近いかもしれない」と感じている方は、それぞれの対策方法を実践していきましょう。
少しでも長く一人暮らしを続けてもらうためにも、早めに対策を始めることが重要です。
1.生活支援サービスの活用
高齢者の一人暮らしが限界を迎える前にできる対策の1つ目は、生活支援サービスの活用です。
買い物や掃除、料理が難しいと感じたら、早めに生活支援サービスを検討しましょう。
市区町村の高齢者支援センターや民間の家事代行サービスでは、以下のようにさまざまなサポートを受けられます。
- 掃除
- 洗濯
- 調理
- 買い物代行
また、配食サービスを利用すれば、栄養バランスが取れた食事を定期的に受けとることが可能です。
調理や買い物の手間もかからないため、高齢者の一人暮らしを支えてくれます。
2.見守り・緊急通報システムの導入
高齢者の一人暮らしが限界を迎える前にできる対策の2つ目は、見守り・緊急通報システムの導入です。
高齢者が一人暮らしを続けるうえで、転倒や体調不良などの急なトラブルに不安を感じている方も多いでしょう。
安全に一人暮らしを続けるためには、見守りや緊急通報システムの利用がおすすめです。
例えば、自治体が運営する「高齢者見守りネットワーク」や地域包括支援センターの巡回訪問、郵便局・新聞配達員などと連携した地域見守りも効果的です。
また、民間では、人感センサーやドア開閉センサー、体調を検知するウェアラブルデバイスなど、さまざまな見守りシステムが登場しています。
安心して一人暮らしをしてもらうためにも、積極的にサービスを活用していきましょう。
独居老人の見守りサービスを探している方は、以下の記事もご覧ください。

3.定期的な健康チェックと家族・地域とのつながり維持
高齢者の一人暮らしが限界を迎える前にできる対策の3つ目は、定期的な健康チェックと家族や地域とのつながりを維持することです。
一人暮らしでも健康的に過ごすためには、健康診断やかかりつけ医での定期受診などを受けるのがおすすめです。
医療機関に頼りきりになるのではなく、自身で血圧・体重・食事内容などを記録しておけば、体調の変化を早期に発見できます。
また、家族や地域とのつながりを意識的に保つことも重要です。
家族と電話やビデオ通話をしたり、近隣住民への挨拶や趣味のサークルに参加したりするなど、人との交流が孤独感を抑えてくれます。
高齢者が趣味を持たないことによるリスクはさまざまなものがあるため、以下の記事もチェックしておきましょう。
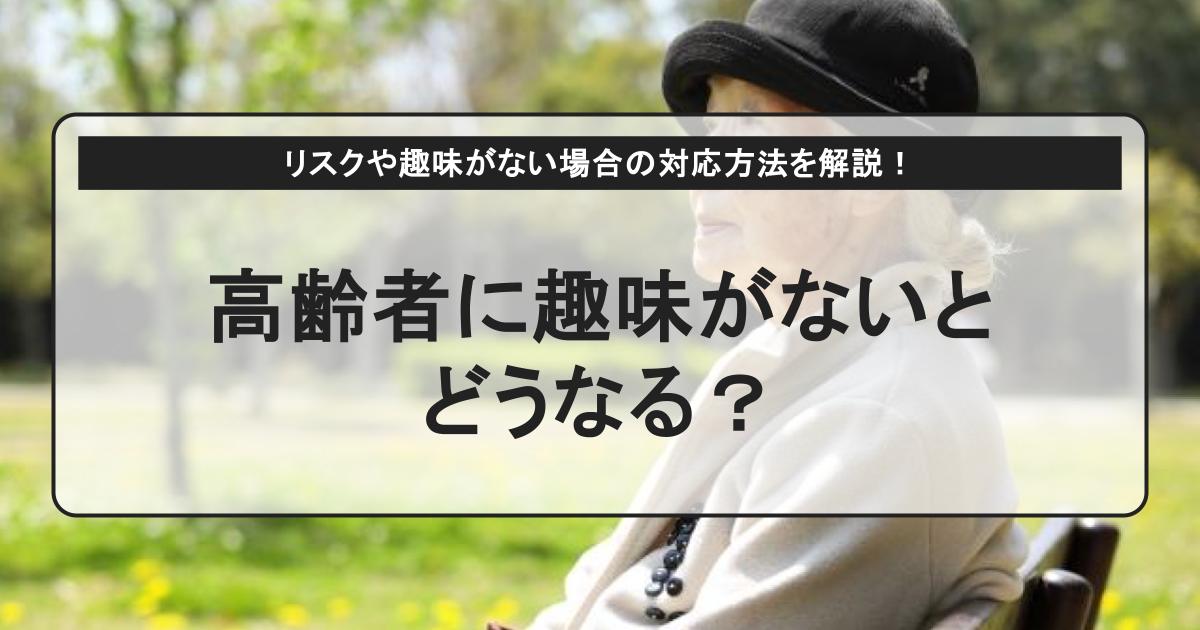
限界でも一人暮らしを続けたい方が利用できるサービス
高齢者の中には、「住み慣れた自宅で過ごしたい」という考えを持っており、一人暮らしの継続を希望している方も多いでしょう。
ここからは、一人暮らしを続けたいという方が利用できるサービスを紹介していきます。
公的な支援制度と民間のサポートという2つのサービスを詳しく解説します。
公的支援制度(介護保険・高齢者向け福祉サービス)
高齢者になっても一人暮らしを続けたい方は、公的な支援制度を活用するのがおすすめです。
介護保険制度を活用すれば、要支援または要介護の認定を受けたうえで、訪問介護やデイサービス、訪問看護などを利用できます。
また、市区町村によっては介護保険の適用外の場合でも、高齢者生活支援サービスや配食・安否確認サービスなどを提供しています。
一人暮らしの高齢者が利用できる公的支援制度は、数多くあるため積極的に活用していきましょう。
どの支援制度が活用できるのか分からないと悩んでいる方は、地域包括支援センターに相談してみることをおすすめします。
生活に関する総合的な相談を受け付けているため、自分に合った制度を見つけることが可能です。
民間のサポート(宅食・家事代行・見守りアプリなど)
高齢者になっても一人暮らしを続けたい方は、民間のサポートの利用を検討してみましょう。
例えば、宅配弁当サービスは、管理栄養士が監修したメニューを定期的に届けてくれるため、崩れがちな栄養バランスを整えてくれます。
家事代行サービスでは、掃除・洗濯・買い物・調理などを必要な分だけ依頼できるため、体力や時間の負担を軽減可能です。
また、スマートフォンや専用の端末を使用した見守りアプリや、通報ボタン付きのアクセサリーなども人気があります。
離れて暮らしていても、一人暮らしの高齢者の安否が確認できるため、活用してみるのがおすすめです。
一人暮らしの見守りサービスを探している方は、以下の記事もご覧ください。
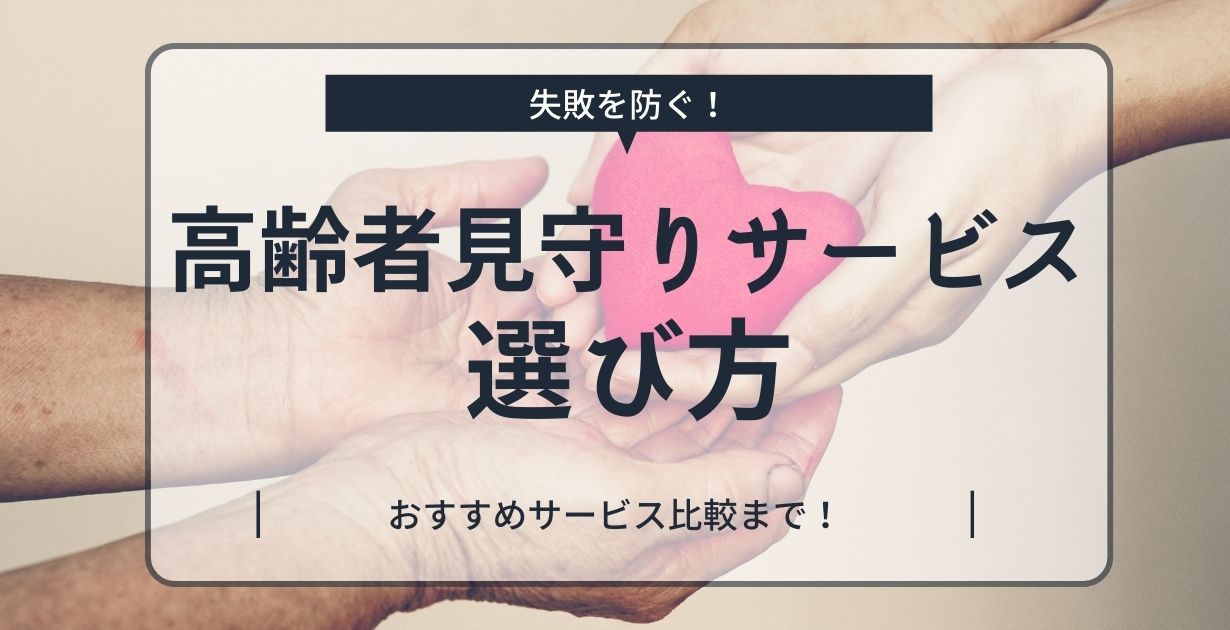
高齢者の一人暮らしの限界のサインに要注意|まとめ
本記事では、高齢者の一人暮らしの限界について詳しく解説しました。
高齢者の一人暮らしの限界は、年齢によって定められるものではなく、健康状態や周囲からのサポートの有無によって変わります。
限界を迎えると重大な事故につながる恐れもあるため、記事内で紹介した「高齢者の一人暮らしの限界のサイン」を見逃さないように注意しましょう。
また、限界を感じていても、公的支援制度や民間のサポートを活用すれば、一人暮らしの期間を延長できます。
一人暮らしの限界を迎える前に、適切な対策を行って、重大な事故を防ぎましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら