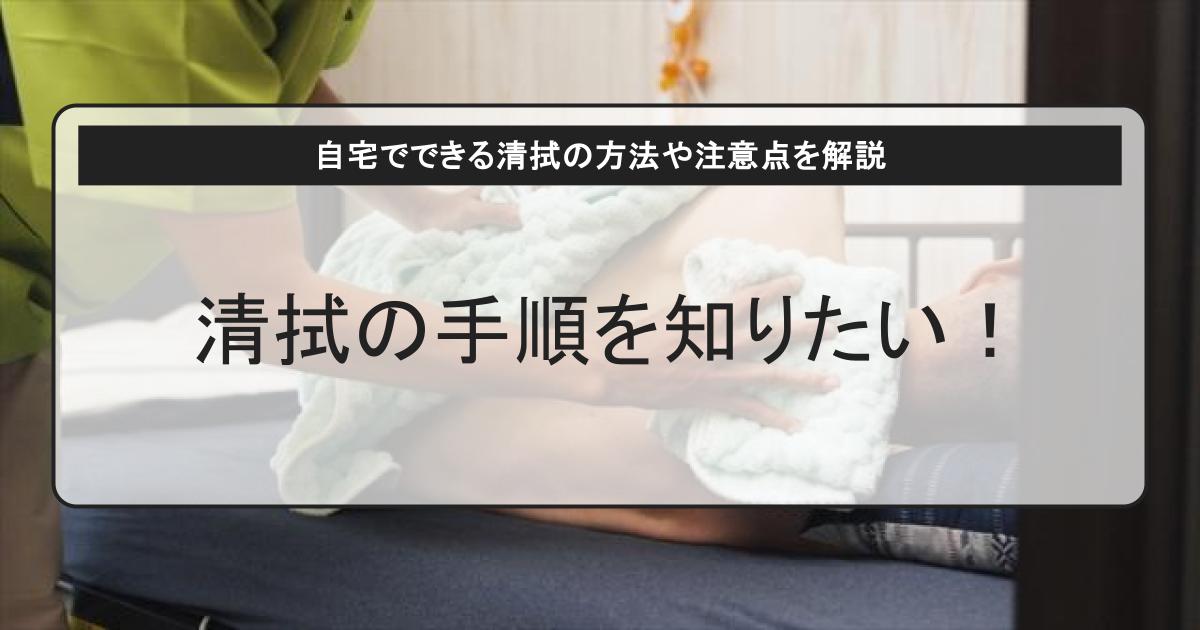「清拭(せいしき)ってどうやればいい?詳しく手順を知りたい」
自宅で高齢の親を介護していると、体調や季節の影響で「毎日お風呂に入れない日」が出てきます。
そんなときに役立つのが「清拭」です。
清拭はお湯に浸からずに体をやさしく拭いて清潔にする方法で、皮膚トラブルの予防や血行促進、リラックス効果も期待できます。
本記事では、家庭でも安全・快適に行える清拭の手順を、準備から注意点、便利アイテムまで解説します。
今日からすぐに始められるポイントも紹介するので、親御さんの清潔と快適を守る日常ケアの参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら清拭の目的と効果
清拭は単なる体を拭く作業ではなく、高齢者の健康や心身の安心に大きく関わるケアです。
皮膚の清潔保持や血行促進だけでなく、心の安らぎや日々の体調チェックにも役立ちます。
ここでは、清拭を行うことで得られる具体的な効果を、4つの観点から紹介します。
皮膚を清潔に保ちトラブルを防ぐ
清拭の目的と効果の一つ目は、皮膚を清潔に保ちトラブルを防ぐことです。
高齢になると、汗や皮脂、古い角質が肌に残りやすくなります。
入浴を控える日が続くと、かゆみや発疹、皮膚炎の原因になることもあるのです。
清拭はこうした汚れをやさしく取り除き、肌を清潔に保つことで、皮膚のトラブルを防ぐ効果があります。
血行を促し体を温める
清拭の目的と効果の二つ目が、血行を促進して体を温めることです。
タオルで体を拭く刺激は、軽いマッサージのように血行を促します。
特に足先や手先など冷えやすい部分を清拭すると、体がじんわり温まり、むくみの軽減にもつながるでしょう。
心をケアしコミュニケーションを深める
清拭を行うことで、心をケアしながらコミュニケーションを深めることができます。
清拭の時間は、介護する人とされる人の大切なふれあいの時間でもあります。
「気持ちいいね」「冷たくない?」と声をかけながら行うことで安心感が生まれ、よりリラックスした時間を過ごせるでしょう。
体調変化に気づくきっかけに
清拭中に肌の乾燥や赤み、床ずれの初期症状などを見つけることができるのも大きな利点です。
日々の清拭は、清潔を保つだけでなく、体調を見守る大切な習慣にもなります。
清拭を行う前の準備
清拭を安全で快適に行うためには、事前の準備がとても重要です。
体調や環境を整え、必要な道具をそろえることで、本人も介護する側も安心して清拭に臨むことができます。
ここでは、清拭前に確認しておきたいポイントや準備の方法について紹介します。
体調と環境を確認
清拭を始める前に、まず確認したいのは体調と室内環境です。
発熱・傷・皮膚の赤みがあるときは、その部分を避けるか、清拭を控えるようにします。
室温は22〜26℃くらいを目安に、寒さを感じないように暖かく整えましょう。
冷えた部屋では、せっかくの清拭が負担になってしまいます。
参考:よくわかる 介護Q&A
準備するもの
必要なものを手の届く範囲にそろえておくと、清拭をスムーズに進められます。
- お湯(40℃前後)
- 清拭タオルまたは清拭用タオル(数枚)
- 洗面器やバケツ
- 乾いたバスタオル(体を覆う用)
- 着替えや下着
- 保湿クリームまたはローション
お湯はぬるすぎると汚れが落ちにくく、熱すぎると肌を刺激する恐れがあります。
手を入れて「少し温かい」と感じるくらいが目安です。
プライバシーと安心への配慮
清拭は肌を露出するケアなので、本人が恥ずかしさを感じないように配慮しましょう。
バスタオルや毛布を体にかけながら、拭く部分だけを少しずつ出すようにしてください。
「ここを拭くね」「少し冷たくない?」と声をかけながら進めると、安心感を与えられます。
安全に行うための工夫
介護する側も無理のない姿勢で行うことが大切です。
ベッドの高さを調整したり、滑りやすい床にはタオルを敷いたりして、安全を確保しましょう。
また、本人が手を動かせる場合は、できる範囲を自分で拭いてもらうと、自立心を保ちやすくなります。
全身の清拭の基本手順
清拭は、体の上から下へ、汚れやすい部分を順番に拭いていくことが基本です。
正しい順序で行うことで、皮膚トラブルの予防や血行促進につながり、介護される方もより快適に感じられます。
ここからは、全身を清拭する際の具体的な手順を段階ごとに解説します。
1.顔・首まわり
最初は顔から始めます。
目や口のまわりなど、デリケートな部分は特にやさしく行いましょう。
目は内側から外側へ向かって拭き、鼻や口のまわりは清潔なタオルで軽く押さえるように汚れを取ります。
そして、耳や首の後ろは汗が溜まりやすいので忘れずに行ってください。
顔を拭き終えたら、乾いたタオルで水分を軽く押さえましょう。
2.上半身(胸・お腹・背中・腕)
次に胸からお腹、腕へと進めます。
胸は心臓のある左側から拭くと、体が少しずつ温まりやすくなります。
お腹は「の」の字を描くように、優しくマッサージするように拭くと便通の促進にも効果的です。
腕は肩から手首にかけて下方向へ拭いていきます。
背中を拭くときは、体を少し横向きにしてもらい、肩甲骨まわりから腰にかけて丁寧に拭きます。
3.下半身(太もも・膝・ふくらはぎ・足先)
下半身は、太ももから足先に向かって拭いていきます。
ひざの裏やふくらはぎは汗をかきやすいので、軽く押さえるようにしながら拭きましょう。
足先は、指の間まで丁寧に行います。
汚れを取った後は乾いたタオルでしっかりと水分を拭き取ると、肌トラブルを防げます。
4.陰部・おしりまわり
最後に、最も汚れやすい陰部やおしりまわりを清潔なタオルで拭きます。
女性は前から後ろへ、男性は陰茎→陰嚢→肛門の順で行うのが基本です。
1回ごとにタオルを変えて衛生的に行いましょう。
排泄後のケアとして清拭を取り入れると、清潔を保つだけでなく感染予防にもつながります。
5.清拭後のケア
全身の清拭が終わったら、乾いたタオルで軽く全身を押さえ、残った水分を取り除きます。
そのあと、乾燥しやすい部分には保湿クリームやローションを塗りましょう。
肌がしっとりすると、かゆみや乾燥を防ぐだけでなく、触れられる心地よさも感じやすくなります。
最後に着替えを済ませ、体が冷えないうちに清拭を終えるのがポイントです。
清拭を行う際の注意点
清拭は高齢者の清潔を守る大切なケアですが、間違った方法で行うと皮膚に負担をかけたり、体調に影響を与えたりすることがあります。
安全で快適に行うには、ちょっとしたコツや注意点を押さえておくことが大切です。
ここでは、清拭を行う際の注意点を紹介します。
優しく拭く
清拭は優しく拭くことが基本です。
強くこすったり、同じ場所を何度も拭いたりすると、皮膚を傷つける原因になります。
特に関節部分やひざ裏、脇の下など、皮膚が柔らかい箇所はやさしく押さえるように拭きましょう。
タオルの使い回しを避ける
清拭では、同じタオルで複数の部位を拭かないことが大切です。
顔用・上半身用・下半身用など、部位ごとにタオルを分けると清潔に保てます。
特に陰部やおしりは最後に専用のタオルを使い、感染予防にも配慮しましょう。
お湯の温度と室温に注意する
お湯が冷めると体が冷えてしまうので、適温(40℃前後)を保つ工夫をしましょう。
また、室温が低いと清拭中に寒さを感じ、体に負担がかかります。
寒い季節は暖房や毛布で体を温かく保つことも大切です。
体調に合わせて無理をしない
発熱や皮膚の炎症、体調不良時には無理に清拭を行わないことも大切です。
清拭は毎日完璧にやる必要はありません。
体調や季節に合わせ、無理のない範囲で続けることが、安心・安全につながります。
コミュニケーションを取りながら行う
コミュニケーションを取りながら行うことも、清拭を行ううえで大切なことです。
「冷たくない?」「ここは気持ちいい?」と声をかけながら拭くと、安心感が増します。
また、拭く順番を本人に伝えたり、手伝ってもらったりすると、自立心を保ちながら清拭ができます。
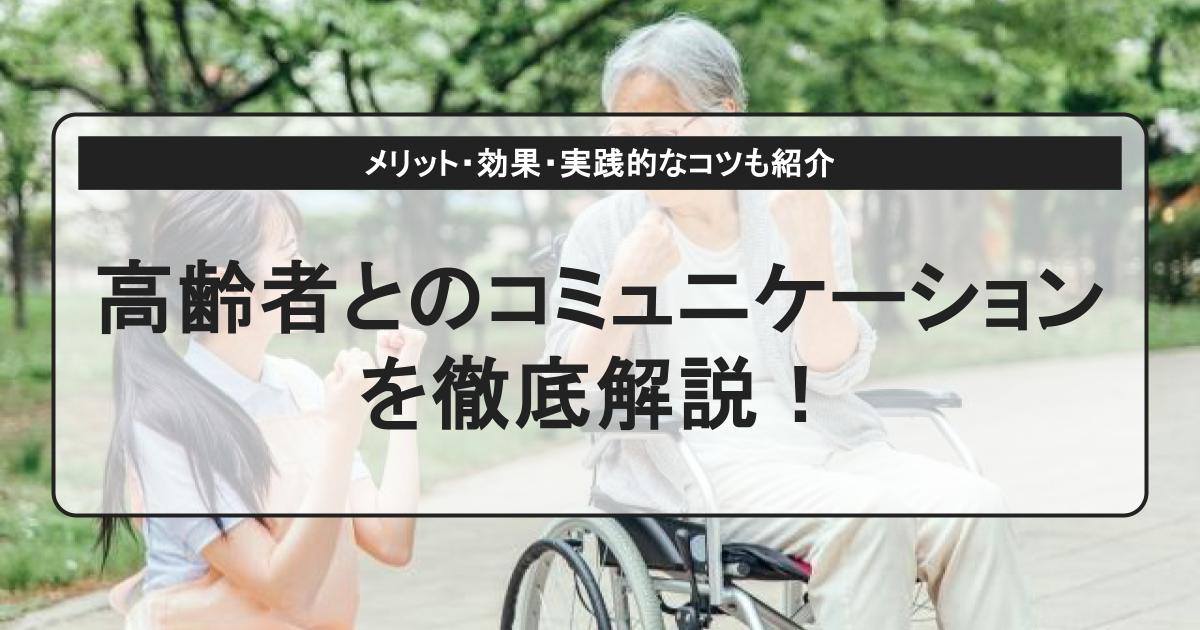
季節ごとに工夫する
季節ごとの工夫も大切です。
冬場は室温を上げ、タオルを温めてから使うことで、清拭中の冷えを防げます。
一方、夏場は汗をかきやすい部位をこまめに拭くことで、湿疹やかゆみの予防につながります。
また、湿度が低い季節は肌が乾燥しやすいため、保湿を念入りに行うことが皮膚トラブルの防止に効果的です。
使える便利アイテム・清拭シートの紹介
清拭をより快適に安全に行うためには、便利なアイテムを活用するのがおすすめです。
忙しい日や体調が優れない日でも、手軽に全身を清潔に保つことができます。
使い捨て清拭シート
お湯を用意せずにすぐ使える使い捨ての清拭シートは、時間や手間を大幅に省けるのが魅力です。
保湿成分入りのタイプなら、拭いたあとも肌がしっとりし、乾燥やかゆみを防ぐことができます。
また、顔用や体用に分かれたシートを使うことで、衛生的に清拭を行えます。
介護用清拭タオル
介護用の清拭タオルは、柔らかく吸水性の高い素材で作られており、肌に負担をかけずに全身を心地よく清拭できます。
洗濯して繰り返し使えるタイプであれば、経済的にも負担が少なく、家庭で長く活用できます。
入手方法と使い方のポイント
これらのアイテムは、介護用品店やドラッグストア、ネット通販などで手軽に手に入ります。
初めて使用する場合は、家族で一度試して、肌への刺激や使いやすさを確認しておくと安心です。
便利なアイテムを上手に取り入れることで、清拭の負担を減らしながら、親御さんの清潔と快適を守ることができます。
まとめ|清拭の正しい手順を知って身も心も寄り添うケアを
清拭は、お風呂に入れない日でも高齢者の清潔と快適を守る大切なケアです。
正しい手順で行えば、皮膚トラブルの予防や血行促進、心のリラックスにもつながります。
介護する人とされる人が穏やかにふれあう時間にもなり、信頼関係を深めるきっかけにもなります。
ただし、日々の介護では体調の変化や急な異変に気づけないこともあるかもしれません。
そんな不安を和らげてくれるのが、見守りサービスです。
見守りを取り入れれば、離れて暮らしていても親の体調や生活の様子を把握でき、必要なときにすぐ対応できます。
日常の清拭やケアを続けながら、家族みんなが安心して過ごせる環境を整えましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら