「耳が遠いと認知症になりやすいの?」
「補聴器をまだ早いと言って嫌がる」
上記のように、ご家族の耳が遠くなってきていることに不安を抱える方も少なくありません。
耳が遠い=補聴器というイメージは強く、多くの方が補聴器を考えがちです。
しかし実際には、補聴器以外にもさまざまな選択肢があり、抵抗がある方でも聞こえの改善に役立つ方法は存在します。
本記事では、補聴器に抵抗がある方のための改善方法・便利グッズ・生活工夫・支援サービスについて詳しく解説します。
聞こえの問題でお悩みの方や、そのご家族にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら補聴器以外で聞こえをサポートする方法
補聴器以外にも聞こえをサポートする方法は多数あります。
主な選択肢を3つのカテゴリーに分けて、それぞれの特徴と適用場面を詳しく見ていきます。
集音器
まず注目したいのが「集音器」です。
集音器は補聴器に比べて安価で操作も簡単な機器です。
補聴器が医療機器として厳しい基準をクリアしているのに対し、集音器は医療機器ではないため手軽に購入できます。
軽度から中等度の難聴の方や「ちょっと聞きづらい」程度の方に適しており、補聴器への第一歩として選択される方も多くいます。
価格帯も数千円から数万円と幅広く、まずはお試しで使ってみたいという方にもおすすめです。
ただし、重度の難聴には対応が困難な場合があることも理解しておきましょう。
骨伝導タイプやネックスピーカー
補聴器以外で聞こえをサポートする方法に、骨伝導タイプやネックスピーカーもあります。
これらの機器は耳をふさがずに音を伝える仕組みを採用しています。
骨伝導は頭蓋骨を通じて音の振動を内耳に直接伝達し、ネックスピーカーは首にかけて使用するタイプで、どちらも耳への圧迫感が少ないのが特徴です。
補聴器のような閉塞感や違和感を嫌がる方にとって、非常に使いやすい選択肢となります。
特に会話やテレビの聞き取りに適しており、長時間使用しても疲労感が少ないというメリットがあります。
外耳道に問題がある方や、耳垢が多い方にも適用しやすい機器です。
音声認識やスマホアプリの活用
耳の遠い高齢者には、音声認識やスマホアプリの活用もおすすめです。
最新のツールを活用した支援方法として、会話を文字に変換できるアプリがあります。
話した人の声を自動的にテキスト化し、画面上に表示してくれるため、聞き取りが困難な場面でも内容を理解できます。
また、Bluetooth対応のスピーカーと組み合わせることで、ノイズをカットしながらクリアな音声を届けることも可能です。
スマートフォンやタブレットを使い慣れている方であれば、比較的簡単に導入できる方法といえるでしょう。
音声認識の精度も年々向上しているため、実用性も高いです。
高齢者の耳が遠い原因とよくある症状
高齢者の耳が遠くなる原因には、大きく3つのパターンがあります。
- 加齢性難聴:高齢者に多い聴力低下
- 病気や外傷による聴力障害
- 日常生活でのサイン
それぞれの特徴を理解することで、適切な対策を選択できるようになります。
加齢性難聴:高齢者に多い聴力低下
高齢者の聴力低下で最も多いのが「加齢性難聴」です。
加齢性難聴は文字通り年齢を重ねることで生じる聴力の低下で、高音域から徐々に聞き取りにくくなる特徴があります。
加齢性難聴は進行性であり、残念ながら薬物治療では改善することができません。
50代から始まることが多く、70代以降では多くの方に見られる症状です。
高音域から聞こえなくなるため、女性や子どもの声が特に聞き取りづらくなることが知られています。
また、騒がしい環境での会話理解が困難になるのも、よく見られる症状の一つです。
病気や外傷による聴力障害
加齢以外にも病気や外傷による聴力障害があります。
中耳炎や耳硬化症、突発性難聴などの病気が原因となって聴力が低下することがあります。
病気や外傷の場合、適切な治療により聴力の改善が期待できるケースもあるのです。
また頭部外傷や騒音による損傷も聴力障害の原因となることがあります。
薬の副作用や全身疾患が関連している場合もあるため、聞こえの異常を感じたら耳鼻咽喉科での診察を受けましょう。
日常生活でのサイン
耳が遠くなっているサインは以下のような症状が特徴で、主に日常生活の中で現れます。
- 聞き返しが増える
- テレビの音量が大きくなる
- 電話での会話が困難になる
- 複数人での会話についていけない
- インターホンや電話の着信音に気づかない
上記のサインに気づいたら、早めに対策の検討が大切です。
家族が先に気づくケースも多いため、周囲の方の観察が重要な役割を果たします。
耳が遠いと高齢者はどうなるのか
高齢者の耳が遠い状態を放置すると、以下のようなさまざまな問題が生じてきます。
- 周囲の音が聞こえず転倒や事故のリスクが増える
- 会話が減り孤立や孤独を招いて社会とのつながりが薄れる
- コミュニケーションが困難になると家族や友人との関係にも影響が出る
- 聴覚の刺激の減少により脳の活動が低下して認知機能に悪影響を与える可能性がある
聞こえの問題は本人だけでなく、家族関係にもストレスを与えることになりかねません。
何度も大きな声で話す必要がある、コミュニケーションがスムーズに取れないなどの状況が続くと、家族の負担も大きくなるでしょう。
高齢者の認知症については、以下の記事も合わせて読んでみてください。

補聴器以外で日常生活でできる聞こえる工夫
補聴器に頼らずとも、日常生活の工夫で聞こえの問題を改善できる方法があります。
コミュニケーションの工夫と家庭環境の音響改善を組み合わせることで、より良いコミュニケーション環境を作ることができます。
コミュニケーションの工夫
まず重要なのがコミュニケーションの工夫です。
耳の遠い高齢者に話しかける際は、ゆっくりとはっきりと話すことを心がけ、必ず正面から声をかけましょう。
口の動きが見えるようにすることで、聴覚だけでなく視覚的な情報も活用できます。
またジェスチャーや表情を豊かにして、言葉以外の手段でも意思疎通を図ることが効果的です。
重要な話をする際は、雑音の少ない静かな環境を選び、一度に多くの情報を伝えるのではなく、要点を絞って話すことも大切です。
高齢者が話の内容を理解できているか確認しながら会話を進めると、誤解や聞き漏らしを防げます。
難聴の高齢者に対するコミュニケーションについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
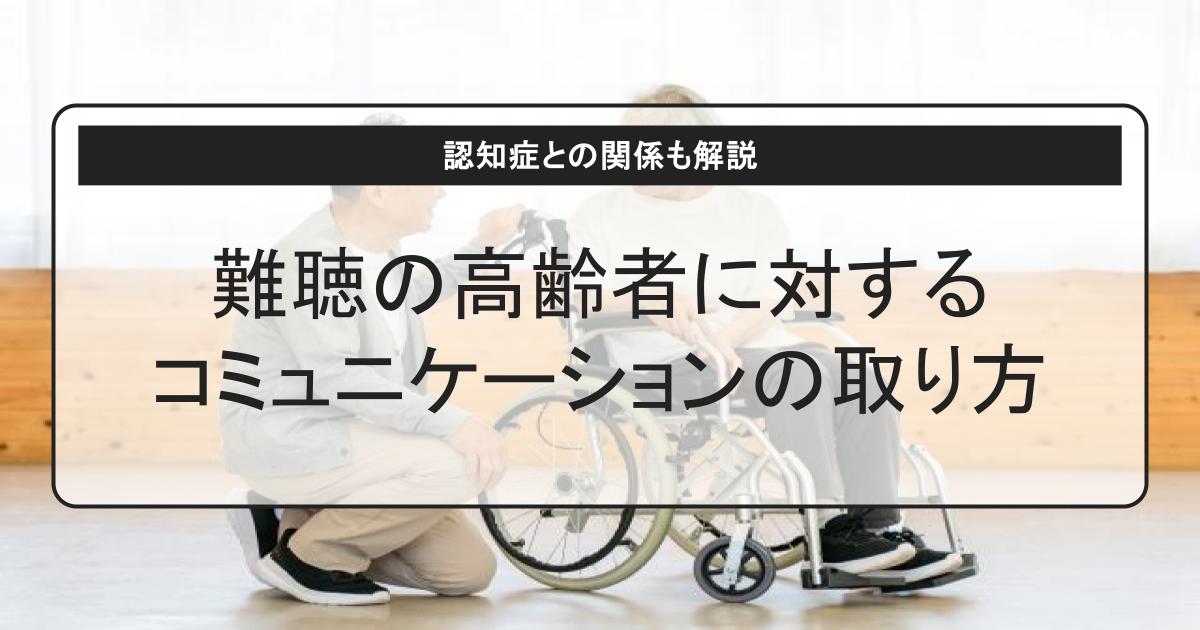
家庭環境の音響改善
次に家庭環境の音響改善が大切です。
室内の反響を減らす吸音材を利用すると、クリアな音環境を作ることができます。
家具の配置を工夫して音の反射を減らせるほか、厚手のカーテン・カーペット・ソファなどにも自然な吸音効果があります。
また、スピーカーやテレビの配置を調整し、聞き手により近い位置に設置することで音量を上げずに聞き取りやすさの向上が可能です。
家庭内の環境改善は比較的費用をかけずに実施でき、家族全員にとって快適な住環境作りにもつながります。
補聴器を嫌がる理由と勧めたい場合の説得の工夫
多くの高齢者が補聴器を嫌がる理由には、見た目への抵抗・高額な費用・使い慣れるまでの大変さなどがあります。
特に「年寄り扱いされたくない」という心理的な背景は非常に強く、自立性やプライドに関わる重要な問題です。
補聴器への抵抗感を和らげる説得方法として、段階的なアプローチが効果的です。
「まずは集音器から試してみませんか」というように、ハードルの低い方法から提案しましょう。
補聴器は短時間から使い始めることで、徐々に聞こえ方に慣れてもらえます。
また、補聴器のメリットだけでなく、聞こえの問題を放置するリスクについても丁寧に説明することが大切です。
家族として本人の気持ちを尊重しながら、根気よく話し合いを続けていきましょう。
一度の説得で諦めず、時間をかけて理解を得る姿勢が重要になります。
高齢者の聴力を観察しながら適切な方法で生活の質を改善
耳が遠い高齢者への対応は、補聴器だけが選択肢ではありません。
集音器・骨伝導機器・音声認識アプリなど、補聴器以外にも多くの選択肢があります。
さらに日常生活でのコミュニケーション工夫や環境改善を組み合わせて、生活の質を改善していきましょう。
何よりも重要なのは、家族の理解と協力です。
本人の気持ちを尊重しながら適切なサポートをすることで、耳が遠い問題に前向きに取り組めるでしょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら









