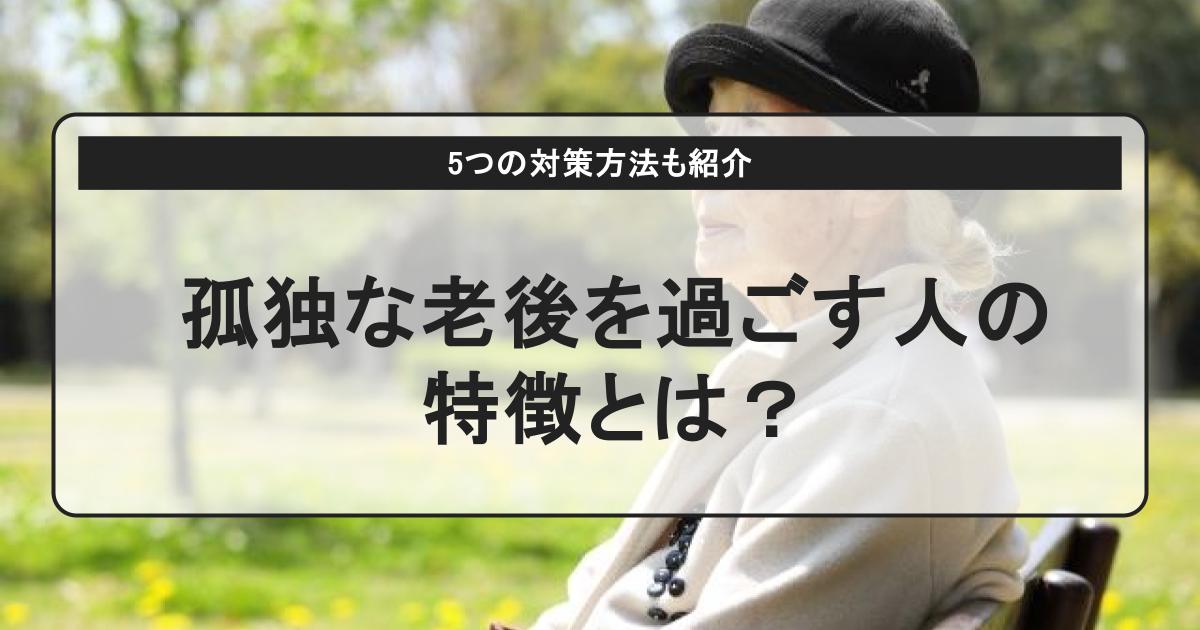「孤独な老後を過ごす人の特徴が知りたい!」
「孤独な老後を防ぐための対策方法は?」
上記のように、孤独な老後を過ごす人の特徴などが気になっている方も多いでしょう。
本記事では、孤独な老後を過ごす人の特徴7選を紹介していきます。
記事内で紹介している「孤独な老後を過ごす人にならないための対策」も参考にしながら、早めに対策していきましょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら孤独な老後を過ごす人が増えている理由とは
近年、日本では孤独な老後を過ごす人が増えています。
その背景には主に「高齢化社会と単身世帯の増加」「家族や地域コミュニティとのつながりの希薄化」「定年後のライフスタイルの変化」という3つの要因があります。
総務省の人口統計によると、2024年10月時点で65歳以上人口は3,624万人、総人口の29.3%を占め、75歳以上は2,078万人に達しています。
長寿化は喜ばしい一方で、内閣府の「高齢社会白書」では65歳以上の単身世帯は2020年時点で男性15.0%・女性22.1%、今後はさらに増加すると予測されています。
加えて、核家族化や転居の増加で地域コミュニティのつながりが薄れ、内閣府の孤独・孤立全国調査では「家族との死別」(24.6%)や「一人暮らし」(18.8%)が孤独感の主要因と報告されています。
さらに、定年退職により職場というコミュニティを失い、生活リズムや人間関係が大きく変わることで孤独を感じやすくなる人も多いのです。
孤独な老後を過ごす人の特徴7選
孤独な老後を過ごす人の特徴として、以下の7つがあります。
- 人間関係が限定的で交友関係が少ない
- 定年後に社会との接点がなくなった
- 経済的不安を抱えている
- 健康不安があるが相談できる人がいない
- デジタル機器に不慣れで情報が限られる
- 趣味や生きがいを見つけられていない
- ネガティブ思考で新しい挑戦を避ける傾向がある
孤独な老後を過ごす人の特徴を知っておくことで、対策方法を考えられるため、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
特徴をあらかじめ知っておけば、早めに対策をして孤独な老後を過ごす可能性を減らせるでしょう。
また、既に孤独な老後を過ごしている方も、それぞれの特徴を改善していくことで、孤独感から抜け出せる可能性が高まります。
ここからは孤独な老後を過ごす人の特徴7選について具体例を交えながら、詳しく解説していくのでぜひ参考にしてください。
① 人間関係が限定的で交友関係が少ない
孤独な老後を過ごす人の特徴の1つ目は、人間関係が限定的で交友関係が少ないことです。
交友関係が狭い方は、何気ない会話や相談相手が限られるため、孤独を感じやすくなります。
実際に内閣府の全国調査(2025年)によると、「日常的に相談できる人がいない」と答えた高齢者は、約21.7%に上ります。
人間関係が限定的な場合は、体調不良や生活の悩みなどを共有できず、一人で問題を抱え込んでしまう場合も少なくありません。
さらに、近隣住民との会話が減少すると、地域活動や支援情報などが耳に届きづらくなるため、より孤独感が強まります。
② 定年後に社会との接点がなくなった
孤独な老後を過ごす人の特徴の2つ目は、定年後に社会との接点がなくなった方です。
定年退職は生活の大きな転換点であり、仕事で築いた社会的役割や人間関係を失うきっかけになりやすいです。
退職後は自由な時間を楽しめるという魅力もありますが、予定のない日々が続くと寂しい・孤独といった感情を感じやすくなります。
「定年後のライフスタイルの変化」でも紹介したように、転職や退職が孤独感に影響していると感じている方は多いです。
退職後は収入も減少するため、外出や旅行を控えてしまう高齢者も多く、活動範囲が狭くなりがちです。
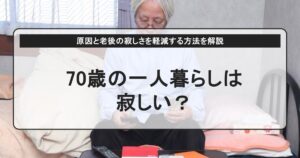
③ 経済的不安を抱えている
孤独な老後を過ごす人の特徴の3つ目は、経済的不安を抱えていることです。
老後2,000万円問題が話題になっており、老後の経済的不安を気にしている方も多くいます。
内閣府の「高齢社会白書(2024年)」によると、65歳以上の高齢者世帯の平均所得は318.3万円であり、現役世代世帯669.5万円の約半分になります。
経済的不安がある高齢者は、交通費・交際費などを節約するために、外出を控えがちです。
さらに、健康維持のためのスポーツや学び直しなどの自己投資が減少する場合も多く、社会的な孤立が強まりやすいです。
④ 健康不安があるが相談できる人がいない
孤独な老後を過ごす人の特徴の4つ目は、健康不安があるが相談できる人がいないという点です。
日々の生活における不安を相談できる相手がいないことは、孤独感を強める大きな原因になるとされています。
「通いの場」への参加を調査した研究では、通いの場に参加した後期高齢者の要介護リスク5点以上の悪化リスクが46%抑制されたことが分かっています。(通いの場とは、高齢者が定期的に集まり、交流や活動を行う地域拠点のことです)
体調の異変を相談できる相手がいない場合は、医療機関の受診や生活改善が遅れて、症状が悪化するケースも少なくありません。
⑤ デジタル機器に不慣れで情報が限られる
孤独な老後を過ごす人の特徴の5つ目は、デジタル機器に不慣れで情報が限られている点です。
インターネットやスマートフォンなどの利用が苦手な高齢者は、情報収集やコミュニケーションの機会が減少しがちです。
高齢者のインターネット利用率の調査では、65歳以上のインターネット利用率は60.9%に達しています。
一方、80歳以上では36.4%にとどまっています。
近年では、地域のイベント・福祉サービス・オンライン講座などの告知をWeb上で行っている場合が多いです。
そのため、デジタル機器に不慣れな高齢者は、情報格差が生まれやすいです。
また、離れて暮らす家族・友人とオンラインでつながる機会を失ってしまうことも孤独な老後を過ごす原因になります。
⑥ 趣味や生きがいを見つけられていない
孤独な老後を過ごす人の特徴6つ目は、趣味や生きがいを見つけられていない点です。
高齢者は退職をして時間がある方も多いですが、打ち込める趣味や生きがいがない場合、孤独感を感じやすいです。
趣味や活動は気分転換だけではなく、他者との交流機会を生む役割もあります。
例えば、地域のサークル活動・ボランティア・オンライン学習会などに参加すると、同じ関心を持つ人との出会いが増加します。
高齢者が趣味を持たないことは、さまざまな問題に発展する恐れがあるため、以下の記事で趣味を持つ重要性について理解しておきましょう。
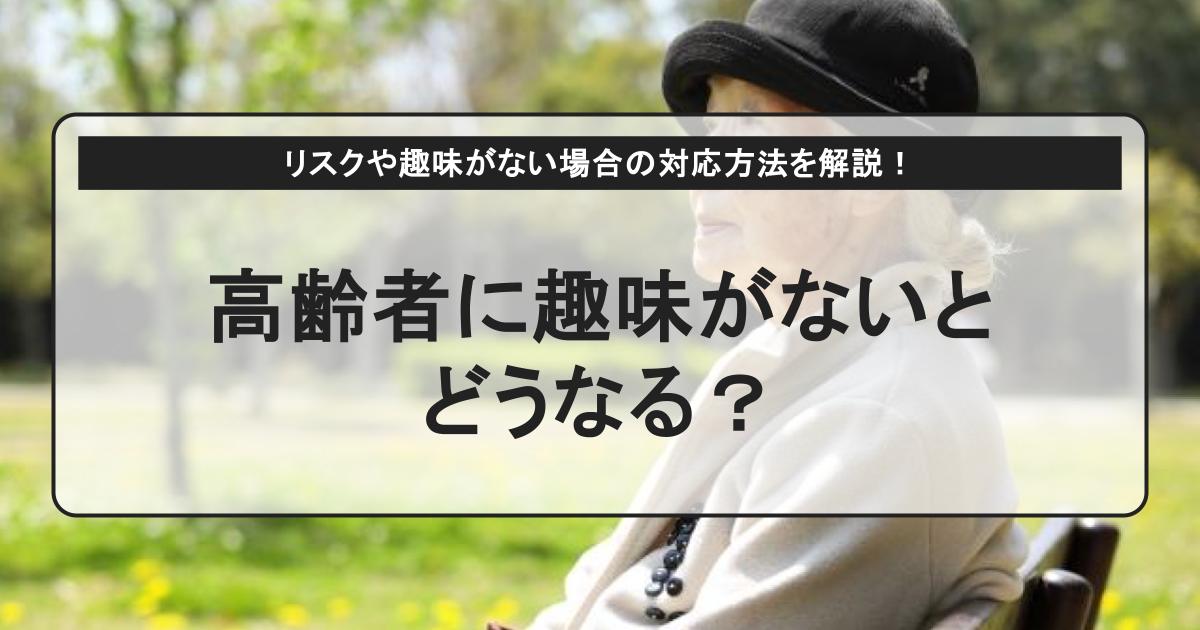
⑦ ネガティブ思考で新しい挑戦を避ける傾向がある
孤独な老後を過ごす人の特徴7つ目は、ネガティブ思考で新しい挑戦を避ける傾向がある方です。
「自分には向いていない」「今さら始めても遅い」などの否定的な思考を持つ高齢者も多いですが、孤独感を強める原因になります。
新しい環境に踏み出すことをためらうと、人間関係や活動範囲が狭まり、孤立しやすくなるのです。
また、ポジティブな思考を持つ高齢者は、主観的な幸福度が高く、孤独感を抱きにくい傾向があるという研究結果もあります。
そのため、「うまくやる」よりも「試すこと」自体に価値を見出すのがおすすめです。
孤独な老後を過ごす人にならないための対策
孤独な老後を過ごす人にならないための対策方法として、以下の5つが挙げられます。
それぞれの対策方法を詳しく解説していくので、「孤独な老後を過ごしたくない」と考えている方は参考にしてください。
人間関係を広げる工夫
孤独な老後を過ごす人にならないための対策の1つ目は、人間関係を広げる工夫をすることです。
実際に厚生労働省は高齢者の地域参加を推奨しており、「高齢者の社会参加は心身の健康維持に効果がある」としています。
地域のサークル活動やボランティア、自治体主催の交流会などは、共通の話題を持つ仲間を見つけやすいです。
さまざまなイベントに積極的に参加し、コミュニケーションを取れる環境を整えていきましょう。
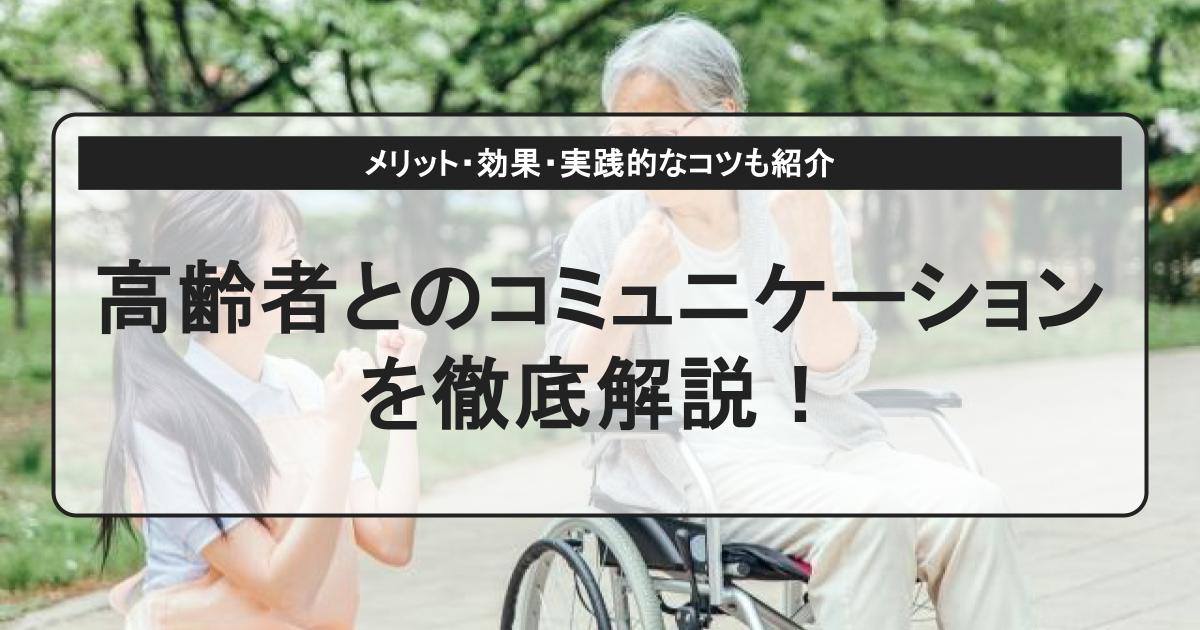
経済的な備えと老後資金の見直し
孤独な老後を過ごす人にならないための対策の2つ目は、経済的な備えと老後資金の見直しです。
単純に収入源を確保するだけではなく、使える制度を知ることも重要です。
例えば、「高齢者生活支援サービス」では、家事援助・買い物代行などのサービスを低額で利用できます。
また、各自治体で実施されている「シルバー人材センター」では、短時間の仕事が紹介されており、収入を補いつつ新しい人間関係を築けます。
健康維持のための習慣づくり
孤独な老後を過ごす人にならないための対策の3つ目は、健康維持のための習慣づくりです。
「健康づくりのための身体活動基準」では、高齢者は1日40分程度の軽い運動を取り入れることが推奨されています。
軽い運動だけでも、筋力の維持や生活習慣病の予防につながるため、外出頻度の低下を防ぐことが可能です。
外出頻度の低下は、高齢者にさまざまな問題を引き起こす恐れがあるため、注意する必要があります。
健康講座や体操教室などに参加すれば、周囲とのコミュニケーションも活発になるのでおすすめです。

デジタル活用で情報や人とつながる
孤独な老後を過ごす人にならないための対策の4つ目は、デジタル活用で情報や人とつながることです。
デジタル機器は、情報収集や人との交流を増やすために便利なツールです。
デジタル機器に慣れていない高齢者向けに「デジタル活用支援」などのサービスも提供されており、スマホの基本操作やLINEの使い方などを学べます。
「スマートフォンを使いこなせるようになりたい」と考えている高齢者は、ぜひ活用してみましょう。
新しい趣味や学びで生きがいを見つける
孤独な老後を過ごす人にならないための対策の5つ目は、新しい趣味や学びで生きがいを見つけることです。
趣味や学びなどの活動は、老後の生活にメリハリをつけられるため、孤独を防ぎやすくなります。
「高齢者の生涯学習参加に関する研究」では、趣味や学習活動に積極的に参加する高齢者は、幸福度が高く健康状態も良好な傾向があるとされています。
趣味や学びなどの新しい活動は、自己肯定感を高めて充実感を得られるので、孤独な老後を避けるためにおすすめの方法です。
また、自宅でもできるおすすめの過ごし方を紹介しているので、以下の記事も参考にしてください。
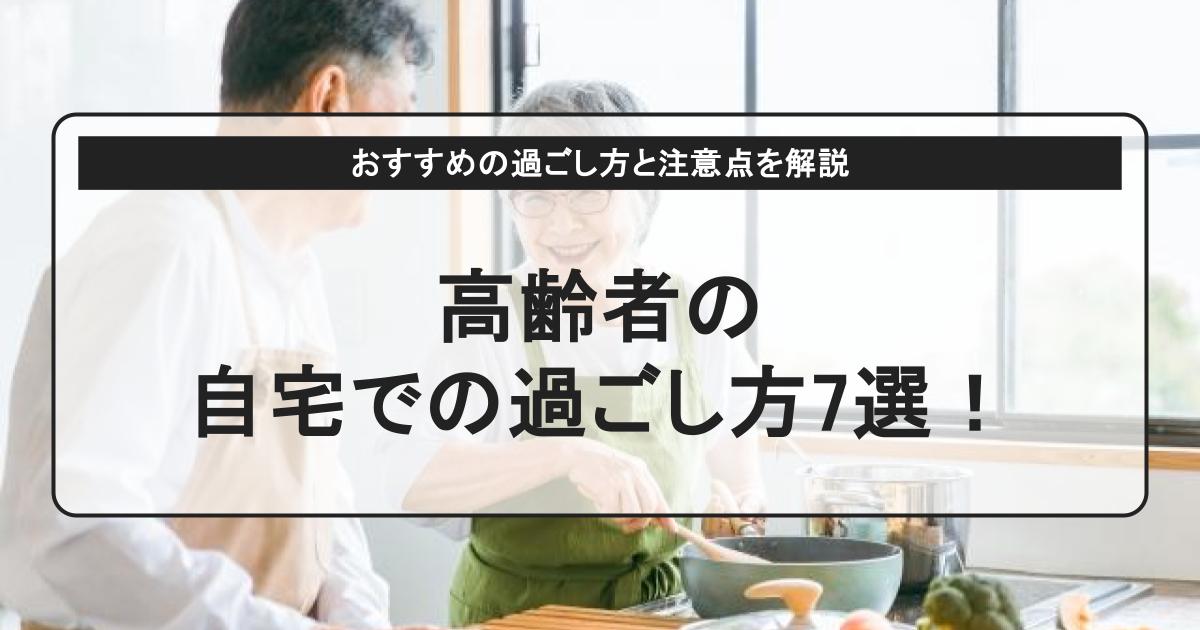
まとめ|孤独な老後を避けるために今からできること
本記事では、孤独な老後を過ごす人の特徴について詳しく解説しました。
日本では高齢化の進行に伴い、孤独な老後を過ごす人が増えています。
その背景には、単身世帯の増加や地域とのつながりの希薄化、定年後のライフスタイルの変化などが影響しています。
しかし、孤独は未然に防ぐことが可能です。人間関係を広げる工夫や経済的な備え、健康維持の習慣づくりに加え、デジタル活用や新しい趣味への挑戦が効果的です。
早めに行動を起こし、社会とのつながりを意識的に持つことで、安心で充実した老後を実現できるでしょう。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら