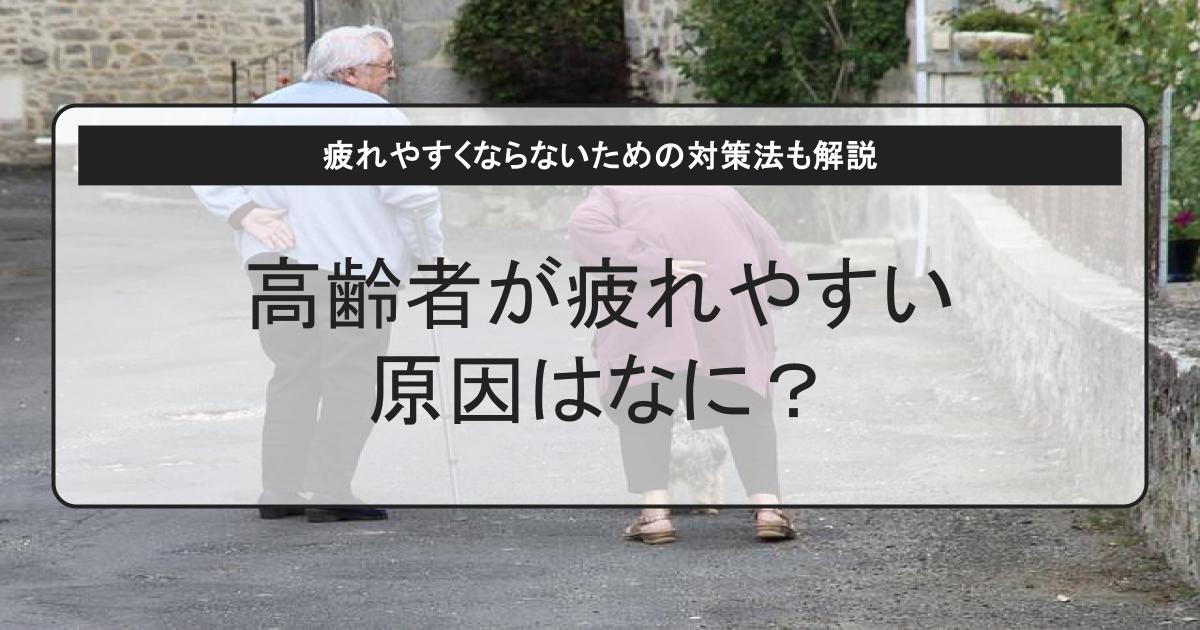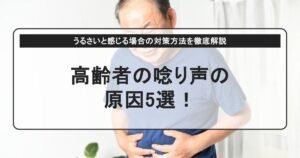「高齢者の親がなんだか最近疲れやすくなっている気がする」
「そもそも疲れやすい原因は何?」
上記のようにお悩みではありませんか?
疲れやすい原因には栄養不足や運動不足、さらには睡眠の質や持病の影響など、さまざまな要因が潜んでいます。
この記事では、疲れやすさの主な原因と、自宅でできる簡単な対策を紹介しています。
高齢者が元気に毎日を過ごすためのヒントを、ぜひチェックしてみてください。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら高齢者が疲れやすい原因とは?
年齢を重ねると、若いころと比べて体力の回復に時間がかかったり、少しの活動でも疲れを感じやすくなったりすることがあります。
その原因は「年のせい」と一括りにされがちですが、実際にはさまざまな体の変化や生活習慣が関係しています。
まずは高齢者が疲れを感じやすくなる具体的な原因について、詳しく見ていきましょう。
栄養不足
高齢者が疲れやすくなる原因の一つ目が、栄養不足です。
高齢になると食欲が落ちたり、偏った食事になりがちだったりして、体に必要な栄養素が不足しやすくなります。
特に疲れやすさに関係する栄養素が不足すると、体がうまく機能せずだるさや倦怠感を引き起こしやすくなるのです。
ここからは、疲労感に関わる代表的な栄養素について詳しく解説していきます。
糖質不足
糖質が不足すると、高齢者は疲れやすくなることがあります。
糖質(炭水化物)は体内で分解されることでブドウ糖などに変わり、細胞が活動するためのエネルギー源として使われます。
過剰に摂取すると肥満の原因になりますが、逆に不足すると体を動かすためのエネルギーが足りなくなり、疲れやすくなってしまうのです。
鉄分不足
鉄分は、体内の細胞へ酸素を運ぶ役割を担っています。
この鉄分が不足すると、貧血を引き起こしやすくなり、以下のような不調が現れるようになります。
- 疲れやすさやだるさを感じる
- 力が出ない
- 食欲がわかない
- 息切れする
特に女性は月経によって多くの鉄分を失うため、男性よりも鉄分不足になりやすい傾向があるため注意が必要です。
タンパク質不足
タンパク質は、骨・筋肉・血液・内臓など、体をつくるうえで欠かせない栄養素で、生命維持にとっても非常に重要です。
不足すると筋肉の量や力が低下しやすくなり、貧血を引き起こすこともあります。
その結果、疲れを感じやすくなってしまうのです。
高齢者のタンパク質についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

ビタミンB不足
ビタミンB群は、タンパク質・脂質・糖質といった栄養素をエネルギーに変える過程で必要となる成分です。
特にビタミンB1・B2・B6は疲労回復を助ける働きがあり、これらが不足するとエネルギーの生成がうまくいかず、疲れを感じやすくなります。
高齢者の栄養対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

運動不足
運動不足も高齢者が疲れやすくなる原因の一つです。
運動不足になると新陳代謝が落ち、水分や血液の巡りが悪くなってしまいます。
その影響で筋肉に乳酸がたまりやすくなり、疲労感が出やすくなるのです。
また体を動かさない生活は、精神的なストレスや神経的な疲れを引き起こす要因にもなりやすいと言われています。
睡眠不足
高齢者が疲れやすくなる原因の一つに、睡眠不足もあります。
睡眠は、体と脳をしっかり休めるために欠かせないものです。
眠っている間には、細胞の働きを活発にする成長ホルモンが分泌されたり、食事から摂った栄養が吸収されてエネルギーへと変わったりしています。
睡眠時間の長さだけでなく、眠りの深さ=質も重要で、浅い眠りが続くと疲労がなかなか解消されにくくなります。
以下の記事では高齢者の睡眠について詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
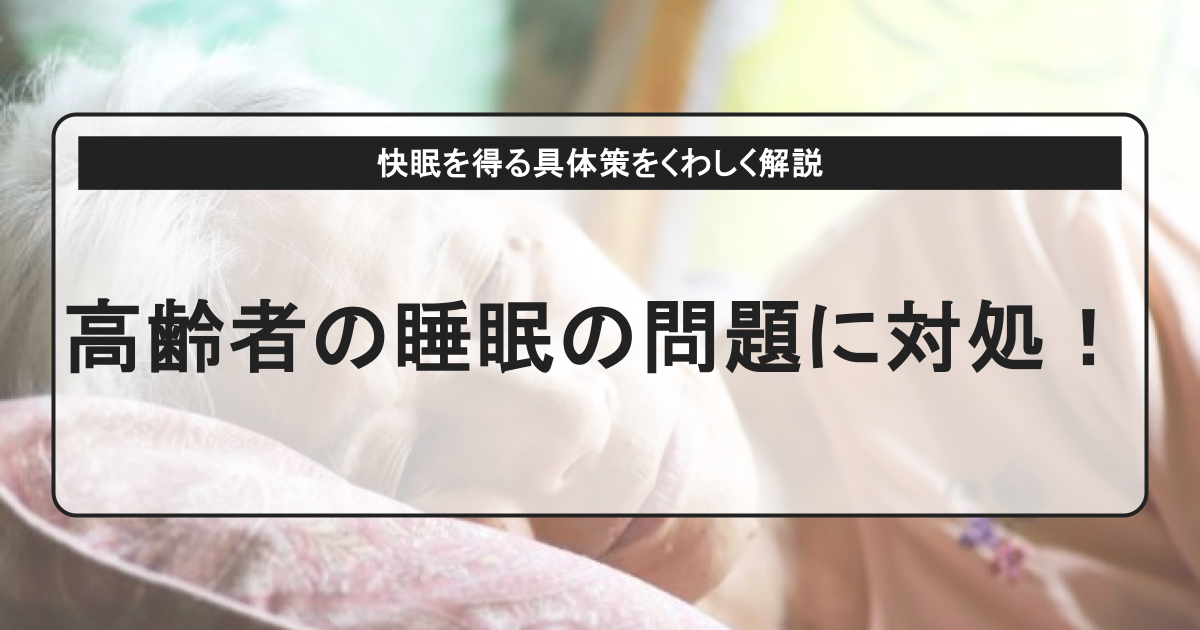
低血圧
高齢者は低血圧によっても、疲れやすくなることがあります。
低血圧になると、体全体の血流が悪くなり、脳への血液供給が不足します。
その結果体がだるく感じたり、頭痛・ふらつき・めまいといった症状が現れやすくなるため、注意が必要です。
糖尿病
糖尿病によっても、高齢者が疲れやすくなることがあります。
糖尿病は、高血糖が長期間続くことで免疫力が低下し、さまざまな病気にかかりやすくなる状態です。
その影響で疲れが取れにくかったり、体のだるさが長引いたりすることがあります。
もし健康診断で血糖値やHbA1cが基準を超えていると指摘された場合は、定期的に検査を受けることが大切です。
貧血
貧血は、血中のヘモグロビンが減少することで、酸素が全身に十分に供給されにくくなる状態です。
ヘモグロビンは本来、酸素を体中に運ぶ重要な役割を担っていますが、不足するとさまざまな症状が現れます。
貧血の原因は多様で、年齢や性別によっても異なります。
特に女性は月経や胃潰瘍、十二指腸潰瘍が影響することがあり、高齢者では血液の病気や悪性腫瘍が原因となることもあるのです。
月経に関連する場合、血の塊や過多月経が見られることが多く、胃潰瘍では食事中にみぞおち周辺の痛みやむかつき、胃もたれが現れます。
十二指腸潰瘍では、空腹時に痛みを感じることがあります。
また、皮下出血や体重減少がある場合も注意が必要です。
うつ病
うつ病の明確な原因はまだ解明されていませんが、体や心にかかるストレスが引き金となり、脳の機能に異常が生じることで症状が現れると言われています。
気分が落ち込み、興味を持つことが難しくなり、すぐに疲れを感じたり、睡眠障害や食欲の低下が見られたりするようになります。
その結果日常生活が困難になることもあるため、注意が必要です。
高齢者の疲れやすさへの対策
高齢者が感じる疲れやすさは、睡眠や入浴などの生活習慣を見直すことで改善できる傾向にあります。
ここからは疲れを軽減し、健康的な体調を維持するために効果的な対策を紹介します。
これから紹介する方法を日常生活に取り入れることで、心身の状態を整え、元気に過ごすためのサポートになるでしょう。
良質な睡眠をとる
十分な睡眠を確保することは、体と脳をしっかりと休めるために大切です。
日中に眠気を感じたり、集中力が低下していたりする場合、睡眠不足が原因かもしれません。
睡眠は時間を確保するだけでなく、質も重要です。睡眠の質を高くするには、枕の高さや寝室の照明を調整するなど、リラックスできる環境を整えることをおすすめします。
また、就寝前にスマホを使うと脳が刺激され、睡眠の質が悪化する可能性があるため、注意が必要です。
さらに、休日だからといって夜更かしや寝坊をすると、体内時計が乱れ睡眠の質が低下します。
睡眠中は体力回復や脳の休息、記憶の整理、免疫力の強化が行われます。
質の高い睡眠を心がけ、生活リズムを整えることを意識していきましょう。
筋肉をほぐす
疲れを解消するためには、体をほぐすことが効果的です。
固まった筋肉をゆっくりと伸ばすことで、血行が改善され、酸素や栄養が全身に行き渡りやすくなります。
さらに、筋肉に溜まった疲労物質である「乳酸」をスムーズに排出する手助けにもなるのです。
また筋肉ほぐしは体の疲れだけでなく、精神的な疲労にも良い影響を与えることができます。
筋肉を伸ばすことで副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定して、体がリラックスします。
ストレッチの効果を最大限に引き出すためには、腹式呼吸を意識するのがおすすめです。
鼻から深く息を吸い込み、お腹に空気を入れ、口からゆっくり吐き出すようにしましょう。
この呼吸法により、副交感神経が活発になり、リラックス効果が高まります。
特にお風呂後や寝る前の15分程度にストレッチを行うのが理想的です。
ただし、寝る前に激しい運動をすると眠りが浅くなる可能性があるので、注意が必要です。
栄養バランスの整った食生活を心がける
1日3回の食事で栄養バランスを意識することは、疲労回復に大きく役立ちます。
特に朝食と昼食はしっかり摂るよう心がけ、夕食は控えめにして胃腸への負担を軽減することがポイントです。
ご飯やパンなどの糖質(炭水化物)はエネルギー源になりますが、それだけでは疲れが取れにくいです。
そこで、ビタミンB1などの栄養素を一緒に摂取すると糖質の代謝がスムーズになり、効率よくエネルギーに変換されます。
糖質に限らず、どの栄養素も偏って摂るとうまく機能しません。
栄養素同士が助け合うことで本来の働きを発揮するため、日々の食事では栄養のバランスを意識することが大切です。
じっくり湯舟に浸かる
疲れが溜まっていると感じたときは、湯船にゆっくり浸かることで疲労回復が期待できます。
入浴によって体がしっかり温まり、血流やリンパの流れが促進されることで、老廃物の排出がスムーズになり回復を助けてくれます。
また、筋肉のこわばりがほぐれて心身がリラックスし、精神的な疲れの軽減にもつながるでしょう。
ただし、熱すぎるお湯に長時間入ると逆に疲れてしまうことがあるため注意が必要です。
40度以下のぬるめのお湯に、10分ほどを目安にゆったり浸かるのがおすすめです。
「高齢者の親が入浴拒否して困っている…」という方は、以下の記事も合わせて参考にしてください。
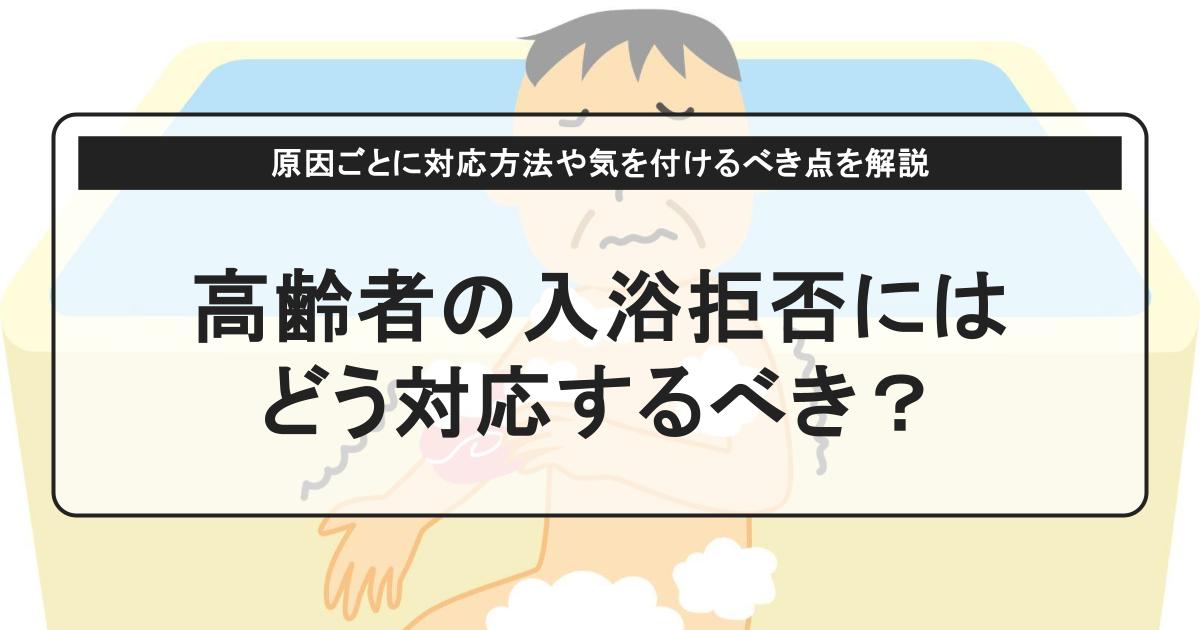
適切な運動を心がける
疲れを感じているときこそ、無理のない範囲で軽く体を動かすことが有効です。
軽めの運動をすることで血流が良くなり、筋肉に溜まった乳酸が排出されやすくなります。
さらに、神経伝達物質の「セロトニン」が分泌されることで、自律神経が整い、精神的な疲れや神経の高ぶりが和らぐ効果も期待できます。
イライラした気持ちやストレスを軽減するのにも役立つでしょう。
ただし、強度の高い運動はかえって疲労を感じやすくなるため、自身が楽しめる内容で心地よく続けられる範囲の運動を心がけることが大切です。
高齢者の疲れやすい原因は人それぞれ
高齢者が疲れやすくなる原因には、栄養不足・運動や睡眠の不足・血流や代謝の低下など、加齢に伴う体の変化や生活習慣の影響が関係しています。
糖質やビタミンB群、鉄分、たんぱく質などを意識したバランスの良い食事を心がける、軽い運動やストレッチで血流を促す、そして質の高い睡眠をとるなどが、疲れをためにくくするポイントです。
無理のない範囲で生活を整えることで、心身ともに健やかに過ごす力が高まります。
なおご家族と離れて暮らしている場合は、体調や生活の変化を見逃さないよう「見守りサービス」の活用もおすすめです。
日々の様子をそっと見守り、もしものときもすぐに対応できる安心を届けます。
- 費用をおさえて離れて暮らす親を見守ることができる
- Wi-Fiや設置工事が必要ない
- 誤検知や無駄な通知がない
-1.png)
現在、上記のようなサービスをお探しでしたら、ぜひとも私どもの「ハローライト」をご検討ください!ハローライトは電球の点灯を検知することで離れて暮らす親の安否確認ができる見守りサービスです。
\ サービスが評価され2023年度グッドデザイン賞を受賞 /
ハローライトについて詳しくはこちら